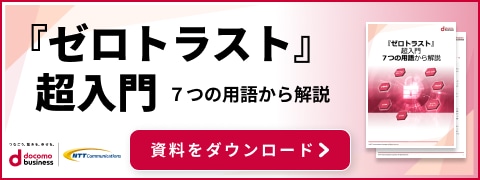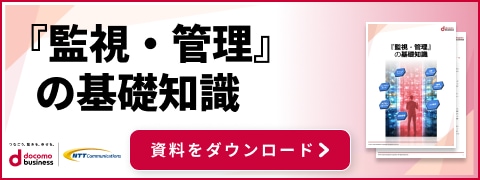ネットワーク可視化の方法と
可視化ツールのメリット・デメリット
近年さまざまな業界でIT化が進んでおり、PCをはじめとする多くのデジタル機器がネットワークに接続されることで、利便性が高まっています。しかし、接続不良や通信速度が低下した場合に、ネットワーク内のどこで問題が発生しているのかわかりにくいのが欠点です。そこで、ネットワークの全体把握が実現できるように、ネットワークの可視化が求められています。
本記事では、ネットワークの可視化の概要や可視化の方法、監視ツールの必要性などを解説します。

目次
ネットワークの可視化とは?
ここでは、ネットワークの可視化とは具体的にどのようなものなのかを解説し、ネットワークの可視化により解決できることや、可視化に必要なソリューションを紹介します。
ネットワーク全体の状態を確認できるようにすること
ネットワークの可視化とは、サーバーやルーター、PCなどの機器が、どのように関連しあい、どのような状態でつながっているのかを一目でわかるようにすることです。
可視化に用いるネットワーク構成図に明確なルールはありませんが、大きく物理構成図と論理構成図の2種類に分けられます。
物理構成図は、機器が設置されたフロアや設置台数などを明らかにして、ネットワーク機器の物理的な配置を図にしたものです。一方、論理構成図は、IPアドレスなどにより情報の流れを明らかにしたものを指します。
さらに、構成図内で、機器の通信状態や接続状態を色分けしてわかりやすく表現すれば、ネットワーク全体の状態が一目で把握できるようになるでしょう。
現在のネットワーク環境は、PC1台をとってみても、ルーターやプリンターなど複数の機器につながっており、非常に複雑化しています。これらを一目で把握できるように可視化することは、そう簡単ではない困難な作業であることも事実です。
しかし、企業がビジネスを進める上でネットワークを可視化していなければ、外部から不正アクセスされた場合に、不審な接続をただちに検知できません。また、従業員が勝手にインストールしたアプリケーションなどの、いわゆるシャドーITについても、ネットワークの可視化により通信を監視することで、その存在に気付きやすくなります。このようにセキュリティの面からも、ネットワークを可視化する必要性は増しているのです。
トラブルの原因を見つけやすく迅速に解決できる
ネットワークを可視化する目的は、ネットワークのトラブル予防や、迅速な解決です。
ネットワークをあらかじめ可視化しておけば、トラブルが発生した際にどこに問題が発生したのかが一目でわかるため、解決までにかかる時間を短縮できます。
また、トラブルまでには至らない場合でも、ネットワークの可視化は役立ちます。ネットワークが可視化されていないと、明らかなトラブル以外には気付きにくいものですが、可視化されていれば、ネットワークの性能低下を把握しやすいでしょう。
ほかにも、ネットワークの可視化により、機器の通信状態や接続状態を確認できるため、アクセス集中による速度低下も把握できます。混雑する時間帯がわかっていれば、作業を行う時間を分散させて通信の集中を防ぐことも可能です。
可視化システムの開発が必要になる
ネットワークを可視化すれば、効率的なトラブル対応ができますが、可視化するためにはシステム開発が必要になります。複雑なネットワークの状況をリアルタイムで把握することは容易ではなく、実現するにはコストや手間がかかるでしょう。
また、ネットワークの可視化は一度開発したら終わりではなく、拠点が増えるなどでネットワーク環境が変化すれば、それに合わせて構成図も作り替えなければなりません。つまり、可視化されたネットワークを長期間、効率的に運用していくためには、誰でも構成図を作成・更新できる体制を整える必要があります。
ネットワークの可視化を実現させる3つの方法

ネットワークの可視化を実現させるには、どのような方法があるのでしょうか。ここでは関連性の高い3つの方法を紹介します。
1.手動でネットワーク構成図を作成する
1つめは手動でネットワーク構成図を作成する方法です。構成図は、ExcelやPowerPoint、マインドマップなどを使えば作成できます。ネットワーク機器のつながりだけを可視化したいのであれば、この方法でも対応可能です。
ただし、ネットワーク環境は日々変化することから、1台1台の接続状況を人力で確認する手間がかかります。ネットワークを構成する機器が少ないうちは手動でも対応できるかもしれませんが、機器が増えると難しくなるでしょう。
また、この方法では機器間のリアルタイムの接続状況がわかりません。そうしたことから、労力がかかる割にはメリットがそれほど得られない方法ともいえます。
2.専用ソフトウェアやサービスを活用する
2つ目は、専用の可視化ソフトウェアやサービスを活用する方法です。1つめの手動による方法と比べると、自動化されることで効率良くネットワークを可視化できるでしょう。リアルタイムで状況を把握できるなど機能が充実しているため、トラブルが発生した場合に迅速かつ的確に対応できる点もメリットです。
デメリットは利用料金がかかる点ですが、なかには機能が制限された無料版や、一定期間無料で利用できる体験版が用意されていることもあります。とりあえず無料で使ってみて、使い心地が良ければ有料版のサービスを利用するのも一つの方法です。
3.無料のオープンソースソフトウェアを導入する
3つ目はオープンソースソフトウェアを使う方法です。可視化ソフトウェアのなかには、オープンソースソフトウェアとして無料でダウンロードして利用できる製品もあり、コストをかけずにネットワークの可視化ができます。無料とはいっても、機能が充実したソフトウェアが多く、有名なZabbixやNagios Coreなども無料のオープンソースソフトウェアです。
ライセンスによってはソフトウェアをカスタマイズできるものもあり、自社の状況に合わせて細かな調節ができれば、ネットワーク全体の状況をより把握しやすくなるでしょう。ただし、利用するにはネットワークやソフトウェアのことを熟知している人材が必要です。詳しい内容は次の章で解説します。
オープンソースソフトウェアの利用には注意が必要

ネットワークを可視化する方法の一つとして、オープンソースソフトウェアを利用する方法を紹介しました。無料のオープンソースソフトウェアであれば、費用をかけずに充実した機能を利用し、可視性を向上できますが、注意すべき点もあります。ここでは、オープンソースソフトウェアを利用する際の3つの注意点を解説します。
1.高い技術力が必要
多くの場合、オープンソースソフトウェアはメーカーのサポートが期待できないため、導入時の各種設定やカスタマイズは自社で行なわなければなりません。自社のネットワークに合わせてカスタマイズするには、高い技術力が必要です。また、バグや脆弱性が放置されている場合もあり、変更などへの対応も自社で行う必要があります。
設定やカスタマイズの方法がわからない場合や、設定にミスがありうまく動作しない場合は、導入に失敗する可能性があるため注意が必要です。
2.日本語で利用できない
オープンソースソフトウェアは海外のものが大半を占めているため、マニュアルや製品の公式サイトは日本語化されていないことが多く、外国語で対応しなければならないことがあります。
しかも、単に外国語ができれば良いというわけではなく、ネットワークやソフトウェアの専門知識がなければマニュアルの理解が難しいため、外国語とネットワークのどちらにも精通した人材が必要です。
また、オープンソースソフトウェアは一切の制約なく使えるというわけではなく、ライセンスにもとづいて使用しなければなりません。違反した場合は訴訟問題に発展する場合もあるため、ライセンスが外国語で記載されている場合でも、内容を正確に把握する必要があります。
3.無料版ソフトは機能が制限されていることもある
有料のオープンソースソフトウェアで無料版を使用する場合、有料版の機能を制限した状態で提供されていることがあります。この場合、自社に必要な機能が使えない可能性があるでしょう。
また、無料版は基本的にサポート対象外のため、トラブルが発生した場合も自社で解決しなければならないなど、細かな部分で使いにくさが目立ちます。
当初はコストのかからない無料版が良いと感じていても、このような使いにくさが頻発すると、稼働もかかり結果的に有料版にしておけば良かったと感じることにもなるでしょう。
オープンソースソフトウェアを導入するメリット
一方でオープンソースソフトウェアの導入で得られるメリットも少なくありません。主なメリットは以下の4点です。
1.信頼性が高いため安定・安心して利用できる
ソースコードが公開されているため、第三者機関に監査を依頼して信頼性や透明性の担保できます。一般的なソフトウェアではソースコードが公開されておらず、どのように動作しているのかを監査できず、さらに開発企業の倒産や合併などによりサービスが終了するリスクがあります。また、ユーザーやコミュニティーがソースコードを修正・改良することで、安定的な稼働と継続的に改善される点もポイントです。
2.柔軟性・自由度が高い
オープンソースソフトウェアはソースコードの構造や仕組みを容易に閲覧できることに加え、利用状況や必要に応じて、自由にカスタマイズを行える特長を持っています。たとえプログラミングの知識がなくても、プラグインを利用する、あるいは既存システムや最新技術との連携を図ることで、さまざまなニーズに対応できます。
3.導入・運用コストを大幅に抑制できる
基本的にオープンソースソフトウェアは無償でソースコードが公開されています。多くのサービスを無料で利用できることため、導入やシステムの設計・導入にかかるコストの大幅な削減が実現できます。加えて、ライセンスの管理費やシステム交換などの維持費も抑えられるため、自社に適したコストモデルの設計が可能です。
4.迅速にバグや脆弱性を解決できる
ユーザー数の多いオープンソースソフトウェアほど公開されている情報が多く、バグや脆弱性を発見された場合でもコミュニティー内で迅速に対処されるため安全に利用できます。
いま、注目のネットワーク可視化ツールとは?
ラトビアのZabbixLLCが開発した総合システム監視ソフトウェア「Zabbix」は、世界的な実績を持つ非常にすぐれたオープンソースのソフトウェアです。サーバーからネットワーク、アプリケーションまで一元的な監視が可能。エンドツーエンドのネットワーク監視はもちろん、ログ監視、死活監視(Ping監視)、サービスポート(TCP)監視、CPU使用率監視、メモリー使用率監視、ディスク使用率監視、プロセス監視、トラフィック監視、Web監視などにも対応しています。
機器間の結線情報を束ねて構造情報に変換する「 T-View 」機能などを活用することで、ネットワークを軸にしたシステム全体を俯瞰した稼働状況の可視化も実現可能です。
しかし、先に挙げたオープンソースソフトウェアであるがゆえの注意点をクリアしておく必要があります。Zabbxを熟知する信頼できるパートナーを選定することは、有効な解決策の1つと言えるかもしれません。
「ZABICOM」は、NTTドコモビジネスが提供するZabbixを用いた統合監視ソリューションです。Zabbixのプレミアムパートナーとして数多くの実績を持つNTTドコモビジネスが、検討段階のコンサルティングから導入、運用、保守までトータルにサポート。導入時の各種設定やカスタマイズ、日本語によるわかりやすいマニュアルの提供、機能制限のないオールインワンパッケージの的確なピックアップまで、NTTドコモビジネスが伴走してお手伝いします。オープンソースソフトウェア実装の注意点、課題がクリアにできることが大きな魅力です。主な提供サービスは以下の通りです。
導入検討フェーズ
「ご提案」
お客さまに最適な導入プランをご提案します。
「導入コンサルティングサービス」
新規、移行、コスト削減など、お困りの内容についてZabbix導入から運用設計までコンサルティングします。
保守サポート
「お客さまサポート窓口の設置」
ZABICOM(Zabbix)に関するお問い合わせ(使用方法、不具合、故障など)の問題解決をサポートします。
さらにZabbixのトレーニング体制も充実。「Zabbix LLC 認定の研修トレーナー」 を擁しており、スキルアップに向けた認定研修プログラムを定期的に開催しています。
まとめ
近年では企業におけるIT化が進んでおり、社内にネットワークを構築している企業は少なくありません。ネットワークには不正アクセスなどのセキュリティリスクがあることから、ネットワークを可視化する必要性が増しています。
ネットワークを可視化するには、手動での構成図作成、専用ツールの利用、オープンソースソフトウェアの利用などの方法がありますが、頼りになるパートナーが確保できるなら、オープンソースソフトウェアの利用をおすすめします。高い技術力や語学力を持つ人材をプロに託せるためです。まずは、既存の監視システムに「ZABICOM」を追加することを検討してみてはいかがでしょうか。
キャリアならではの幅広いインテリジェンスを生かした状況の把握や分析、対策といったPDCAサイクルにより、継続的にネットワークの品質や安全性を向上できます。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。