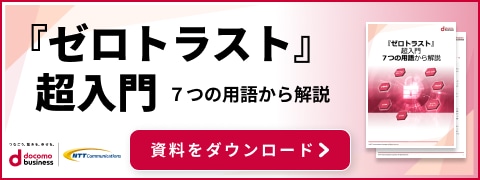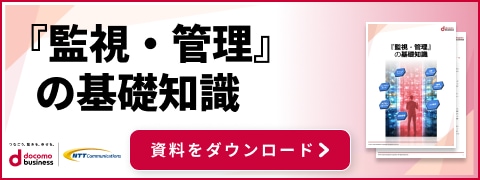2025年の崖とは?現状の課題や対策を徹底解説
「2025年の崖」では、基幹系システムなどを担う人材の退職・高齢化などの影響を受けて、2025年までにIT人材の不足は“約43万人”までに拡大し、大企業の旧来の基幹系システム(レガシーシステム)の導入年数が21年以上経過した割合は“約6割”になると指摘されます。ITを担う人材が減ることでシステムの刷新ができなくなり、レガシーシステムをそのまま使い続けることになります。結果として2025年には21年以上経過したレガシーシステムが約6割になると指摘されています。2025年の崖が現実とならないようDX推進などの対策が求められています。


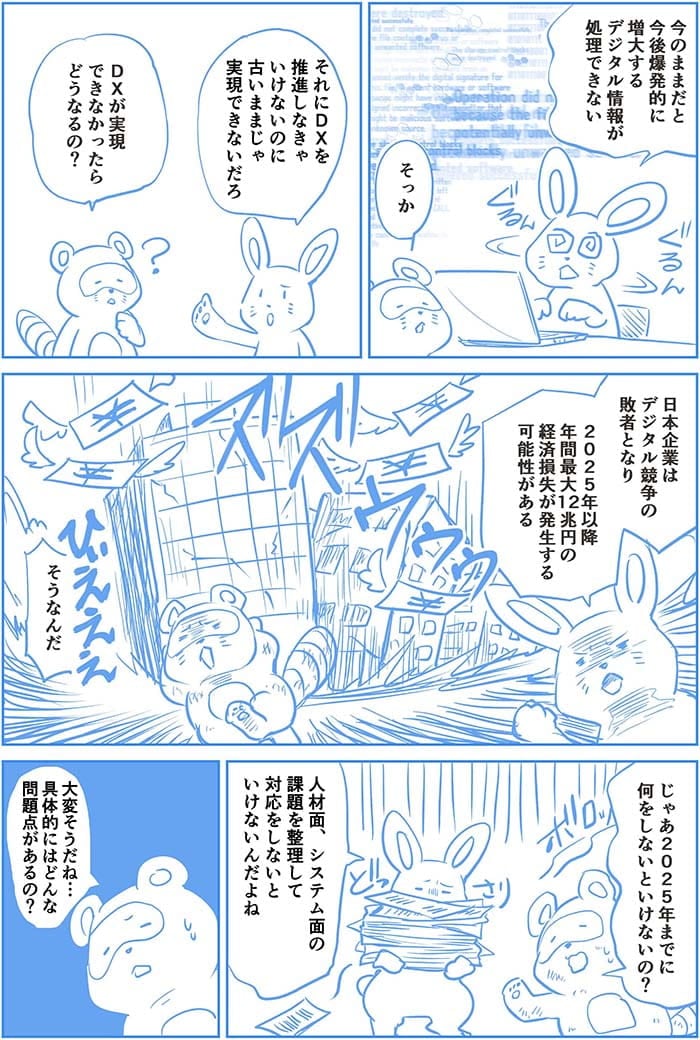


目次
金融業、自動車産業、製造業。IT業界のみならず、今あらゆる業界において、新たなデジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation:DX)の推進が加速している。特に、ここ数年は、政府が主導する働き方改革を実現するための手段としてのDX推進を模索する動きも活発化している。
DXの推進により、あらゆる企業、特にこれまでデジタル化とはあまり縁のなかった一部の製造業、農業や漁業、林業といった一次産業、対面中心のサービス業などでは、利益や業務効率が上がり、生産性向上が実現できるとされている。さらに、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルなど、DXにより創出された新しい価値は、企業間での競争における優位性を確立できるようになるともいわれている。
しかし、DXを成功させるには、社員が迅速に対応できる柔軟な組織体制やカルチャー、人材、情報共有、システムなどを見直し、新たなビジネスモデルに合わせて整備する必要がある。その際の大きな障壁といわれるのが、「人材面」と「システム面」への対応だ。
2025年の崖とは?
「2025年の崖」とは、日本企業のシステムの問題解決や経営改革がおこなわれなかった場合、2025年以降に最大12兆円/年の経済損失が生じるとする問題のことだ。経済産業省が2018年に発表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」」のなかで言及されている。この問題に対応できなかった場合、デジタル競争での敗北や既存システムを利用する際の維持管理費用の高額化を招くリスクが大きいとして、2025年の崖が現実とならないよう競争力の強化など対策が求められる。
その前提となる概念として「コネクテッド・インダストリーズ」がある。2017年3月にドイツ情報通信見本市で経済産業省によって発表された。コネクテッド・インダストリーズでは、人と機械・システム関連が協調するデジタル社会の実現や、デジタル技術に強い人材の育成などを推進している。
なぜ国際競争への遅れが懸念されているのか
先述の「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」」のなかで、日本企業が抱える課題に対応できなかった場合、国際競争への遅れが懸念されている。現在の日本企業が抱える課題として、以下の2点が挙げられる。
- 既存システムの複雑化かつブラックボックス化
- 新システム移行に伴う業務プロセスの見直し
日本企業では事業部ごとに異なるシステムが構築されていたり、過剰なカスタマイズがなされていたりするケースが多く、事業部間の情報共有・連携不足、システムが複雑化・ブラックボックス化してしまっている。これにより、市場の変化に柔軟に対応するのが難しくなり、デジタル競争の敗者となるリスクが高まる。
上記の課題を解消するには業務プロセス自体の見直しから取り組む必要があるが、現場サイドの抵抗も大きく、柔軟なシステム利用への対応をスムーズに進められないことも課題の1つだ。
世界的にデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)への対応が進められるなか、日本は大きく遅れをとっているのが現状。欧米諸国では、組織の柔軟な改革と早期からの取り組み、先進的な導入事例が生まれている。特にアメリカではすでに大きく変革が進んでいて、情報処理推進機構(IPA)の調査によるとアメリカ企業の72%がDXに取り組んでいることがわかった。一方、日本企業の割合は45%と、アメリカを大きく下回っている。※
DXレポートのその後
先述のDXレポートに続き、経済産業省は2020年に「DXレポート2(中間取りまとめ)」、2021年に「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」を発表しているものの、2025年の崖への懸念は取り払われていない。さまざまに関連した問題が絡み合い、DX推進などの全体対応が遅れている現状がある。
ただし、日本でもまったく取り組みが進められていないわけではない。一部業界では、デジタル企業が市場に参入したことで既存企業が追いやられる「デジタル・ディスラプション」も発生している。
2025年の崖に対する現状の問題点・課題
2025年の崖に対する対応が遅れている原因として、経営面・技術面・人材面にそれぞれ問題点・課題がある。ここでは、それぞれどのような問題や課題があるのか解説する。
経営面における問題点
DXレポートのなかで、「システムの維持管理費がIT予算の9割以上を占めるようになる」と言及されている。複雑化や老朽化したシステムは運用・保守に多くのコストがかかり、システムの刷新やDX対応にまでコストを回せていないことが、経営面における問題点として挙げられる。ブラックボックス化した既存システムを運用・保守できる人材の不足が懸念されていて、人材不足にともなう保守費用の増大も予測される。
また、経営層の情報共有、理解不足も課題の1つである。DX化が必要なことは理解しているものの、具体的な戦略を持てていない経営者も少なくない。経営層の指示が曖昧ではビジネスの革新が起こりにくく、企業内の業務効率の低下だけでなく国際的な競争力の低下も招いている。
技術面における問題点
DXレポートでは、老朽化・肥大化・複雑化・ブラックボックス化したシステムを「レガシーシステム」と呼んでいる。約8割の企業がこのレガシーシステムを抱えているといわれており、これが技術面における問題点の原因だ。2024年には固定電話網PSTNの終了、2025年にはSAP製ERPの保守サポートが終了する。業務にこれらを採用している企業では、早急な対応が求められる。
レガシーシステムに関連した問題は、長期に渡って部分的なメンテナンスを施してきたことで複雑化している。また、新たなシステムを導入したとしても、今度は過去の膨大なデータの移行が新たな課題となってしまう。
ドキュメントなどが整備されていないケースが多く、運用・保守の属人化が進行しているのも技術面における問題点の1つ。加えて、レガシーシステムが足かせとなり、新たなビジネスモデルや情報、技術に柔軟に対応できず、デジタル変革の時代に適応できない点も問題として挙げられる。
人材面での課題
2025年の崖では、基幹系システムなどを担う人材の退職・高齢化などの影響を受けて、2025年までにIT人材の不足は“約43万人”までに拡大するといわれている。レガシーシステムのプログラミング言語を知る人材や先端IT人材が供給不足となり、最新の情報技術に基づいたシステムの刷新ができなくなることが懸念される。
DXレポート2.1では、ユーザー企業のIT人材が育たない点も課題として指摘されている。システム開発をベンダーに丸投げして依存してしまっているユーザー企業では、社内にシステムに関するノウハウが蓄積されず、DX化が遅れる要因となる。
2025年の崖に向けたDX施策を推進すると何が変わる?
「レガシーシステムの刷新やDX推進は費用対効果が得られにくい」と考えている経営層もいるかもしれないが、2025年の崖に向けてDX施策を推進すると、企業にとって多くのメリットがある。
以下で、DX推進に取り組む3つのメリットを紹介する。
期的にはビジネスの成長・変革につながる
レガシーシステムの刷新やDX推進への投資には、基幹系システムの見直し、業務プロセスの標準化、人的リソースの再配分など莫大なコストと開発リソースが必要となる。しかし、この投資を実行しなければ、新しいビジネスモデルによる効果を最大限に引き出すことができず、今後到来するデジタル変革の時代に適応できなくなるかもしれない。つまり、レガシーシステムがDXによるビジネス変革の大きな足かせとなる可能性を秘めているのである。
今後到来するデジタル変革の時代に適応するためには、DX推進が必須といえる。DXの推進は短期的に見ると費用対効果が低く感じるかもしれないが、新たなビジネスチャンスを生み、全体的な長期メリットが大きい。
生産性の向上に繋がる
DX推進の大きなメリットとしては、生産性の向上も挙げられる。最新のテクノロジーを駆使したシステムやツールは作業効率を格段にアップさせ、ヒューマンエラーの抑制にもつながる。生産性が向上して労働時間が減れば、結果として人件費の削減にも効果が期待できる。
働き方改革が実現する
例えば、VPNやクラウドサービスなどを取り入れればオフィス以外の場所でも仕事ができるようになり、テレワークの導入が可能になる。デジタル環境が整っていないために、働き方改革やテレワーク導入ができていない企業もあるだろう。DX推進に積極的に取り組むことで、テレワークなど柔軟な働き方をスムーズに採用できるようになるのもメリットの1つだ。
2025年の崖を回避し、DXを推進する方法は?
経済産業省は企業のDX化を推進するために、「DX推進ガイドライン」を公開している。これをベースにして取り組みを進めるのがよいだろう。
以下では、企業がDXを推進する具体的な方法を紹介する。
システムの棚卸し・把握と必要な機能の洗い出し
はじめに、現行システムが抱える機能を棚卸しして、必要になる機能を洗い出す。次に、ERPやクラウドサービスなどをフル活用し、既存のレガシーシステムでおこなっていた業務を集約する。この新たなシステムに合わせて自社の業務プロセスを見直すというやり方が、「システム面」でのDX対応を本格展開する際のメインストリームになるだろう。
人材の確保・リソースのシフト
人材面では、刷新したシステムの運用業務をアウトソーシングし、人的リソースをDXなどの戦略的業務にシフトする。これまでIT担当や運用として現場作業を中心に動いていた人材をDX推進担当者として戦略的業務や戦略的なサポートへシフトさせることで、DXを短期間で浸透させるのである。これにより、新しいデジタル化に向けた取り組みを加速させることが可能となる。
IT部門の社員だけでなく、アジャイル開発の実践を通して事業部門の社員にITに慣れてもらうことも重要だ。経済産業省が定めるIT人材育成制度※を活用するのもよいだろう。
DXプロジェクトの進捗管理
2025年はもう目前に迫っており、DXプロジェクトは時間が限られているため、進捗管理が重要となる。ゴールとスケジュールを設定して現在地を常に把握し、遅延を早急に察知して状況に合わせた適切な対応が求められる。
経済産業省が配布する「DX推進指標」とそのガイダンス」は、各企業で簡易な自己診断がおこなえる資料で、プロジェクトの計画を策定する際などに活用できる。
企業がDXを実現するために意識すべきこと
最後に、企業がDXを実現するために意識すべき3つのポイントを紹介する。
経営層を含めて、DXが急務であるという社内の空気感を醸成する
なんとかなるだろうという逃げの姿勢では、「2025年の崖」を乗り越えることはできない。CEOなどの経営層が正面から「2025年の崖」に向き合い、投資の意思決定をしなければ、大きな痛手を受けることになる。
経営層だけでなく、社員を含めた全社的な協力が必須だ。大半の事業部門を巻き込んだ体制づくりが欠かせない。「DXによって何を実現するのか」といった目的やビジョンが、プロジェクト内や社内の関係者間で共有されている必要がある。
経営層が明確な目標・ビジョンを展開し、会社として「DXが急務である」といった空気感を社内に作り上げることで、現場サイドを巻き込んだスピード感のある対応が可能になる。
これまでの過程や仕事のやり方にこだわりすぎない
2025年の崖が懸念される背景として、20年以上前の「ERPブーム」がある。ERPをはじめとする基幹システムの導入が進み、その際「既存の業務体系に合わせてシステムを独自にカスタマイズする」といった場当たり的な対応が多くの企業でおこなわれた。これが、多くの企業でレガシーシステムが使い続けられている一因となっている。
上記の反省を踏まえて、DXの際は「プロセス・イノベーション」が求められる。プロセス・イノベーションは生産工程などを見直して生産性を高めること。「業務にシステムを合わせる」のではなく、「システムに業務を合わせる」姿勢で大幅な業務フローの改善にも取り組む必要がある。
守りのIT投資よりも攻めのIT投資を重視する
IT投資には、「攻め」と「守り」の2つの概念がある。攻めのIT投資とは、AIやビッグデータ活用による製品やサービス、ビジネスモデルなどを大きく変革させるための投資を指す。一方、守りのIT投資とは、ITツールの導入や既存の業務プロセスのIT化への投資のことだ。
守りのIT投資も重要だが、海外との競争を考えると攻めのIT投資をより重視すべきである。そもそもDXとは「デジタルによる変革」を意味し、攻めのIT投資なしにDXの実現は不可能ともいえるだろう。
まとめ
レガシーシステムを使い続けている現在の日本企業は、経営面・技術面・人材面にそれぞれ問題を抱えている。その問題を解消しなければ大きな経済損失を招くとしているのが、「2025年の崖」だ。問題解決のためには、各企業によるDX推進が急務となる。
ここまで説明してきたように、全社一丸となって真剣にDXと向き合わなければ、「2025年の崖」に関連した問題点を克服し、DXを推進していくことはできない。企業によっては、ITインフラや働き方改革にDXを取り入れ、ビジネスの変革を実現している企業もではじめている。IT人材の大量不足やITシステムの老朽化が迫りつつあるなか、デジタル時代に合わせた「人材面」と「システム面」の2大変革にいかに迅速に対応できるか。それが、「2025年」に向けた企業の生き残りの最重要課題となるだろう。