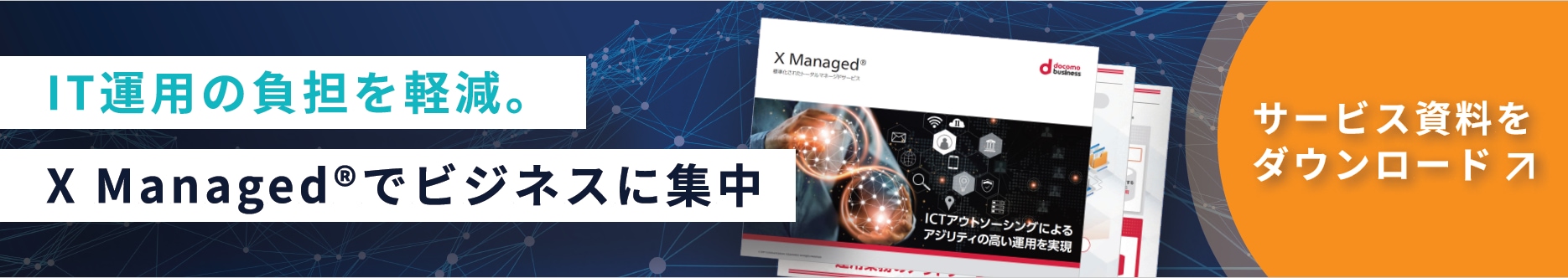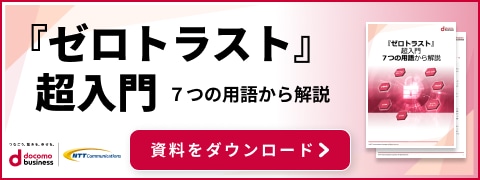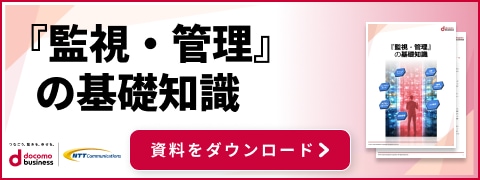SLM(サービスレベル管理)とは?
SLAとの違いやプロセスを解説
SLM(サービスレベル管理)は、ITサービスの品質を向上させるために品質基準を維持するプロセスのことです。SLMで単に品質の基準を決めるだけでなく、SLAやSLOなども合わせて検討しましょう。より高い水準のサービスを目指すことにより、サービス提供者と利用者の信頼関係を築き、効率的な運用のマネジメントが可能です。
当記事では、SLMの基礎知識とプロセス、具体的な指標の設定方法を詳しく解説します。

目次
1. SLM(サービスレベル管理)とは?
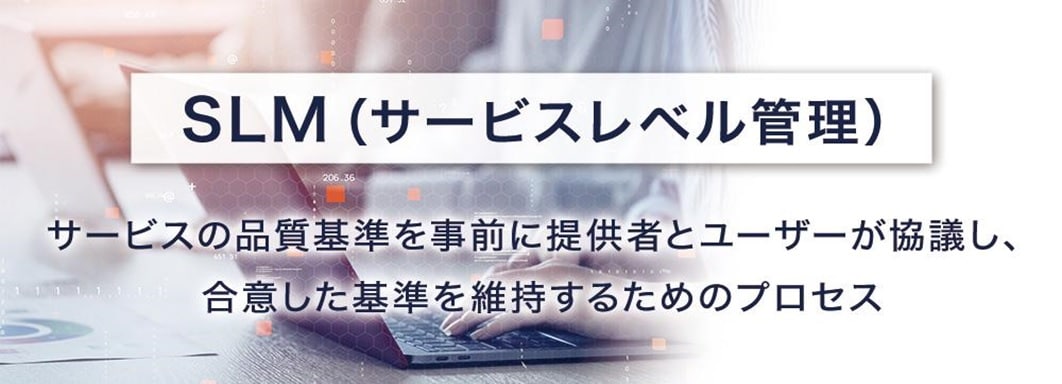
SLM(サービスレベル管理)とは、提供するサービスの品質基準を事前に提供者とユーザーが協議し、合意した基準を維持するためのプロセスを指します。SLMは、ユーザーの満足度向上や効率的なサービス提供・開発のために欠かせません。可用性や性能、データ管理などサービスの各要素の指標を設定し、モニタリングしながら継続的に改善を行います。
1-1. SLAとの違い
SLMに関連する用語としてよく聞くのが、SLA(Service Level Agreement)です。SLAは、サービスの品質基準を具体的に取り決めることです。これには、応答時間や稼働率などの具体的な基準が記載され、会社間の法的拘束力を持ちます。
一方、SLMはSLAで定められた基準を達成するための管理プロセスです。SLAがゴールであれば、SLMはそのゴールに到達するための手段と言えます。
1-2. SLOとの違い
SLO(Service Level Objective)は、サービス品質の達成目標を数値化したものです。たとえば、システムの月間稼働率99.9%や応答時間2秒以内などが該当します。
SLOは、SLAのような法的拘束力を持ちません。SLAはユーザーへの最低保証基準であり、SLOはサービス提供者が内部的に設定する目標として用い、より高いレベルで設定するのが一般的です。
1-3. SLIとの違い
SLI(Service Level Indicator)は、サービスレベルを測定するための指標です。たとえば、システムの稼働率や応答時間、エラー率などがSLIに該当します。SLIは、サービスの状況を定量的に把握するための基盤です。
SLMでは、SLIにもとづいてサービスを監視・分析し、SLAやSLOの達成度に応じて改善策を講じ、サービス品質の継続的な向上を目指します。
1-4. 可用性管理との違い
可用性管理は、ITシステムが継続的に稼働し、ユーザーが必要なときにアクセスできる状態を維持するためのプロセスです。たとえば、システムトラブル時の迅速な復旧やダウンタイムの最小化を目指す取り組みが挙げられます。
現代のビジネスにおいて、ほんの短時間であってもITシステムが停止すれば、企業に甚大な損失を生むリスクがあります。サービスレベルを維持する上で、可用性管理は不可欠です。SLMは可用性管理を包括しつつ、可用性以外の要素も含む包括的な管理プロセスとなります。
1-5. キャパシティ管理との違い
キャパシティ管理は、サービスを提供するために必要なリソースを予測し、適切に準備・調整するプロセスです。たとえば、CPUやメモリーの使用状況を監視し、将来的なニーズに備えることがキャパシティ管理の一環です。
一方、可用性管理はシステムの稼働状態を維持することが目的であり、リソースとコストの最適化を目的とするキャパシティ管理とは異なります。SLMは、これらの管理手法を統合・連携してサービス全体の品質を高めます。
2. サービスレベル管理のプロセス
サービスレベルを適切に管理するためには、段階的にプロセスを進めることが大切です。サービスレベルを決める際の基本的なステップは以下の通りです。
-
現状のサービスレベルを確認する
まず、現在提供されているサービスの品質やパフォーマンスを評価するために、システムの稼働状況やユーザーの満足度の分析を行います。現状の課題や改善すべき点を洗い出すことで、サービスレベルの基準を設定しやすくなります。 -
サービスレベルの目標値を設定する
現状の把握ができたら、次に目標とするサービスレベルの設定を行います。この目標値は、ユーザーのニーズや業務要件にもとづいて行いつつ、実現可能な範囲で設定しなければなりません。目標値には、稼働率や応答時間などの具体的な指標が含まれます。 -
試算や評価を行う
目標値を達成するために必要なリソースやコストを試算・評価するフェーズです。たとえば、現状の運用コストとの比較や予算制約、目標値が事業全体に与える影響を考慮した評価などをこのフェーズで行います。試算結果によっては、目標値の再調整が必要です。 -
契約を行う
サービス提供者とユーザーで合意したサービスレベル目標を基に、正式な契約(SLA)を締結します。契約には、サービス内容・目標値・責任範囲・ペナルティ条件などが明記されるのが一般的です。このプロセスにより、提供者とユーザーの認識を統一できます。 -
サービスレベルを満たしているか確認する
契約後は、設定したサービスレベル目標が達成されているか継続的に確認しなければなりません。パフォーマンスのモニタリングや定期的なレビューを実施し、必要に応じて改善を行いサービスの品質維持に努めます。
現状分析から契約・評価・改善まで一貫した流れを構築すると、ユーザーの満足度を高めるとともに、運用効率も向上させられるでしょう。
3. サービスレベルを決めるための指標
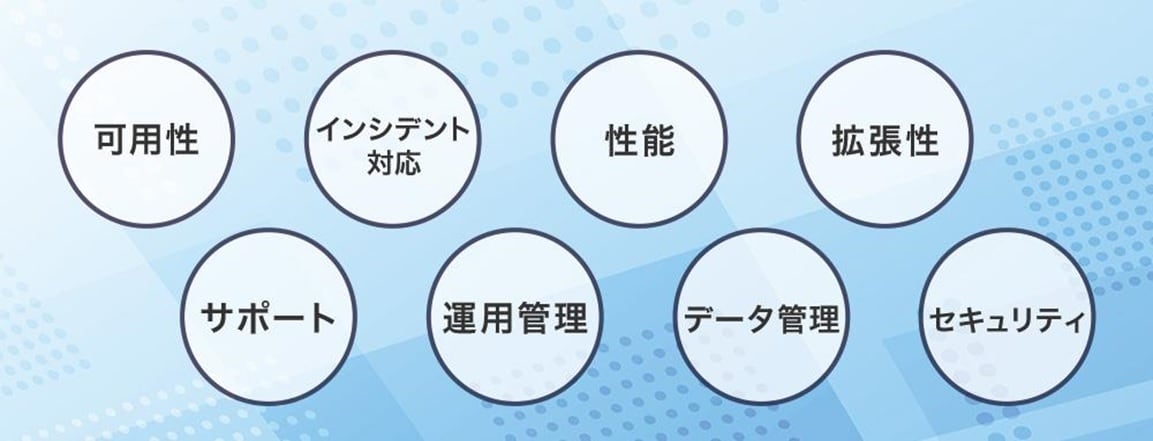
サービスレベルの合意を行う際には、どのような項目を取り入れるべきかが重要です。合意時に盛り込むべき基本的な項目は、経済産業省が作成したサービスレベル一覧のひな形を参考にするとよいでしょう。以下では、合意に含めるべき8つの項目を解説します。
3-1. 可用性
可用性は、サービスがどの程度利用可能であるかを表します。基本的な項目は、以下の通りです。
- サービス時間
- 計画停止予定通知
- サービス稼動率
サービス時間では、提供される時間帯や計画停止時間が明確に定められなければなりません。たとえば、基本業務は5:00~22:00、Web公開は24時間対応といった条件を設定します。
計画停止予定通知は、サービスを利用できなくなる期間を事前にユーザーへ連絡する規定で、7日前までに通知するルールが一般的です。これにより、ユーザーは対策を講じられ、業務への影響を最小限に抑えられます。サービス稼働率は稼働時間の割合を示しており、通常は99%以上が指標です。
3-2. インシデント対応
インシデント対応は、トラブルが発生した場合の迅速な復旧を目的とした取り組みです。基本的な項目は、以下の通りです。
- 故障通知プロセス
- 故障通知時間
- 故障監視間隔
- ディザスタリカバリ
- 重大故障時の代替手段
故障通知プロセスでは、トラブル発生時の連絡方法や経路が定められます。故障監視間隔では、30分ごとに故障インシデントを収集・集計するルールが一般的です。
ディザスタリカバリは、災害時のシステム復旧・サポート体制を指し、迅速な対応が求められます。また、早期復旧が困難な重大故障時に備え、代替手段を用意しておかなければなりません。
これらの取り組みにより、トラブル発生時でもサービスの信頼性を保ち、ユーザーへの影響を最小限に抑えることが可能です。
3-3. 性能
性能は、サービスがどの程度スムーズに機能するかを示します。具体的な応答時間や処理速度などが挙げられます。基本的な項目は、以下の通りです。
- オンライン応答時間
- バッチ処理時間
- サービス提供状況の報告方法
オンライン応答時間は、リクエストに対してシステムが応答するまでの時間であり、通常は5秒以内が目標値として設定されます。バッチ処理時間は一括処理の完了までの時間で、目標値は5分以内が目安です。
サービス提供状況の報告方法としては、四半期ごとにサービス提供状況を報告する形式が一般的です。性能指標を明確にすることで、ユーザーがサービスの品質を客観的に把握できます。
3-4. 拡張性
拡張性は、将来的にサービスをどの程度柔軟に調整できるかを示します。基本的な項目は、以下の通りです。
- カスタマイズ性
- 外部接続性
- 接続ユーザー数
- アップグレード方針
カスタマイズ性では、特定の機能の追加やクラウドストレージの拡大など、ユーザーが独自にサービスを変更できる範囲を定めます。外部接続性は、APIを通じて外部システムと連携する能力を指しており、接続制限や仕様が明記されるのが一般的です。
また、接続ユーザー数は、サービスを同時に利用可能なユーザー数のことで、プランごとに上限が異なるケースが少なくありません。アップグレード方針では、バージョンアップや変更管理、パッチ管理の基準を示します。
3-5. サポート
サポートは、ユーザーが安心してサービスを利用できるようにするためのサポート体制に関する指標です。基本的な項目は、以下の通りです。
- サービス提供時間帯(故障対応)
- サービス提供時間帯(一般お問い合わせ)
- ヘルプデスク
トラブル発生時、およびの一般的なお問い合わせの受付時間帯としては、平日の9:00~17:00までと定めるのが一般的です。夜間や休日の対応としてヘルプデスクが設置されるサービスもあります。
サポート手段には、電話・メール・チャットなどさまざまです。困った際に迅速な解決が図れる環境を整えられていれば、ユーザーは安心してサービスを利用できます。
3-6. 運用管理
運用管理は、サービスが継続的に安定して稼働するための取り組みを指します。基本的な項目は、以下の通りです。
- システム監視基準
- 死活監視
- サービス故障監視
システム監視基準では、システムの死活監視やサービス故障を早期発見できる環境の整備が求められます。たとえば、監視でサービス稼働状況やトラブル状況を確認し、通知する時間・頻度の設定が挙げられるでしょう。死活監視や故障監視には、WebサーバーやOS、アプリケーションログの監視なども含まれます。
3-7. データ管理
データ管理では、データの保護や取り扱いに関する内容を定めます。基本的な項目は、以下の通りです。
- データの保証の要件
- バックアップデータ保存期間
- データ消去の要件
データの保証の要件では、データベースや設定ファイルの保管場所やバックアップの頻度などを取り決めます。データ消去の要件では、サービスを解約した後のデータの取り扱いを定めます。たとえば、データ消去や保管媒体を破棄するタイミング、データ移行の支援などです。適切なデータ管理は、サービスの信頼性を高める要因となります。
3-8. セキュリティ
セキュリティは、外部攻撃や内部不正に対する防御策を具体的に定めます。基本的な項目は、以下の通りです。
- 公的認証取得の要件
- 情報取扱者の制限
- 情報取扱環境
- ログの取得
- セキュリティパッチ対応
- ウイルスチェック対応
- 通信の暗号化レベル
セキュリティに関しては、サービスが取得している公的認証を記載します。データにアクセスできる人員や、取り扱い環境も厳格に管理する必要があります。
ユーザーの求めに応じて提供できるログ情報の種類も明記する必要があります。ログの取得と分析は、システムトラブルや不正アクセスを防ぐために欠かせません。取得したログを定期的に分析・診断することにより、潜在的な問題を早期に特定し、対策を講じられるためです。
また、セキュリティパッチ対応やウイルスチェック対応、システム間のデータ送受信を保護する暗号化レベルも、サービスに対する信頼性を示します。
4. SLMを適切に行うメリット
サービスレベルを決め、SLMを適切に行うことで、サービスを提供する側と利用する側の双方に多くのメリットが生まれます。双方の関係がより円滑になり、サービスの満足度と信頼性を向上できるでしょう。以下では、それぞれの視点からメリットを解説します。
4-1. サービス提供側のメリット
SLMの適切な実施により、サービス提供者側が得られる主なメリットは、以下の3つです。
- 認識の齟齬を防げる
SLMにより、サービスの内容や品質基準が明確になるため、提供者とユーザーの間で期待値のズレが発生しにくくなります。たとえば、対応時間やサポート範囲を事前に取り決めておけば、曖昧な要求や過剰な期待を受けにくくなり、効率的な運用ができます。 - トラブル時に対処しやすい
SLMでは、トラブルが発生した際の対応手順や責任範囲が明確に定義されます。そのため、問題が発生しても迅速かつ適切に対応できる体制を整えることが可能です。 - ほかのサービスとの差別化になる
自社のサービス内容や品質基準を他社と差別化できるのも、SLMを適切に行うメリットです。たとえば、SLAで定めた高い可用性や迅速なサポート体制が正しく実行されていれば、競合他社より優れたサービスであるとアピールできます。
SLMは、提供するサービスの透明性を高め、効率的な運用とユーザーの満足度の向上を実現するために欠かせません。
4-2. サービス利用側のメリット
SLMを導入すると、サービスを利用する側にも多くの利点があります。
- サービスのクオリティが明確で分かりやすい
SLMがきちんと行われていると、提供されるサービスの品質や範囲が具体的に記載されます。受けられるサービス内容やメリット・デメリットを事前に把握できるため、ユーザーは自分の分野やニーズにもっとも適したサービスを選択しやすくなります。また、契約された基準が守られているかを確認しやすく、かつ期待と実際のズレが起こりにくくなるのもメリットです。 - トラブルの際補填がある
SLMには、トラブル時の補償内容や対応策も定められています。たとえば、トラブル発生時の復旧時間や補償金額が契約にもとづいて保証されるため、万が一の際にも安心です。提供者側と揉める要因が減れば、トラブル時のストレスを軽減できます。
明確な契約内容にもとづく補償やサポート体制は、信頼性の向上にも寄与するでしょう。
5. SLMを運用する際のポイント

SLMを運用する際には、実現可能なレベルの設定や継続的な改善プロセスが重要です。適切な管理を行うことで、効率的かつ信頼性の高いサービス提供が可能になります。以下のポイントを押さえながら運用を進めていきましょう。
5-1. 実現可能なレベルを定める
サービスレベルを設定する際は、現在確実に提供可能な範囲内に定めることが大切です。そもそも、サービスレベルは合意形成の過程で提供者とユーザーの認識をすり合わせるために決められる指標です。高すぎる目標を掲げたり、開発中のツールを前提にしたりするのは避けましょう。トラブルや不満を引き起こしやすいだけでなく、サービスの維持すら難しくなる可能性があります。
実現可能なレベルの設定は、長期的な信頼関係を築くための基盤になります。ユーザーのニーズと提供者のリソースを慎重に調整し、バランスの取れたSLAの設定がSLMの運用に重要です。
5-2. PDCAサイクルを回す
サービスレベルの管理には、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルの活用が欠かせません。
たとえば、サービス稼働率やインシデント対応時間などの数値を定期的に分析し、目標値に達していない場合はその原因を特定します。その後、課題解決に向けた施策を講じ、再度運用を最適化します。PDCAを回すことで、サービス品質の維持と、顧客満足度の向上や競争力の強化が期待できるでしょう。
SLMの運用には、信頼できるパートナーや専門的なベンダーの支援が有用です。たとえば、ドコモビジネスの「X Managed」では、SLAの運用支援やセミオーダー型のサービス提供を行っています。SLMの運用効率を高めるためには、専門サービスの活用を検討するのがおすすめです。
まとめ
SLMは、ユーザー満足度を高め、サービス提供の信頼性を確保するための不可欠なプロセスです。SLAで定めた基準を基に、モニタリングや改善を通じて品質を維持することで、サービス提供者と利用者の双方にとって多くのメリットがあります。
適切なSLM運用は、契約時の認識の齟齬を防ぐほか、トラブル発生時にも迅速に対処できるようになります。信頼性と効率性を両立するために、SLMの運用を検討しましょう。