交通費として適正なガソリン代は?通勤費との違いから考え方まで解説

公開日:2022/10/19
交通費は企業活動に必要な経費の1つです。しかし、「ガソリン代の面からすると、通勤費と何が違うのか?」と疑問を抱くケースもあるでしょう。実際、経費精算上では、交通費と通勤費は明確に分ける必要があります。
交通費と通勤費の違い、1kmあたりのガソリン代の出し方の事例などについて解説していきます。
目次
交通費と通勤費は異なるもの
よく混同されますが、交通費と通勤費は税務上の扱いが次のように全く異なるものです。
| 通勤費 | 通勤交通費とも呼ばれる。扱いは所得税の対象となる人件費。 一定の金額までは非課税だが、それ以上となると課税対象となる |
|---|---|
| 交通費 | 業務上必要になる通勤以外の移動費のこと。 タクシーや飛行機などといった移動手段を対象として、全てが非課税となる。 |
営業職の自家用車による移動などは、交通費に分類される
通勤費は所得税の対象であり、企業が従業員に与える通勤のための費用だといえます。一人ひとり金額が異なり、非課税上限額がバス・電車では15万円までと決まっています。しかし、車では明確に距離と非課税限度額が定められている点は知っておきましょう。
参照:国税庁|No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
対して、交通費は全額経費として扱われ、業務上必要な移動を指す言葉です。上限額が決まっておらず、どのような移動手段に対してどの程度までの上限があるのかは会社ごとにことなります。法律上の決まりはありません。
交通費の違いを知ったうえで使い分けていきましょう。
交通費・通勤費のガソリン代のルール
ここからは交通費・通勤費のガソリン代のルールの内容についてみていきましょう。どちらであってもルールに基づいて運用されるため、概要を知ることが大切です。
細かいルールは企業ごとに異なる
交通費に関しては、タクシー・電車・飛行機などそれぞれの移動手段に対して、ルールを作る必要があります。また、細かいルールは企業ごとに決まっており、必ず領収書を貰うなどといった対策も必要です。
通勤費に関しては、月・日などの規定・全額支給・一律支給の3パターンに分かれることがほとんどです。全額支給に関しては、ルートに合わせてガソリン代を支給するため、従業員の負担が軽減します。
社用車と自家用車の扱いは異なる
業務で自家用車を使用する場合は、交通費として1km辺りのガソリン代を計算し支給するケースが多いのが実状です。プライベート用の移動と分ける必要があり、スタートと使用後のキロ数をメモするなどといったチェック業務も発生します。
また、社用車である場合はガソリン代は経費として扱うため、ガソリン代に応じた代金の支給などを行うといった対応が必要です。場合によっては、法人カードを貸し出して支払いを行うこともあります。
限度額は確認の必要がある
通勤費の法律上の非課税限度額はバス・電車であれば15万円と決まっています。そのうえで、 企業によっては法律とは別に上限が規定が決まっているケースもある点は知っておきましょう。
例えば、企業までの距離が10キロメートル以内であれば一律で15,000円を支給するといった就業規則があれば、従うことになります。仮に遠方からルールがない場合は、改めて作成する必要もあります。
交通費に関しては経費となるため、上限はないものの、プリベイトカードやクレジットカードであれば5万円などの上限を設けることも可能です。ただし、従業員の行動範囲や業務内容を明確に把握する必要があります。
1kmあたりのガソリン代と交通費計算の例
通勤及び業務内で自家用車を使用した場合、1kmあたりのガソリン代と交通費計算の例は次のように考えられます。
・例1
1キロ辺りのガソリン代20円。
業務で30キロ走行→30×20で600円がガソリン代となる
・例2
1キロ辺りのガソリン代25円。
業務で60キロ走行。25*60で1500円がガソリン代となる
・例3
1キロ辺りのガソリン代22円
業務で55キロ走行。22×55キロで1,210円がガソリン代となる
ガソリン代が常に変動するため、平均単価などを参照しつつ決めていきましょう。一度決めたとしても定期的に見直しすることが大切です。
ガソリン代のより詳しい計算方法についてはこちらの記事をどうぞ。
通勤費の相場とは
通勤費の相場は企業や地域によって異なります。ただし、あくまでも相場は目安に過ぎないため、自社の状況に合わせることが大切です。
厚生労働省の「就労条件総合調査結果」から読み解くと、通勤費は企業規模が100人未満でも10,000円を超えており、100人以上大企業であっても14,000円まで届いていませんでした。
企業規模が大きいほど金額が高いように見えますが、世の中の99%の企業が中小企業である点を考慮すると通勤費を従業員に支払っている企業は多いといえるでしょう。また、あくまでも平均の金額であるため、企業によってはもっと高額となっているケースもあります。
自社の従業員の状況を把握し、適切な額を支給することが大切だといえます。
交通費をスムーズに経費精算するための方法
ここからは、交通費をスムーズに経費計算するための方法をみていきましょう。これまでの一般的な交通費精算の流れは、紙によるやり取り・無駄なコミュニケーションなども含めて、あまりスムーズといえないものでした。しかし、近年ではスムーズな経費精算が可能になっています。
経費精算ツールの導入
交通費精算を行う機会が多い場合、経費精算ツールの導入を推奨します。データによってなり取りするため、ペーパーレス化・電子帳簿保存法にも対応可能です。
また、NTTコミュニケーションズでは、経費精算ツールであるSmartGo™ Stapleを提供しています。とくに通勤費と交通費を分けられるツールを探している方は、SmartGo™ Stapleの利用を検討してみましょう。
経費精算ツールで業務効率化を目指す場合はこちらの記事から。
支払いのキャッシュレス化
支払いに関しては現金ではなく、法人カードやプリペイドカードによってキャッシュレス化するとスムーズな処理が可能となります。例えば、小口現金で必要な金額を経費として渡すよりもカードによって管理した方がスピーディーなやり取りが可能です。
加えて、経費精算ツールと連動することで自動入力・履歴の参照なども可能となるため、これまで以上に円滑な企業活動が行えるでしょう。
交通費精算の注意点
ここからは、交通費精算の注意点をみていきましょう。とくに業務効率や経理担当の業務負担が気になる場合は、ツールで対応したい業務を現場と話しながら決める必要もあります。
交通費精算の流れを理解しておく必要がある
一般的な交通費精算の流れは次のようになります。
1.交通費精算書を作成し提出
2.上司から承認を貰い、経理担当者が内容を確認(この段階で差し戻しが発生)
3.日付と印鑑を添付し、精算金を対象者へ
従業員の数がある程度多く、1カ月単位で交通費精算を実施する場合、従業員に対する負荷が高くなることも少なくありません。
ツール導入では対応したい業務の優先順位を決める
ヒューマンエラーの減少を目指す場合、手書き・手入力の機会を減らす必要があります。その場合は、領収書やレシートを添付できる機能などが役立つでしょう。 また、交通系ICカードと連携できる場合、通勤・交通費に関して不正利用や差し戻しの心配がなくなるだけでなく、従業員の負担軽減も可能です。
まとめ
通勤費・交通費の1kmあたりのガソリン代は、企業によってルールが異なるものの、所得と経費に分かれているため、全く別の要素として考える必要があります。加えて、通勤費に関しては、法律的な決まりがなく、バスや電車以外ではある程度上限が決まっている点は知っておきましょう。 NTTコミュニケーションズでは、経費精算ツールであるビジネスd経費精算を提供しています。交通系ICカードと連携できるため、キャッシュレス化が可能です。また、通勤費と交通費を分けられるツールを探している方は、ビジネスd経費精算の利用を検討してみましょう。
経費精算でお悩みの方へ
こんなお悩みございませんか?
 経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる
経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる 立替の事務手続きが多い
立替の事務手続きが多い 出社せずに経費精算を完結させたい
出社せずに経費精算を完結させたい 定期代支給を廃止し、都度精算にしたい
定期代支給を廃止し、都度精算にしたい
そのお悩み、ビジネスd経費精算ですべて解決できます!
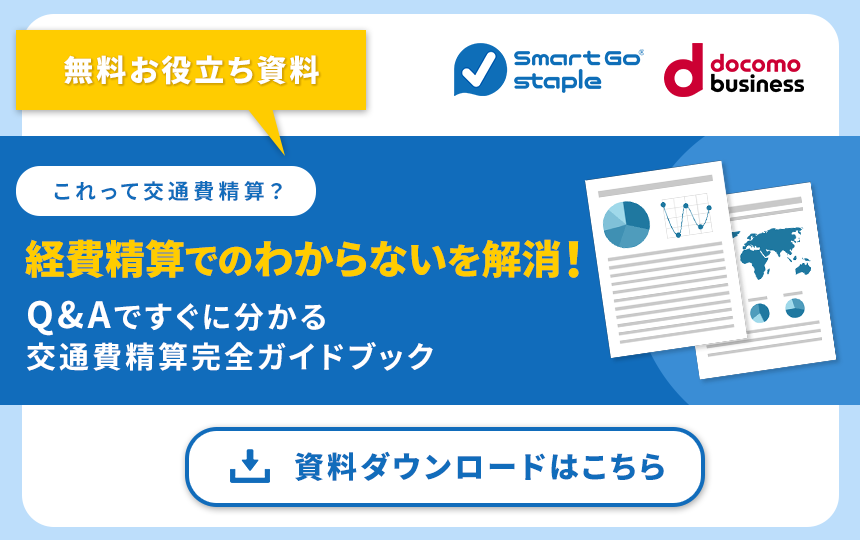




 JP
JP















 あわせて読みたいおすすめの記事
あわせて読みたいおすすめの記事





