経費精算時におけるガソリン代の計算方法を解説

公開日:2022/07/29
経費精算でガソリン代を計算する場合、考え方やルールを知っておくことが重要です。本記事では、経費精算でガソリン代を計算する際の考え方から使用できる勘定科目、注意点・効率化を図る方法までを紹介します。
経費精算でガソリン代を計算する際の考え方
経費精算でガソリン代を計算する際は、正しい考え方を持っておくことが大切です。以下では、経費精算でガソリン代を計算する際に知っておくべきことを3つ紹介します。
ガソリン代は支給しなくてもよい
マイカー通勤をする社員に対して、ガソリン代を通勤手当として支給する会社は多くあります。しかし、ガソリン代などをはじめとした通勤手当の支給は、法律上、義務化されていません。
したがって、マイカー通勤をする社員に対して「ガソリン代を支給する・しない」は会社側の裁量によって決められると言えます。他には、ガソリン代の計算方法・勘定科目なども会社のルールに基づいて定められています。
経費精算に携わる方は、ガソリン代の支給について会社側が自由に決められることを知っておきましょう。
自家用車は走行距離に応じて精算する
自家用車のガソリン代を経費精算する場合は、走行距離に応じた金額を算出します。自家用車の場合、通勤や出張以外にもプライベートで車を使用する機会があるため、1か月にかかったすべてのガソリン代を経費として精算できません。
自家用車のガソリン代は、下記の数式で算出することが一般的です。
自家用車のガソリン代=走行距離÷燃費×1Lあたりのガソリン代
自家用車のガソリン代を求める際は、走行距離・燃費・1Lあたりのガソリン代を把握することが欠かせません。それぞれの確認方法は下記のとおりです。
走行距離
走行距離は、出発地点の車のメーターの数値から到着地点の車のメーターの数値の差を出すと求められます。メーターをリセットできる車種の場合は、出発地点でメーターの数値を「0」にしておけば、走行距離を簡単に求められます。一定のルールに則って走行距離を出したいときは、Googleマップなどを使うことがおすすめです。
燃費
燃費は、各車種のカタログやインターネット上に出てくる燃費情報をもとに決めます。ただし、カタログに掲載されている燃費は実測値ではないため、実際の燃費と異なる場合がほとんどです。
正確な燃費は、走行距離に対してガソリンをいくら消費したのかを計算することで求められます。正確な燃費を求めるときは次の手順で調べます。
- 走行距離を把握する
- ガソリンを満タンにした状態で出発する
- 到着後にガソリンを再び満タンにする(レシートなどで給油量を把握する)
- 「走行距離÷給油量」の数式で燃費を算出する
最新車種の場合は、モニターやメーターなどに表示される平均燃費を参考にしてもよいでしょう。
1Lあたりのガソリン代
1Lあたりのガソリン代は情勢によって変動するため、期間を設けて平均価格を求めましょう。経費精算するガソリン代の平均価格は、会社周辺にあるガソリンスタンドの値段を参考にしたり、経済産業省・資源エネルギー庁のサイトをもとに決めたりすることがおすすめです。
従業員数が多い会社などでは、1kmあたりのガソリン代を固定して通勤手当を支給するケースもあります。1kmあたりのガソリン代の相場は10〜20円程度に定める会社がほとんどです。
1kmあたりのガソリン代を固定した通勤手当は、「自宅から会社までの往復距離×1kmあたりのガソリン代×出勤日数」の式で算出します。車種によって通勤手当に差が出ないため、1kmあたりのガソリン代を固定する方法であれば、公平にガソリン代を支給できます。
社用車は全額精算する
社用車の場合はすべて業務に関わる移動とみなされるため、ガソリン代を全額経費として精算できます。他の経費と同様にガソリン代を経費精算する際は、レシートもしくは領収書が必要です。
非課税限度額を通勤手当の上限にする
ガソリン代を通勤手当として支給する場合、上限額を設けている会社がほとんどです。キリの良い数字を上限額として定める会社がある一方で、非課税限度額を通勤手当の上限額に設定する会社も多くみられます。
下記は、自家用車を使用する場合における通勤手当の非課税限度額をまとめた表です。

(出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」)
経費精算におけるガソリン代の4つの勘定科目と適切な使用シーン
ガソリン代を経費精算する際は、4つの勘定科目のなかから適したものを使用します。勘定科目には適切な使用シーンがあるため知っておくことが大切です。
1.車両費に計上する
車両費は、会社が所有する車の維持・管理にかかる費用を計上する際に用いる勘定科目です。ガソリン代は車を使用するために必要な費用となるため、車両費に含めることが可能です。車両費は、ガソリン代だけでなく次に挙げる費用にも使用できます。
- 車検費用
- エンジンオイル交換代
- タイヤ交換代
- 洗車代
- 自動車税および自動車重量税
- 自賠責保険料および任意保険料 など
車両費は、会社が所有する車の維持・管理にかかった費用をわかりやすくしたいときに適した勘定科目です。所有する車の台数が少ない会社は、ガソリン代を車両費として計上すると処理しやすくなります。
2.旅費交通費に計上する
旅行交通費は、本社から支店へ移動するときの交通費や出張などにかかる移動費・宿泊費を計上するときに使う勘定科目です。業務に関する移動で車を使った際にかかるガソリン代も、旅行交通費で計上できます。他にも、旅行交通費は下記で挙げる費用に使えます。
- 電車代やバス代
- 飛行機代や新幹線代
- タクシー代
- 宿泊費
- 出張手当 など
出張や移動が多い会社は、ガソリン代を旅行交通費に計上する場合がほとんどです。出張や移動に関する経費を一括で管理したいときは、ガソリン代を旅行交通費として計上することが適しています。
3.消耗品費に計上する
消耗品費は、使うと消耗する備品を購入した際に使う勘定科目です。車はガソリンを消費して動かすため、ガソリン代も消耗品費として計上できます。消耗品費は、ガソリン代のほかに次で挙げるものにも使用できます。
- ボールペン・コピー用紙などの事務用品
- ドライバー・ボルト・ペンチなどの作業用品
事務用品や作業用品であっても、使用可能年数が1年以上かつ金額が10万円を超えるものは、消耗品費として購入時に全額経費計上できないことを知っておいてください。
ガソリン代は車両費や旅費交通費の側面が強く、消耗品費として計上することはあまり適していません。ただし、ガソリン代を経費に落とす機会が年に数回しかない会社であれば、消耗品費として計上しても経理作業が煩雑になる可能性は低いでしょう。
4.燃料費に計上する
燃料費はガソリンをはじめ重油や灯油など、燃料にかかる費用を計上するときに使用する勘定科目です。経費のなかで、ガソリン代の占める割合が高い会社の勘定科目としておすすめです。
燃料費として計上すれば、会社が所有する車の維持・管理費や出張時の交通費と切り分けてガソリン代を管理しやすくなります。
経費精算でガソリン代を計算する際の3つの注意点
ガソリン代を経費精算する際は、いくつかの注意点があります。以下で紹介するポイントを押さえておきましょう。
勘定項目を統一する
ガソリン代を経費計上する場合、車両費・旅費交通費・消耗品費・燃料費のいずれかの勘定科目に統一して仕分けする必要があります。会計期間中にガソリン代の勘定科目を変更すると、利益操作をしていると税務署から判断される恐れがあるため控えてください。
ガソリン代の勘定科目を変えたいときは、会計期間が終了したタイミングで変更しましょう。
軽油車両は課される税金が異なる
車はガソリン車両と軽油車両に分類できます。ガソリン車両は「レギュラー」「ハイオク」を、軽油車両は「軽油」を使う車のことです。
ガソリン車両と軽油車両では課される税金が異なります。各車両で課される税金の種類は下記のとおりです。
- ガソリン車両:ガソリン税と消費税
- 軽油車両:軽油取引税と石油税
軽油車両の場合、ガソリン代に消費税がかかりません。軽油車両の経費精算をする際は、軽油取引税に消費税を含めず処理することが大切です。
未使用のガソリン代は貯蔵品に計上しなければならない
未使用のガソリンは、原則、貯蔵品として計上しなければなりません。経理上では、給油タンクに残っているガソリンを貯蔵品として取り扱います。決算時には、「経費として計上したガソリン代−貯蔵品として取り扱ったガソリン代」の数式で正確な支出額を求めます。
ただし、給油タンクに残っているガソリンを把握することは難しく、上記の数式で正確な支出額を求めることはできません。以上の背景から、国税庁の法令解釈通知では消耗品費について次のように述べています。
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)
引用:国税庁「第2款 販売費及び一般管理費等」
上記の条文では、「経費としてガソリン代が占める割合が低い場合は、貯蔵品として計上する必要がない」と説明しています。つまり、車に給油したガソリンはそのまま経費精算して問題ありません。
経費精算でガソリン代の計算を効率的に進める方法
ガソリン代の経費精算と言っても、回数が多ければ作業負担が大きくなります。ここでは、経費精算でガソリン代の計算を効率的に進める方法を2つ紹介します。
精算ルールを統一する
ガソリン代の計算を効率よく進めるためには、精算ルールを統一することが重要です。精算ルールが決まっていない場合、ガソリン支給額の上限やガソリン代の勘定科目が担当者によって変わる恐れがあります。
複数の担当者で経費精算する会社では、就業規則で精算ルールを明確に記しておきましょう。例えば、「走行距離1kmあたりに支給するガソリン代の上限額は◯円」や「ガソリン代の勘定科目は〇〇」と決めておけば、ガソリン代の計算をスムーズに進められます。
経費精算システムを導入する
経費精算システムを導入することも、ガソリン代の計算を効率よく進める方法として有効です。経費精算システムでは、1kmあたりのガソリン代を登録できるため、走行距離を打ち込むだけでガソリン代を算出できます。
経費精算システムを使えば、簡単にガソリン代を計算できたり、経理担当者がガソリン代をチェックする手間を省けたりするメリットを得られます。ガソリン代の不正申請も防止できることから、経費精算システムは多くの会社で導入されている状況です。
まとめ
ガソリン代は、車両費・旅費交通費・消耗品費・燃料費のいずれかの勘定科目を用いて経費精算します。経費精算にはいくつかのルールがあるため、経理担当者はガソリン代の仕分け・計算方法などを理解しておくことが大切です。
経費精算でガソリン代の計算を効率よく進めたい方は、精算ルールを明確にする以外に、経費精算システムを導入することがおすすめです。経費精算システムを導入すれば、経理担当者以外の社員でも簡単にガソリン代を算出することが可能となります。
NTTコミュニケーションズでは経費精算ツール”ビジネスd経費精算”を提供しています。
ビジネスd経費精算ではプリペイドカードとの連携により、経費申請の手間が省けて、従業員の立替の負担や経理担当者の振込の手間がなくなります。
日々の精算業務に頭を悩ませている場合は、是非ビジネスd経費精算の導入を検討してみましょう。
経費精算でお悩みの方へ
こんなお悩みございませんか?
 経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる
経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる 立替の事務手続きが多い
立替の事務手続きが多い 出社せずに経費精算を完結させたい
出社せずに経費精算を完結させたい 定期代支給を廃止し、都度精算にしたい
定期代支給を廃止し、都度精算にしたい
そのお悩み、ビジネスd経費精算ですべて解決できます!
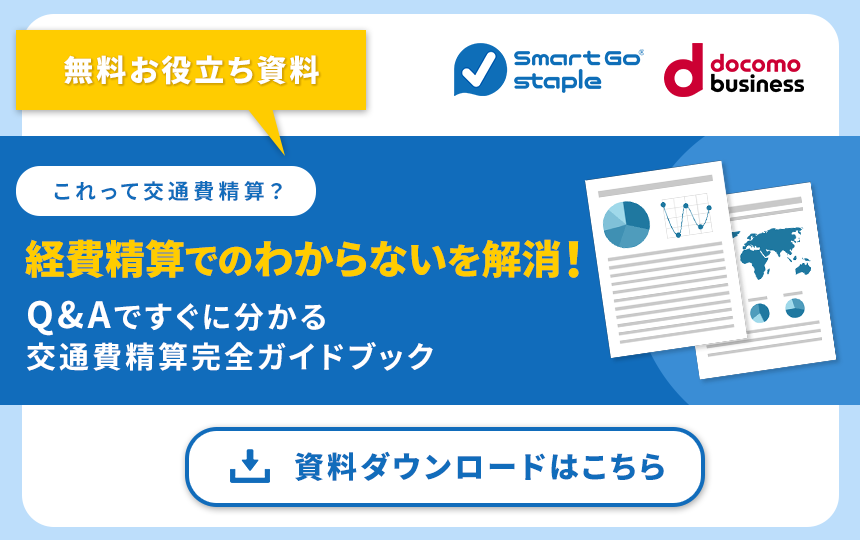




 JP
JP


















 あわせて読みたいDXに関する記事
あわせて読みたいDXに関する記事





