立替精算とは?仮払金との違いや精算方法、注意点を解説

公開日:2022/10/19
本来、会社が支払うべき経費を、社員が一時的に立て替えて支払い、後に会社が精算する一連の業務を「立替精算」といいます。
仮払金との違いや具体的な精算方法について詳しく知りたい人もいるでしょう。
本記事では、立替精算の精算方法や仮払金との違い、立替精算を行う際の注意点について解説します。立替精算について詳しく知りたい方は参考にしてください。
目次
立替精算とは
本来、会社が負担すべき経費を従業員があらかじめ支払うことを「立替経費」といいます。その後、従業員は立替分の経費を会社から受け取るために精算手続きを行わなければなりません。
この一連の流れが「立替精算」です。
仮払金との違い
仮払金の場合は、先に会社から担当社員に概算額を支払います。実際に社員が経費を支払った後、仮払金と過不足額を精算する方法です。
立替精算の場合は全額社員が事前に支払うため、社員は精算されるまで一定額をいったん自分の財布から負担しておかなければなりません。一方、仮払金の場合は事前に会社から概算額を受け取れるため、一定額の自己負担が不要になる点が大きく異なります。
経費精算の課題とDXによる解決方法についての記事はこちらです。
立替経費の精算方法
立替経費の精算方法は、どこの会社も大きくは違いません。ここからは、具体的に立替経費の精算方法を見ていきましょう。
ただし、会社により独自のルール等が設定してある場合も少なくありません。実際に精算を行う際は社内ルールに従いましょう。
従業員が経費を立替
従業員は業務に必要なものを購入するために、自分のお金で支払います。出張時や旅費・交通費の立替、消耗品の購入、会議用の飲料購入など具体的な内容は多岐にわたります。
領収書を受け取る
領収書が発行されるものであれば、宛名欄に会社名を記載した領収書の受け取りが欠かせません。会社によっては、領収書よりも明細のわかるレシートを推奨している場合もあるため、事前に社内ルールを確認しておきましょう。
担当者は、自動販売機でジュースを購入する場合など、領収書やレシートのない支払いがある際は事前に上長や経理部、社内ルールなどでどのようにすればよいか確認が必要です。
また、経理部では事前に経費立替に関する細かいルールを定めておきましょう。
領収書に関する記事はこちらです。
領収書を添付し、稟議書を作成
担当者は領収書を添付し、稟議書を作成します。稟議書の書式を事前にある程度決めておくと、チェック項目が減らせ業務効率化につながります。稟議書の書式を整えると、担当者の情報不足による記入ミスも減らせ、差し戻しリスクの減少につながるといえるでしょう。
上長の承認を得る
稟議書に上長の承認を得ます。承認の必要な上長が複数人居る場合、稟議書に必要な上長の押印欄を作成しておき、社内で定めた順番に沿って稟議書を回しましょう。
内容に不備があった場合は、担当者に差し戻します。
経理の確認・仕訳
稟議書が経理に回ってきたら、確認し仕訳を行います。内容の不備があった場合、上長または担当者に確認が必要です。
経理から従業員へ支払
立替精算のルールをあらかじめ社内で定めておきます。例えば、指定日や給料日にまとめて精算、稟議書が来た都度精算、など会社によりさまざまです。
稟議書が提出される都度小口現金で支払う会社もあれば、ある程度まとめて振込を行う会社もあるでしょう。
会社の規模や経理の負担具合などにより、自社に適したルールが必要です。なお、振り込む場合は給料と一緒に処理すると、振込手数料の負担額を減らせます。
立替精算が生じる主な機会
立替精算が生じる機会はある程度限られています。ここでは、代表的なものを見ていきましょう。
交通費
営業担当者が取引先に訪問する時の、移動費用などを指します。例えば、バスや電車の運賃、タクシー代、社用車や自家用車で移動する場合の駐車場代などが該当します。
交通費計算に関する記事はこちらです。
出張費
旅費規程などに基づき、出張時に支給される費用です。交通費・宿泊費・出張日当などが含まれます。企業により、移動距離や宿泊の有無などで出張規定を定めています。
旅費規定があいまいな場合は、きちんと整理しておきましょう。
立替精算の注意点
立替精算は、手数が多くミスが発生しやすい業務の1つと言えるでしょう。経理担当者、立替担当者共に負担の大きい点にも注意が必要です。できるだけ、事前にわかりやすく処理しやすい社内ルールを定めておかなければなりません。
ここでは、立替精算の時に注意しておきたい点を4つみていきましょう。
電子帳簿保存法
2022年1月1日より、電子取引によりWeb領収書を受領した場合は、電子保存することが義務付けられています。(ただし、2023年12月31日までは紙に出力して保存しても良い)
そのため、社員が電子データで領収書を受領した場合は、従業員から電子データを受け取らなければなりません。例えば、Amazonなどのオンラインショップで買い物をした場合、Web領収書を受領することもあるでしょう。
その時になって慌てないように、会社としてどのように領収書データを保存していくのか、社員はどのように稟議申請すればよいのか、具体的なルールをあらかじめ定めておかなければなりません。
ミスを誘発しやすい
立替精算は担当者・経理担当者共に、ミスを誘発しやすい仕組みとなっています。その理由はいくつかあります。主なミスの要因をみていきましょう。
立替精算の仕組みは複雑です。立替頻度が少ない社員は、稟議の書き方や稟議書のまわし方、領収書の貰い方などに慣れることができません。そのため、何度も同じようなミスを繰り返してしまいます。これを防止するためには、初めての社員でも簡単に立替精算できるようなわかりやすい社内ルールが必要になります。
一般的な稟議書は紙で上長や経理などにまわすため、途中で紛失するリスクがあります。その場合、稟議書に貼り付けた領収書も一緒に紛失してしまうため注意しなければなりません。稟議書紛失のリスクを防止するためには、オンラインで稟議書が提出できる「経費精算システム」の導入を検討してみましょう。
立替社員は経理部署以外の人間の場合が多く、領収書の処理に慣れていません。そのため、金額の書き間違えや領収書の宛名間違いなどを誘発しがちな点があるため注意が必要です。
経理担当者の元には、数多くの稟議書が回ってきます。1つずつ確認し仕訳・経費精算を行うには時間がかかります。とくに忙しい時期に多くの稟議書が回ってきた場合、ミスの誘発につながるため注意しましょう。
業務の負担になる
立替精算は担当者・経理担当者ともに業務の負担となります。
自分のお金を立て替えなければならない点で負担を感じる担当者も少なくありません。さらに、領収書を受け取り稟議書を記入し上長の印をもらうという、多くの業務が発生します。
現金で立替精算を行っている場合は、どこかのタイミングで経理担当者と直接会い、現金を受け取らなければなりません。
経理担当者にとっては振込や現金の受け渡しの手間だけでなく、仕訳の手間も生じます。
月またぎ・年度またぎに気を付ける
立替精算を行う際、月またぎや年またぎには気を付けなければなりません。
商法上、立替精算の事項は5年と定められているため、月またぎの精算は法律上の問題はありません。
年度またぎの立替精算を行う場合は「発生主義の原則」に従わなければならないため、注意が必要です。たとえ精算が可能でも、経理担当者は前年度分の経費計上が必要となり、仕訳の手間が生じます。手間や負担が増えるとミスの誘発にもつながります。
また、立替精算にあまり長く余裕を持たせておくと、担当社員が申請自体を忘れる可能性もあるため注意が必要です。
不必要な月またぎ・年度またぎを防止する為に、立替精算には、「担当者の経費支払後、10日以内に提出する」など、一定の締め切りを設けておきましょう。
立替精算の負担改善方法
立替精算には多くの負担が生じます。負担が増えるとミスを誘発するため、注意しなければなりません。
ここでは、立替精算の負担改善方法をみていきましょう。
法人用クレジットカード
法人用クレジットカードを導入すると、現金の受け渡しの手間がなくなります。加えて、短答社員は自分のお金を立て替える必要がなくなるため、金銭的な負担改善にもつながります。
立替精算以外でも、法人用カードの導入でキャッシュレスが進むと経理担当者の業務効率化がすすむため、導入を検討してみましょう。
法人カードの経費精算効率化に関する記事はこちらです。
経費精算システム
紙の稟議書を回すと、紙紛失のリスクが伴います。また、押印のために上長や担当者はわざわざ会社に出向かなければならないため、負担と感じる場合が少なくありません。
経費精算システムを導入すると、稟議書の承認がオンライン化できます。手持ちのスマホやパソコンから承認できるため、上長は稟議書押印のために出勤する手間がいりません。紙の稟議書と違い紛失のリスクもないため、立替精算の負担軽減がみこめます。
外注化
必要であれば、立替精算を外注化することも可能です。ただし、外注化にあたり社内と外部とをつなぐために立替精算業務の内容をマニュアル化し、具体的な作業内容などを指示しなければなりません。
社内ルールの明文化には時間がかかります。また、外注にはある程度の費用が必要です。経費精算の負担度合いと必要費用を見比べて、外注化の是非を決定しましょう。
まとめ
立替精算とは従業員が必要な経費を自分で立て替え、その後会社から経費精算を行うという一連の流れを指します。
立替担当者、経理担当者ともに負担が多い業務となります。負担が増えるとミスの誘発につながるため注意が必要です。必要に応じて社内ルールを整え、デジタルツールや法人カードの導入などを検討し、簡略化・自動化をすすめましょう。
NTTコミュニケーションズでは経費精算ツール”ビジネスd経費精算”を提供しています。
ビジネスd経費精算ではプリペイドカードとの連携により、経費申請の手間が省けて、従業員の立替の負担や経理担当者の振込の手間がなくなります。
日々の精算業務に頭を悩ませている場合は、是非ビジネスd経費精算の導入を検討してみましょう。
経費精算でお悩みの方へ
こんなお悩みございませんか?
 経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる
経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる 立替の事務手続きが多い
立替の事務手続きが多い 出社せずに経費精算を完結させたい
出社せずに経費精算を完結させたい 定期代支給を廃止し、都度精算にしたい
定期代支給を廃止し、都度精算にしたい
そのお悩み、ビジネスd経費精算ですべて解決できます!





 JP
JP


















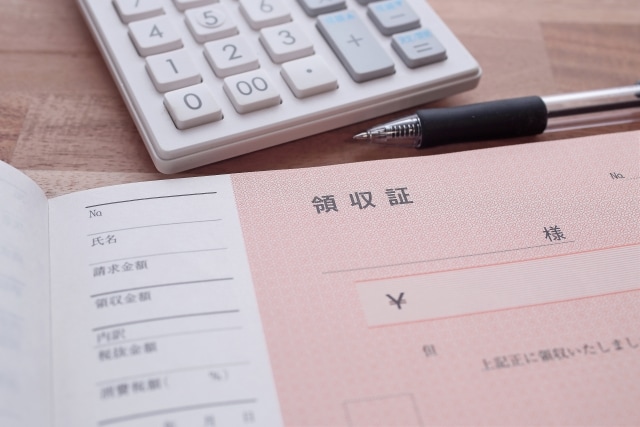




 あわせて読みたいおすすめの記事
あわせて読みたいおすすめの記事





