電子帳簿保存法の2年猶予とは?主な改正内容や対応方法を解説

公開日:2022/11/25
電子帳簿保存法の改正には、2年間の猶予があります。この猶予期間に何をすればよいのか、期間が終わった後はどう変わるのか気になる担当者の方は少なくありません。 本記事では2年猶予について解説します。改正内容や対応方法にも触れるので、参考にしてください。
目次
2022年の電子帳簿保存法の代表的な改正内容とは
2022年に大幅に改正された電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データによって保存する際の方法について定めた法律です。
国税関係の帳簿などは基本的に7年間の保存が義務付けられています。そのため、用紙の保管場所に多くのスペースが必要でした。ペーパーレス化に取り組みたい企業にとっては朗報といえるでしょう。紙ではなく電子データとして保存できるため、必要な情報をすぐに検索できるのも電子保存のメリットの1つです。
帳簿や書類を電子化すれば、コスト削減や業務効率化につながります。
2022年に大幅に法改正がありました。なかでも把握しておきたい主な点は次の3つです。それぞれについて詳しくみていきましょう。
事前承認制度の廃止
従前は、帳簿の電子化を行う際は税務署への事前申請と承認が不可欠でした。しかし、事前承認制度は廃止となりました。
そのため、各企業は法令に対応する準備を整えたらすぐに、制度を運用できます。
検索機能要件の緩和
改正前は検索機能要件として、複数項目のかけ合わせといった複雑なものが求められていました。
改正後は、帳簿・書類に関する検索要件が廃止されています。スキャナ保存や電子取引に関する検索要件もシンプルなものに緩和されており、具体的な要件は次の3つです。
・「日付」「金額」「取引先」の3項目を検索条件として設定
・日付と金額の範囲指定で検索可能
・2項目以上を組み合わせて検索可能
システムやツールを利用する際は、これらの検索要件を満たしたものを選択しましょう。
電子データ保存の厳格化
改正前は電子データで受け取った領収書・請求書・発注書などの国税関係の書類を、書面に出力し、紙媒体で保存することが可能でした。
しかし、改正後は電子データで受け取った場合、データで保存することが義務化されました。2024年1月1日からは紙に印刷しての保存が認められなくなるため注意が必要です。
これまでは全て書面で保存していた企業も、今後は電子取引で受け取った書類に関しては電子データで保存しなければなりません。
電子帳簿保存法の2年猶予とは
改正法は2022年1月1日から施行されています。しかし、多くの企業がシステムの改修やワークフロー整備が間に合っておらず、対応できないという声があがりました。
また、これまで電子データで受理していたものを、あえて紙で受け取る企業も出てきたため法の思惑とは逆行してしまう例もあがっています。
これらの混乱に対応するため、改正法への対応が間に合わない場合、下記2つの条件を満たせば、書面での保存が認められることとなりました。
所轄税務署が妥当と判断できる、やむを得ない理由がある場合
出力書面を適切に保存し、提示の求めがあった場合応じられるようにしておくこと
やむを得ない理由として、「システムの準備が間に合わない」などがあげられるでしょう。しかし、この妥当性を判断するのは所轄税務署となります。
税務署への届出は不要
猶予期間に「紙出力」を選択する場合においても、税務署への届出は不要です。自社の判断のみで、書面での保存または電子データでの保存が選択できます。
ただし、この猶予期間は2023年12月31日までです。その後は、電子データとして保存できるよう、各企業は早めの準備や対策が欠かせません。
電子帳簿保存法への対応は必須
電子データ保存が義務化されるため、全ての企業において改正法への対応が必須となります。たとえ、現在該当する取引が1つもない場合でも、IT化が進む一方の現代において今後も発生しないとは言い切れません。
多くの国税関係の帳簿や書類は7年間の保存義務があります。そのため、7年間データを長期保存できる保存先を確保しなければなりません。会社によってはデータ量が膨大になるところもあるでしょう。
豊富なデータを長期間保存できるクラウドサービスやシステムなどの準備が欠かせません。この法律にはデータバックアップの義務はありません。しかし、国税関係に必要なデータは企業としても重要なものばかりです。消失した場合、企業運営に差し障るため万全の態勢で臨まなければなりません。
万が一、データが消えてしまった場合に備え、バックアップの準備もしておきましょう。
2年間は体制作りのための期間
期限までの2年間は社内の体制を整えるための期間です。データ保存には一定の要件が課せられています。
その要件にあうシステムを探し、準備しておきましょう。紙ベースからデータベースに切り替える際は、業務フローが大幅に変わることも少なくありません。
業務フローを見直し、変更点についてはルールを作成して周知徹底が必要です。
例えば、これまで経費精算において紙の領収書で申請していた場合は、写真で領収書を撮影してデータ化し申請する方法に変更することもあるでしょう。それにあわせて、稟議書をデータ化すれば上司の認定方法も変わってきます。
どこまでを電子化するのか見極めて、それに伴い変更していく業務について洗い出さなければなりません。
改正への対応は面倒だと感じる企業もあるでしょう。
しかし、これまで書面で保存していた国税関係の書類をデータで保存することは企業にとっても大きなメリットにつながります。主なメリットは次の2つです。
・書類の保管場所が不要となる
・経理業務の効率化
国税関係の書類は7年間の長期保存義務があります。書面で保存している場合大きなスペースが必要です。また、保存するためのキャビネットやバインダーなど多くの経費が必要でした。しかし、データ保存するとこのようなスペースや備品が不要になります。
書面保存している場合、情報を探すのに多くの時間がかかります。さまざまな書類をめくり、情報を探さなければたどり着けません。しかし、データ保存であれば必要なデータはすぐに検索可能です。経理業務の効率化につながるといえるでしょう。
DX化に関する記事はこちらです。
電子帳簿保存法の対応方法
法律に対応するために、何から始めればよいかわからないこともあるでしょう。ここでは、対応方法についてみていきます。
社内の電子取引の内容を把握する
現在、社内でどの程度の電子取引があるのか洗い出します。あわせて、電子取引以外の紙の領収書なども今後はデータ保存するのか従来通り書面保存するのか、対応を決めておきましょう。
保存システムの容量がどの程度必要か見積もるためには、電子情報がどの程度の量になるか把握しておかなければなりません。
会計処理に関する記事はこちらです。
データ保存の要件を満たす
データを保存する場合は「真実性」と「可視性」を担保しなければなりません。具体的には、次の要件などを満たしておく必要があります。
・訂正・削除・追加などの履歴が分かるシステムを利用する
・使用するシステムの説明書を備えておく
・ディスプレイやプリンタの準備
・検索条件として「日付」「ファイル名」「金額」などの指定ができる
領収書やレシート、請求書などの取引関係書類にはスキャナ保存が認められています。
スキャナ保存で必要な保存要件は次のとおりです。
・書類の訂正・削除の事実やその内容確認が可能
・検索条件として「日付」「金額」「取引先」の指定ができる
・税務職員の求めによりデータのダウンロード可能
システムを利用する際は、要件を満たしていることを事前に確認しておきましょう。
紙はスキャナ保存制度を活用する
取引関係書類にはスキャナ保存が認められています。取引先関係書類の主なものは次のとおりです。
・領収書
・レシート
・見積書
・契約書
・請求書
スキャナ保存は、スキャナ本体を利用したものだけでなく、スマートフォンやデジタルカメラで撮影したものも含まれるため、利便性が向上しています。
スキャナ保存制度を活用すると、紙の原本が廃棄できる点はメリットといえるでしょう。印刷や紙の保管コストなどの削減につながります。
領収書に関する記事はこちらです。
電子帳簿保存法の運用事例
法律に沿って運用していくためには、スモールステップで取り組むことが欠かせません。
例えば、立替経費計算の処理を紙で行っていた場合、スキャナ保存に対応させるといった場合に必要な流れをみていきましょう。
経費精算を電子化する場合、外部のツールを導入する企業は少なくありません。ビジネスd経費精算など、電子帳簿保存法に対応したツールを選択します。
また、経費精算に関するこれまでのフローを確認し、システムを導入した際のフローではどう変更があるのか把握しましょう。
ツールの使用により、上長は自分のスマホで部下の稟議書が確認できるようになるため、これまでのように、稟議書をまわして上長の承認印を求めるといった、面倒な手作業が廃止できます。
ルールが大幅に変わると混乱が生じます。事前に、経費精算ルールを改定し社内に周知した後で、運用を開始しましょう。不都合が生じた場合は、その都度見直すことで快適な運用が可能になります。
経費精算キャッシュレス化についての記事はこちらです。
まとめ
電子帳簿保存法の施行は2024年1月1日です。その日から、特定の取引の電子データ保存が義務化されるため、それまでに、社内の現状を把握し必要な準備を整えておかなければなりません。
この機会にペーパーレス化に取り組む企業も増えると考えられています。データ保存の要件を満たすシステムの利用が欠かせません。必要に応じて社外のツールの利用を検討してみましょう。
NTTコミュニケーションズが提供するビジネスd経費精算は、電子帳簿保存法に対応しています。サービスを利用すると、経費精算業務が簡略化されるため利便性が向上します。要件を満たしたシステムを利用したい場合、ビジネスd経費精算を検討してみましょう。
経費精算でお悩みの方へ
こんなお悩みございませんか?
 経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる
経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる 立替の事務手続きが多い
立替の事務手続きが多い 出社せずに経費精算を完結させたい
出社せずに経費精算を完結させたい 定期代支給を廃止し、都度精算にしたい
定期代支給を廃止し、都度精算にしたい
そのお悩み、ビジネスd経費精算ですべて解決できます!





 JP
JP



















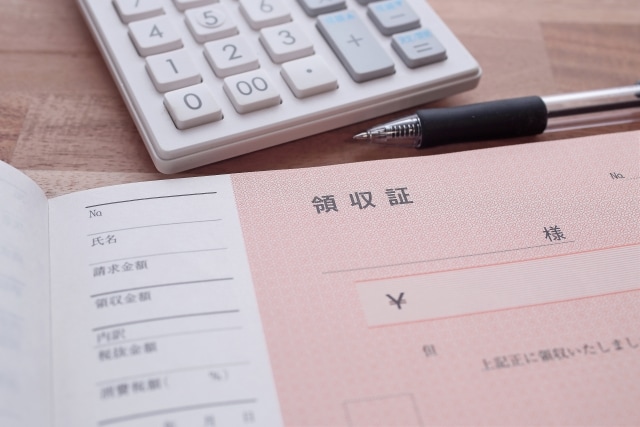



 あわせて読みたいおすすめの記事
あわせて読みたいおすすめの記事





