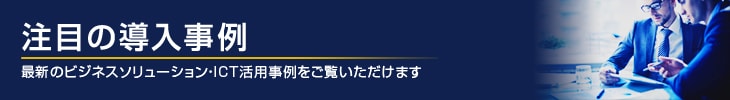マカフィー株式会社
顧客のセルフサービスによる早期解決を支援、
マカフィーが目指す「Call to Web」の仕組み

マカフィー株式会社
カスタマーサクセスグループ
コンシューマーサポートデリバリー
オペレーションマネージャー
宮﨑 竜一氏
「『Call to Web』をはじめとして、お客様のサポート経験の向上をめざしています」
課題
約半数が気づいていないWeb上のFAQページに、
コンタクトセンターから誘導したい
ウイルス対策ソフトなど、個人ユーザー向けのソフトウェアも販売するマカフィーでは、顧客からの問い合わせを受け付けるコンタクトセンターを2つ開設している。1つは、技術的な問い合わせに対応する『テクニカルサポートセンター』、もう1つが契約関連の問い合わせに対応する『カスタマーサービスセンター』だ。
しかし、カスタマーサクセスグループのコンシューマーサポートデリバリーでオペレーションマネージャーを務める宮﨑竜一氏は、従来のコンシューマー向けコンタクトセンターのあり方に、課題を抱えていたという。
「問い合わせ内容の上位にランクインしていたのは、インストールやプロファイル情報の変更など、比較的容易といえる操作が大半でした。弊社ではWeb上のサポートページに、こうした操作に関するFAQを用意していました。しかし、電話で問い合わせをする顧客の約半数が、その存在を知らなかったのです。実際に、問い合わせをしてくる顧客とオペレーターとのやり取りをモニターしても、FAQページを紹介するだけで解決できる事例が少なくありませんでした」
これに加えて、セキュリティベンダーである同社ならではの課題もあった。それはマルウェアのアウトブレーク(大規模感染)や、一時的なトラブルなどが原因で発生する、突発的な「コールスパイク」(コールの集中)だ。コールスパイクがいつ起きるのか、その予測は容易ではなく、オペレーターの人数をあらかじめ確保しておくことは現実的ではない。このような緊急事態にも、平時と同じように、応答率を低下させない仕組みの構築が急務となっていた。
「商品の購入や、お問い合わせに至るまでの顧客の行動、思考プロセスは、従来とは大きく変わってきています。それならば、『早急な解決を望まれているものの、解決策を見つけられずにお電話をお掛けいただいたITリテラシーの高い方』に対してFAQによる自己解決を促進することが、最終的に顧客にとっても我々にとってもメリットになると考えました」(宮﨑氏)
このページのトップへ
対策
IVRとSMS送信を組み合わせた
顧客の“自己解決”を促すソリューションを導入
マカフィーが「自己解決」のために選択したのが、NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」だ。ナビダイヤルのIVR(音声自動応答)機能に、SMS(携帯電話のショートメッセージサービス)の自動送信システムを組み合わせたシステムを導入した。なぜ、IVRとSMSを連携させたのだろうか?そのポイントは、着信時の自動音声ガイダンスで「自己解決」を促すことにあった。
マカフィーが導入したシステムでは、まずは問い合わせのコールに対し、解決策の概要とFAQページの存在をIVRでアナウンスする。次に、ナビダイヤルの「発信者端末種別ルーティング」という機能を使って、発信元がモバイル端末か、固定電話かの判別を行う。もしモバイル端末からコールしてきた場合は、FAQページのURLをSMSで即時送信し、FAQへの遷移を促す。
同社ではこの仕組みを「Call to Web」と呼び、コンタクトセンターの新しいソリューションとして位置付けている。
「“Call to Web”の発端となったのは、ガイダンス時に解決策をサジェストしたら、自己解決を試みる方が一定数いるのではないかと思ったことです。加えて、ナビダイヤルの機能の1つであるトラフィックレポートを分析すると、約半数の問い合わせがモバイル端末からによるものということも判明しました。それであれば、SMSの配信が有効なのではないかとも考えました。これらの仮説が、Call to Webソリューションの発想につながっています」(宮﨑氏)
さらに、同社ではSMS送信が利用できない固定電話からの問い合わせの場合でも、顧客がFAQサイトをWebで検索しやすくするために、既存のサポートページにSEO対策を施した。CMでよく見かける「続きはWeb」のフレーズを参考にして、「マカフィー サポート」などの単純明快なキーワードで検索できるようにし、SMS以外のルートでもIVRガイダンスから簡単にFAQに誘導できる導線を整備している。
このページのトップへ
効果
PDCAを高速で回し、
自己解決率の向上を実現
マカフィーがこの「Call to Web」の仕組みを成功させるうえで、特に重要なポイントになったのが、ナビダイヤルのIVRの音声ガイダンスが簡単に自分達で変更できることだった。
音声ガイダンスでFAQを紹介したり、SMS送信でFAQへ誘導する仕組みを作ることは確かに大切だが、それと同時にお客さまに「FAQを見てみようか」と思っていただけるメッセージ作りが重要だ。
どのタイミングで、どのようなメッセージを、それぞれのお客さまにお伝えするのが最適なのか、試行錯誤しPDCAを回していく上で、コールフロー変更や音声ガイダンスの内容変更を自分達で柔軟に実施できる仕組みが必要だった。
同社でかつて利用していたオンプレミスの応答システムでは、IVRの内容を変更するために、ナレーターの音声を録音し、外部ベンダー経由でIVRに登録する必要があった。場合によっては変更に1週間を要することもあったという。
「現代のコンタクトセンターでは、顧客ニーズの多様化に合わせ、ガイダンス内容には常に変更・最適化が求められています。ナビダイヤルでは、テキストベースで登録すれば、ガイダンスを音声合成で作成できます。その作業は30分もかかりません。このため、IVRのガイダンスの変更・修正を柔軟に行えるようになりました。また、電話で問い合わせいただいたお客様が、どのような誘導ガイダンスであれば、Webを見たくなるのか、日々工夫を重ねてガイダンスの改良を行っています」(宮崎氏)
この機能を使うことで、突発的なコールスパイクに対応する際のガイダンス作成も簡単になり、問い合わせ動向を見ながら、ガイダンスの内容を最適化することが容易になった。これにより、同社ではPDCAを迅速に回すことが可能になったといいう。
「トラフィックレポートを分析すると、サポートセンターが営業していない時間帯においても一定の着信が確認できました。そこで、営業時間外でも、Call to Webを実践することにしました。営業時間外のガイダンスにも、ナビダイヤルの発信者端末種別ルーティングを入れており、モバイル端末の方には、平日と同様にSMSでFAQページをご案内しています。時間外のコール数の全体の30%にSMSが送信されていますので、一定の効果があるとみています」(宮﨑氏)
マカフィーでは現在、Call to Webの運用に、Caller ID(発信者番号通知)を活用することで、導入効果を検証している。
「ナビダイヤルのトラフィックレポートと、SMS送信システム、そしてコールセンターのPBX、これら3つのシステムに記録されたCaller IDを突合することで、“自己解決数”を算出しています。例えば3つのシステム全てにCaller IDが存在する場合にはCall to WebでFAQを見ていただいたにも関わらず再コールされたことになりますので、自己解決できなかったと判断しています。一方、ナビダイヤルのトラフィックレポートとSMS送信システムにCaller IDが存在しながらコールセンターのPBX側に同IDが存在しない場合には、Call to Webにより自己解決が成功したものと想定されます。そのほかにも様々な組み合わせパターンがありますが、それぞれのシステムに記録される同IDの存在を突合することによって、自己解決効果をある程度検証できると考えています」(宮﨑氏)
これらの分析によると、想定自己解決率はCall to Web導入以来、上昇傾向にあり、最大で約20%の顧客が、問い合わせ後、FAQページを閲覧するなどの行動をとり、自ら問題を解決しているという。課題であったコールスパイクへの対応についても、一定の成果を上げることができている。
宮﨑氏は、顧客体験をさらに向上させるため、すでに次のソリューションの導入を視野に入れている。
「今回の、Call to Web の取り組みで一定の手応えを感じています。チャットボットなどの導入を含めて、今後ともお客様のサポート経験のさらなる向上に努めてまいります」
図 「Call to Web」の実践でIVRガイダンスのナビゲーションを強化

このページのトップへ

マカフィー株式会社
事業概要
1987年にアメリカで創設された、グローバルに展開するサイバーセキュリティ企業。創業以来、30年以上をかけて世界的な脅威データベースを構築しており、6億2千万台を超えるエンドポイントから脅威データを収集、分析することでユーザーのIT環境のリスク低減に貢献している。
URL
https://www.mcafee.com/japan/home/
 「マカフィー株式会社」導入事例印刷用ファイルのダウンロード
「マカフィー株式会社」導入事例印刷用ファイルのダウンロード
(265KB)
 PDFファイルをご覧いただくためには、「Adobe Reader」がインストールされている環境が必要となります。
PDFファイルをご覧いただくためには、「Adobe Reader」がインストールされている環境が必要となります。
(掲載内容は2019年8月現在のものです)
関連リンク



 JP
JP