
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK
オフィスに縛られないハイブリッドワークを快適にしたい。働く場所に合わせてスピーディかつリーズナブルに最適なネットワークやゼロトラストのセキュリティ対策を導入したい。 いつでも、どこからでも、安心・安全・簡単にセキュリティと一体化した統合ネットワークサービスです。
関連コラム
交通課題を解決するMaaSを解説 移動手段はどう変わるのか
近年、「MaaS(Mobility as a Service)」という言葉を聞く機会が増えました。これは交通機関の利用者に限らず、多くの企業にも影響を及ぼし得るものです。そこで本記事では、MaaSの概要やメリット、今後の展望などについて解説します。経営者の方はMaaSへの理解を深め、その動向を逐次チェックしていきましょう。
MaaSとは
MaaSとは
「移動」は私たちの生活において欠かせない基本的行動の1つであり、電車やバス、飛行機、タクシーなど、その手段は多岐にわたります。しかし、それぞれの交通サービスを提供している事業者は異なるため、当然ながら料金体系や利用料金はバラバラです。移動できる範囲にも差があり、実際のところ完全に自由な選択ができるわけではありません。
そのため、どこかへ移動をするときには、短い時間で移動できる方法や安く移動できる方法を利用者が調べることになります。しかも、エリアによっては地理がかなり複雑なところもあり、ルート検索は簡単ではありません。
そこで近年、世界的に注目を集めているのが「MaaS(マース)」です。これは「Mobility as a Service」の略で、種々の交通手段を統合したサービスや、あるいはそのサービスを実現する仕組みのことを指します。MaaSの推進に向けて共通基盤構築を目指す団体では、MaaSを「いろいろな交通サービスを1つの移動手段として統合したもの」と捉えています。

たとえば、バスと電車を使って目的地を目指す場合、従来ではバスの時間や料金を調べ、その到着時刻に合うように電車の時間を調べるという方法が主流でした。しかし、この方法では複数の路線があった場合、考慮すべきルートや移動時間、料金のパターンが増え、最適な選択肢を見出すことが難しいという課題があります。その点、MaaSの仕組みが実現されれば、1つのサービスを使うだけで、バスと電車を統合した効率的なルート検索などが可能になるのです。
MaaSが生まれた背景
MaaSの語源はフィンランドにあります。フィンランドで各種モビリティの情報検索および予約、支払いまでを完結できるMaaSビジネスが生まれたことをきっかけに、世界中へMaaSの考え方や仕組みが広がっていきました。
そのため、フィンランドではMaaSの普及が比較的進んでおり、2025年までに首都ヘルシンキ市における自家用車ゼロを目指したロードマップも示されています。これはMaaSの水準を高めることで、市民は自家用車を使う必要がなくなり、公共の交通手段を活用したほうがより便利に移動できるようになるためです。
実際、フィンランドでは世界初のMaaSプラットフォームが作られ、さまざまな交通機関をアプリ上で検索・予約・決済までできるようになっています。しかも交通手段は定額制のため、市内のバスや電車は使い放題です。ここまでくると、さすがに自家用車の必要性は相対的に低くなり、自家用車ゼロも現実味を帯びてきます。
フィンランドでこれほどMaaSが進んでいるのには、国内に自動車メーカーがないことが大きく関係しています。これはすなわち、フィンランド国民が自動車を購入すると、外国にお金が出ていってしまうことを意味します。国内経済の観点からして、公共交通機関を使ってもらったほうが都合がよいのです。
逆にいえば、自動車メーカーを多く抱える国では、これだけスピーディにMaaSを普及させるのは難しいかもしれません。とはいえ、MaaSの普及に向けた取り組みは世界各国で着実に進んでおり、日本でも徐々に交通サービスの利便性が高まってきています。
MaaSのメリット
MaaSのメリット

MaaSの主なメリットとしては、いろいろな交通手段をシームレスに利用できるようになることがまず挙げられます。たとえ提供事業者が異なるサービスであっても、横断的な利用が可能となるため、利用者はより効率的かつスムーズに移動方法の下調べや予約・支払いまで行えます。
また、自家用車が不要になる点もメリットです。交通サービスが統合された場合、自家用車による移動のほうが高コストとなります。というのも、移動のために仕方なく自家用車を所有する必要がなくなるため、車の購入費や維持費、給油代といった諸々のコストを削減できるからです。もっとも、これはフィンランドのような高い水準でMaaSが普及することが前提ですが、決して可能性のない話ではありません。
さらに自家用車の数が減ることで、渋滞が緩和されるメリットもあります。日本は東京一極集中型ゆえ、関東圏に続く渋滞がしばしば問題となり、特に夏休みなどの長期休暇では帰省・Uターンラッシュのピーク時に長蛇の列が並びがちです。自家用車の数が減れば、その分だけトラフィックに余裕が生まれ、移動もよりスムーズになり、ひいては経済活動の活発化につながります。
もう1つ押さえておきたいメリットとして、公共交通機関のサービスレベルの向上が挙げられます。現状の交通サービスが利用しやすくなるのはもちろん、統合された環境下で多くの人がサービスを利用するほど、多様なデータが分析しやすい形で集まります。それらのデータをもとにバス停の配置やバリアフリー化など、交通環境の整備がより進めやすくなるのです。利用者の属性や使用した移動手段、目的地や宿泊地といった情報も集まるため、交通に関連するさまざまな業界にも影響します。
MaaSの5段階 日本はレベル1
MaaSには何も施されていない状態を含め「0~4」の5つの段階があり、段階ごとに統合される範囲が広がっていきます。そのため、ルート検索がまとめてできるだけでは、十分にMaaSが実現されているとは評価できません。以下では、各段階の詳細について解説します。
レベル0 移動ごとに個別対応
レベル0は、何も統合されていない状態です。バスのサービスならバスのことだけ、電車のサービスなら電車のことだけを調べたり予約したりできますが、利用者が個別に対応しなければなりません。そのため、各サービスが充実していたとしても、利用者には全体として大きな手間が生じます。
レベル1 情報の統合
レベル1は「Integration of Information(情報の統合)」とも呼ばれ、移動に関する情報がまとめられた状態を指します。多くの主流な地図アプリや経路検索Webサービスは、このレベル1を満たすものです。各交通手段を横断する形や、利用料金をまとめた形でもルート検索を行えます。そのため、鉄道やバス会社のWebサイトを個別に調べたのでは判断が難しい場合でも、最適な移動手段を知ることが可能となります。
ただし、必要な情報は調べられるものの、実際にそのルートで移動するサービスを受けるところまでには至らず、あくまで下調べまでです。ちなみに日本は、現状このレベル1のフェーズにあるとされています。
レベル2 予約・支払いの統合
レベル2は「Integration of booking & payment(予約と決済の統合)」と呼ばれます。近年は日本でも一部レベル2に相当するサービスが提供され始めていますが、未だ十分に普及しているとはいえません。一方、欧米はレベル2相当にあるとされています。
レベル2では最適なルートがわかるだけでなく、その移動を実現するための予約から支払いまでを一括して行えるという点で、レベル1とは大きく水を空けています。予約や決済は主にアプリ上で行われます。
レベル3 サービスの統合
レベル3は「Integration of the service offer(サービス提供の統合)」と呼ばれ、フィンランドがこのフェーズに相当します。このフェーズでは予約などをまとめて行えるだけでなく、利用者が1つのサービスを利用するだけで各種交通サービスが利用可能です。これはMaaSオペレーターが事業者の垣根を超え、移動手段を一元化したパッケージとしてサービスを代理提供するためです。
レベル3に達すると、交通手段ごとに料金体系を理解する必要がなくなり、利用者はより簡単・便利に移動ができるようになります。また、フィンランドが期間定額制を採用しているように、利用者はコスト面でも恩恵を受けられます。
ここでのポイントは、事業者同士が連携しているという点です。そして利用者と事業者との間をMaaSオペレーターが仲介します。
レベル4 地域全体で実施
レベル4は「Integration of policy(政策の統合)」と呼ばれ、交通サービスを提供する事業者のみならず、政策レベルで統合された状態を指します。つまり、事業者同士の連携がキーとなるレベル3とは異なり、こちらはさらに官民連携されている点がポイントです。そのため、都市計画やインフラ整備というサービス提供以前の段階から一体となり、結果としてより高水準な交通サービスが実現しやすくなります。
MaaSがもたらすインパクト
MaaSがもたらすインパクト
今後もMaaSへの取り組みが進み、少しずつレベルが上昇していけば、多くの国や地域で便利な移動が実現されていきます。以下では、MaaSの普及が社会全体にもたらしうる影響について見てきましょう。
渋滞の解消
先述したように、MaaSの普及は渋滞の緩和に寄与します。渋滞は巻き込まれた個人を不快にさせ、スムーズな移動を阻害するものですが、社会全体の問題でもあります。渋滞の緩和は個人の活動を促し、社会全体の活発化にもつながります。
また、渋滞はときに流通をも阻害し、直接的に経済へ影響を及ぼすことがあります。渋滞があるだけで業務効率を損ね、生産性が落ちてしまうためです。そういう意味では、ほかのさまざま業界においても、移動の円滑化がもたらす影響は大きいといえます。
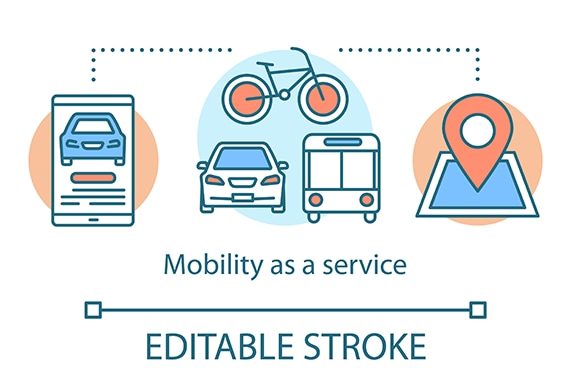
温室効果ガスの排出抑制
渋滞の緩和においてもいえることですが、MaaSの普及により自家用車の利用が減ると、温室効果ガスの排出が抑制されます。バスやタクシーなども環境負荷を大きくする要因ではありますが、交通全体の効率化が図られることで、交通機関の稼働に対する負荷の割合を減らせます。
特に近年では環境問題が取り沙汰されており、「環境負荷を与えてでも大きな成果を出す」よりも、「環境負荷を小さくして効率的に成果を出す」という考え方のほうが支持される傾向にあります。
各国が取り組むSDGsにおいても「クリーンであること」「気候変動への対策」「海洋資源の保全」など、環境問題への対応が重視されています。その点、MaaSはSDGsにも通じる仕組みであるといえます。
地方の交通も便利に
都心部と比べて、地方における交通の利便性は極めて低い傾向にあります。都心部であればさまざまな移動手段が用意されており、利用者は選択的に移動することが可能です。それがかえってルート検索を複雑化させている要因でもあるのですが、地方ではその選択の余地すらほとんどありません。「どのルートを選ぶべきか」という以前に、そもそも「移動ができない」という問題を抱えているのです。そのため、多くの地域では自家用車が半ば必須となっています。
MaaSの普及が進めば、こうした問題も解決されると期待されています。なぜなら、より低コストで交通インフラを維持できるようになるからです。都心部で実証された効果的な交通システムを、その地方に最適化して適用すれば、効率的なインフラ構築が可能となり、そこで活動している人も移動しやすくなります。それゆえMaaSは、地方にも大きなインパクトを与えうるものと評価できます。
公共交通機関の収入増加
移動手段の最適化により公共交通機関の運営効率が向上したり、無駄を削減したりできれば、運賃収入も上がる可能性があります。収入が増加すればMaaSとは別に、個別のサービスレベル向上にもつながります。内部で働く者に給与アップといった形で還元されれば従業員満足度も向上しますし、職場環境・待遇が改善されれば人材獲得や接客品質の向上も期待できます。
海外の先進事例
先述したフィンランド以外にも、すでにMaaS実現に向けて大きな取り組みを始めている国があります。以下では、海外の先進事例についてご紹介します。
台湾の高雄でMaaSアプリが普及
MaaSの導入が進む台湾では、高雄(カオシュン)市にて定額制で公共交通機関を利用できるMaaSアプリが提供されています。同地域は兼ねてから公共交通機関の利用率が低い一方、バイクの利用率が非常に高いという状況にありました。しかもバイクによる死亡事故が多いことや、渋滞が多いことなども問題視されていました。そうした状況を受け、交通通信省と民間事業者が提携し、MaaSへの取り組みが始められたのです。
その結果、月額料金を支払うことで地下鉄や路面電車、バスなどが使い放題となるサービスの提供に至りました。当然、目的地までの最適な経路案内もしてくれます。ほかにも交通の利便性をよりよくするため、シェアサイクルの駐輪場や自転車専用道路の増設、各交通機関の案内板設置といった取り組みも行われています。
日本の動向
日本の動向
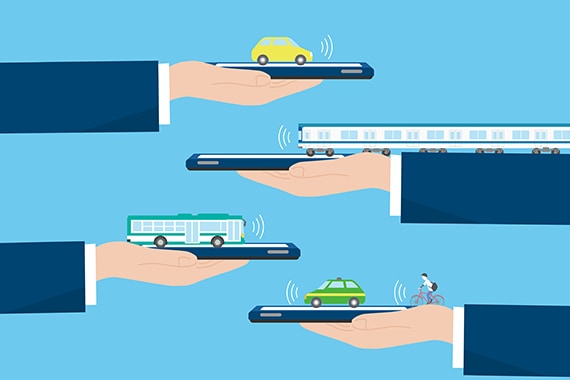
日本は現状、MaaSの普及が進んでいるとはいえませんが、全国各地でMaaSに関連するさまざまな実証実験が進められています。以下では、北海道上士幌町の取り組みを例にご紹介します。
北海道上士幌町で自動運転バスの実証実験
北海道上士幌町では2019年から、経済産業省・国土交通省の協力のもと、地域と企業の協働による挑戦を促す実証実験「スマートモビリティチャレンジ」が続けられています。
同実験は「交通弱者に対する移動サービスの利便性向上」「観光客の移動手段充実」を目的としており、高齢者のために自動運転バスを運行したり、スーパーの商品を配送したりするなどのサービスまで行っています。移動販売の需要性や自動運転の走行技術などが検証されており、こうした実験結果は上士幌町のみならず、全国でのMaaS導入に向けた取り組みに一役買っています。
なお、上士幌町ではバスの自動運転のほか、来訪者向けにMaaSアプリの提供も行っています。これはアプリのニーズ検証と同時に、カーシェアやレンタサイクルなどの新たなニーズ検証、技術検証などの目的も兼ねています。
今後の展望
最後に、日本におけるMaaSの展望について見ていきましょう。
国がMaaSを推進
2020年7月、閣議にて「革新的事業活動に関する実行計画案」が提出され、2025年までに目指すべき指針が策定されました。同案にはMaaSの推進も含まれており、大きく「地域における移動手段の維持・活性化」「モビリティと物流・サービスとの融合」「新しいまちづくりとモビリティ」「データ連携の加速」の4分野について具体的な推進内容が盛り込まれています。主な計画内容としては、たとえば次のようなものがあります。
- 観光や小売、医療などと連携したMaaSの実証結果から、課題やベストプラクティスを整理し、普及を図る
- 官民連携にて交通モード間の接続を強化し、新たなモビリティサービスにも対応可能な状態にする
- クラウドやQRコードによる乗車確認など、低コストで導入可能な取り組みの支援
- さまざまな交通機関におけるスマートフォンでの連携実現
(参照元:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai40/siryou1-2-2.pdf)
このようにMaaS実現に向けた具体的な指針が示されたことから、今後は民間の事業者のみならず、国を挙げた取り組みが期待されます。
MaaSの市場規模予測
富士経済の国内調査によると、MaaSの国内市場は2030年時点で2兆8,658億円まで伸びると予測されています。これは2018年比で3.5倍に相当する値であり、カーシェアに至っては11.9倍にも上るとの見通しです。いずれの伸びも「所有からシェアへ」という意識の変化や、ライフスタイルの変化の拡大が根拠として挙げられています。
(参照元:https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=20022.pdf&nocache)
総括すると、これからは交通インフラや関連サービスが大きく変化すると考えられるため、その変化を踏まえた経営戦略を立てることが重要です。今後の社会情勢に向けてアンテナを張っている企業の方、とりわけ交通関連の影響を受けやすい企業の方は、わずかな兆候も見逃さないようMaaSの動向を逐一チェックしていきましょう。
この記事の目次
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK
サービスに関するご質問など
お気軽にお問い合わせください
資料ダウンロード
-
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK
サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください
サービス詳細情報はこちら



 JP
JP
















