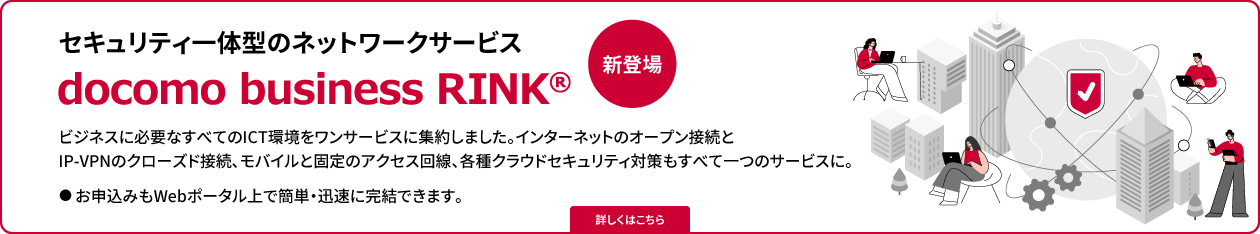選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK
オフィスに縛られないハイブリッドワークを快適にしたい。働く場所に合わせてスピーディかつリーズナブルに最適なネットワークやゼロトラストのセキュリティ対策を導入したい。 いつでも、どこからでも、安心・安全・簡単にセキュリティと一体化した統合ネットワークサービスです。
関連コラム
現在、各所においてDXに関する取り組みが行われていますが、「DXにより何を実現できるのか?」「どのようなアクションをするべきなのか?」といった疑問や悩みを抱えている企業も少なくないでしょう。
これらの課題に対する答えは、最終的には各企業が出す必要がありますが、その入り口部分で自社の取り組みを確認することや、現状を数値として理解することは、正しい決定のための一助となります。そこで役立つのが、DXに関する課題解決のためのツールとして政府が公表した「DX 推進ガイドライン」や「DX推進指標」です。
この記事では、DX 推進ガイドラインとDX推進指標の2つについて、詳しい内容や活用の仕方についてご説明します。
1. DX推進ガイドラインの概略について
1. DX推進ガイドラインの概略について
1-1.「DX 推進ガイドライン」とは?
「DX 推進ガイドライン」は、正式名称を「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」といい、平成30年12月に経済産業省により作成されました。
これまでも政府は、デジタル技術の急速な進歩を活かし、デジタルトランスフォーメーション(DX)の促進を図ってきましたが、多くの企業で取り組みは行われているものの、実際のビジネスの変革にはつながっていないという現状が明らかになりました。
また、国内ではシステムのブラックボックス化や現場サイドからの抵抗などが足かせとなっていることも、取り組みが進まない一因となっています。

このような状況を解決するために、平成30年9月に「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」が取りまとめられ、以降、DX推進にあたり取り組むべき具体的なアクションを策定した本ガイドラインが公表されました。
1-2. 「DX 推進ガイドライン」の構成
本ガイドラインは、主に以下の2つの項目から構成されています。
(1)DX 推進のための経営のあり方、仕組み
- 経営戦略・ビジョンの提示
- 経営トップのコミットメント
- DX 推進のための体制整備
- 投資等の意思決定のあり方
- DX により実現すべきもの: スピーディーな変化への対応力
(2)DX を実現する上で基盤となる IT システムの構築
- 全社的な IT システムの構築のための体制
- 全社的な IT システムの構築に向けたガバナンス
- 事業部門のオーナーシップと要件定義能力
- IT 資産の分析・評価
- IT 資産の仕分けとプランニング
- 刷新後の IT システム:変化への追従力
各項目については、先行事例や失敗事例が掲載されているため、自社での取り組みを考える上での参考にしやすいでしょう。また、全部で9Pとボリュームも少ないため、短い時間で目を通すことができます。
2. 「DX推進指標」の概略について
2-1. 「DX推進指標」とは? なぜ、作られたのか?
DX推進のために、DX 推進ガイドラインと併せて活用したいのが「DX推進指標」です。こちらも同様に経済産業省が公表したものであり、「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」の提言を踏まえ、実際にアクションにつなげるためのツールとして作られました。
「DX推進指標」では、「DX」について次のように定義しています。
『企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること』
「DX推進指標」は、この目標を達成するための手段の一つとして、各企業が簡易な自己診断を行い、経営幹部やDX部門、IT部門などの関係者間で認識を共有し、次のアクションにつなげるためのツールとなっています。
各社の自己診断結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が収集・分析することで、個社の診断結果と全体データとの比較ができるという特徴があります。
2-2. 「DX推進指標」を活用するメリット
DX推進指標は、あらかじめ用意されたフォーマットへ必要事項を記入し、専用サイトから送付するという簡単な手続きでデータを取得することができます。
これを利用することにより、
・DXへの取り組みに関する自己診断ができる
・IPAが作成するベンチマークとの比較により、全体における自社の位置づけがわかる
という2つのメリットが得られます。
そのため、DXへの取り組みを本格的に始めたいという方だけでなく、自社の位置づけが気になるという方にも、利用することをおすすめします。
2-3. 「DX推進指標」の自己診断方法の流れ
実際に企業が回答した内容について、自己分析を行う場合には、以下の手続きにしたがって、評価・分析を依頼します。
Step1:自己診断フォーマットの入手と記入
DX推進指標による自己診断を希望する企業は、以下のサイトから自己診断用のフォーマットをダウンロードし、所定の項目について回答内容を記入します。
https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html
Step2:自己診断結果のサイトへの入力
フォーマットの記載ができた企業は、以下の「DX推進ポータル」へログインし、フォーマットを提出します。
「DX推進ポータル ログイン画面」
https://DX-portal.ipa.go.jp/i/signin/top?d=%2Fu
具体的な操作画面の進め方等については、以下のサイトを参照ください。
「DX推進ポータル利用マニュアル」
https://filemanager.DX-portal.ipa.go.jp/public-documents/manual/Manual_DX%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf
なお、DX推進ポータルを利用する際には、gBizID(GビズID)アカウントが必要となりますので、アカウントをお持ちでない方は、事前に以下のサイトでアカウントを作成してください。
「gBizIDへようこそ」
https://gbiz-id.go.jp/top/
step3:ベンチマークの入手
サイト上から自己診断結果の提出が完了すると、IPAにより作成されたベンチマークをサイトからダウンロードすることができるようになります。
なお、ダウンロードできるベンチマークは、自社が自己診断結果を提出した年度のものに限られますのでご注意ください。
2-4. 「DX 推進ガイドライン」と「DX推進指標」の違い
2つのレポートはいずれも、「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」において提言された、企業が着手すべきロードマップを明示するためのツールとして作られたものです。
「DX 推進ガイドライン」は、DXへの取り組みのためのチェックシートとして、主に経営者向けに作られたもので、比較的簡易な内容となっているため短時間で読むことができます。
「DX推進指標」は、DX 推進ガイドラインで取り上げた課題をさらに充実させ、これらの項目について企業自らがポータルサイト上で自己診断ができるようになっています。経営者のみならずIT部門や技術者なども活用できる内容ですが、DX 推進ガイドラインよりはやや複雑な構成となっています。
2-5. 「DX推進指標」の具体的な活用方法
せっかく「DX推進指標」による自己診断をしたとしても、それを活かせなければ意味がありません。このデータや結果を実際の経営に活かす方法としては、次のようなものが考えられます。
●認識共有や啓発の材料として活用
DXについて、経営幹部や事業部門、IT 部門などの関係者が議論する場合のたたき台とすることで、お互いの認識の共有を図るための材料として活用できます。
●具体的なアクションにつなげるための材料として活用
自社の現状や課題の認識を共有した上で、「あるべき姿を目指すために、次に何をするべきか?」というアクションを起こすための材料とすることができます。
●進捗管理の材料として活用
自己診断は一回だけでなく、年ごとに行うことができ、そのデータを取得することもできます。
そのため、翌年度以降に再度診断を行い、計画の進捗を継続的に評価するための振り返りの材料として活用することができます。
2-6. 「DX推進指標」活用時のポイント
「DX推進指標」は、企業がDXへの取り組みを分析できる優れたツールですが、指標を作成する正しい意味を理解していなかったり、その意味を取り違えてしまったりすると、本来とは異なる使い方となってしまいます。
そのため、本指標の利用にあたっては、以下のようなポイントに留意してください。
●評価にこだわりすぎない
よい点数を取ることが、本指標作成の目的ではありません。企業が指標を活用して自己診断する過程を通じて、経営幹部を含めた関係者が議論をしながら現状や課題を適切に認識し、その認識を共有することが重要なポイントとなります。
●指標は結果のための目的ではなく手段
本指標は、ビジネスモデルそのものを評価するものではなく、企業の変化への対応力を可視化するためのツールです。あくまでもDXへの取り組みにより結果を出すための手段であり、これ自体が目的化されると本質からずれてしまうということに注意してください。
●経営者が自分のこととして認識する
経営者が IT システムを巡る問題をDXの取り組みに欠かせない自分の課題として認識し、必要なアクションにつなげる必要があります。
●指標は「2025年の崖」解決のためのツール
DX レポートで述べられている 「2025年の崖」を乗り越えるためには、デジタル競争に舵を切って、競争領域に資金・人材を大幅にシフトし、競争上の優位性を確保していくことが必要です。本指標は、正しいDXへの取り組みを行う上で、目標達成に欠かせない重要なツールとなります。
●コミュニケーションツールとしても活用が可能
本指標は、他企業や他の業界の取組状況を知るために利用できるだけでなく、取引先等とのコミュニケーションや課題解決の支援ツールとしても活用することができます。
2-7. 「DX推進ポータル」について
「DX推進ポータル」とは、DXを推進する申請手続き等の窓口となるサイトです。
このサイトを利用することで、DXに関するさまざまな申請が可能となります。
以下は、DX推進ポータルから利用できる代表的な3つのサービスです。
●「DX推進指標」の利用
企業がDXへの取り組みの現状について、自己診断を受ける際の窓口となります。
●「DX認定制度」の申込み
「DX認定制度」とは、DXへの取り組みが優良な企業について、国が審査の上で認定をする制度で、DX推進ポータルを通して申請を行うことができます。
●「DX銘柄」の登録等
「DX銘柄」とは、DXを推進するための仕組みを企業内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている上場企業を選定する制度であり、この登録手続きの申請を行うことができます。
3. 「DX推進指標」の構成と特徴について
3. 「DX推進指標」の構成と特徴について

3-1.「DX推進指標」の5つの特徴
「DX推進指標」には、次のような特徴があります。
(1)質問項目は「定性指標項目」と「定量指標項目」の2種類で構成されています。
(2)「定性指標」では、項目ごとに質問が設定されており、用意された回答の中からいずれかを選びます。また、項目はその重要度に応じて、以下の2 種類に区分されています。
- キークエスチョン: 経営者が自ら回答することが望ましい項目
- サブクエスチョン: 経営者が経営幹部、事業部門、DX部門等と議論をして回答する項目
(3)「定性指標」では、回答についてDX 推進の成熟度を6(0~5)段階で評価しています。
| 成熟度レベル | 詳細 | |
|---|---|---|
| レベル0 | 未着手 | 経営者は無関心か、関心があっても具体的な取組に至っていない |
| レベル1 | 一部での散発的実施 | 全社戦略が明確でない中、部門単位での試行・実施にとどまっている |
| レベル2 | 一部での戦略的実施 | 全社戦略に基づく一部の部門での推進 |
| レベル3 | 全社戦略に基づく部門横断的推進 | 全社戦略に基づく部門横断的推進 |
| レベル4 | 全社戦略に基づく持続的実施 | 定量的な指標などによる持続的な実施 |
| レベル5 | グローバル市場におけるデジタル企業 | デジタル企業として、グローバル競争を勝ち抜くことのできるレベル |
(4) 「定量指標」については、自社がDXによって伸ばそうと考えている指標を自ら設定した上で、一定期間後に目指す数値目標を立て、進捗管理を行っていくものとなっています。
(5) 本指標は、企業単位での回答だけでなく、多岐にわたる事業を展開している企業などについては、事業部門ごとに診断・回答することも可能となっています。
3-2. 各指標の主な項目
「DX推進指標」においては、定性と定量という2種類の指標を用い、それぞれの項目について回答した結果をベンチマークとしてフィードバックする仕組みをとっています。
●定性指標の項目について
定性指標は、主に以下の7つの項目について回答する形式です。
- (1) 「ビジョンの共有」
- (2) 「危機感とビジョン実現の必要性の共有」
- (3) 「経営トップのコミットメント」
- (4) 「マインドセット、企業文化」
- (5) 「推進・サポート体制」
- (6) 「人材育成・確保」
- (7) 「事業への落とし込み」
●定量指標の項目について
定量指標の項目では、事例を参考に、自社で一定期間後(例えば、3 年後)に達成を目指す指標を決めて数値目標を立て、その後、その数値について進捗管理を行っていく形式です。
なお、実際の作業では、以下の小分類部分の項目について目標を設定することとなりますが、実際に作成する項目は、ここにあげたものと同じである必要はありません。
(大分類)DX推進の取組状況
(中分類)DXによる競争⼒強化の到達度合い
(小分類) 研究&開発
マーケティング
調査・購買
会計・経理
(中分類)DXの取組状況
(小分類) デジタルサービス
デジタルプロジェクト
業務提携
デジタル化
(大分類)ITシステム構築の取組状況
(中分類)IT顧客管理基盤の構築
(小分類) 予算
人材
データ
スピード
3-3. 「ベンチマーキング」とは?
「ベンチマーキング」とは、自社のビジネスプロセスを改善するため、同じプロセスに関して優れた事例と比較分析をする手法です。
これにより、自社と他社の差を客観的に理解できるとともに、業界・業種、企業規模ごとに自社の位置づけを把握し、次にとるべきアクションへの理解を深めることができます。
活用する事で、以下のような改善点の確認ができます。
- 他社と比べると、自社ではDXへの取組みのスピードが遅れている。
- 他社よりも、新規ビジネスへの IT 投資の比率が少ない。
- 他社よりも経営幹部の関与が薄く、かつDX部門の役割が不明瞭になっている。
3-4. 「DX 推進における取締役会の実効性評価項目」について
DXを推進していく上では、現場関係者の取り組みだけでなく、経営の監督を担う取締役や取締役会が果たすべき役割も極めて大きいといえます。
そのため、DX推進指標の内容を踏まえ、取締役会での議論の活性化に役立てるという目的のもと、取締役会の実効性評価にも活用できるツールとして、「DX 推進における取締役会の実効性評価項目」が策定されています。
これを活用することにより、DXへの取り組みに関する議論のポイントが明確になるとともに、企業において取り組むべき課題の解決に役立てることができます。
「DX 推進における取締役会の実効性評価項目」は、以下の項目について回答する形式で作られています。
- 取締役の選任
- ビジョンの共有
- 危機感とビジョン実現の必要性の共有
- 経営トップのコミットメント
- DXに求められるマインドセット、企業文化
- 人材育成・確保
- 戦略とロードマップ
- IT システムに求められる要素
- IT システムの技術的負債
- IT 資産の仕分けとロードマップ
- ガバナンス・体制
- IT 投資の評価
- 経営陣の評価
- ステークホルダーへの情報開示
なお、こちらについては、DX推進指標のようなベンチマークの作成はされないことに注意してください。
4. DXの取り組み事例
DXの取り組みを行う上では、指標やベンチマークも重要ですが、実際の事例を参考にすることが、もっとも成功のイメージをつかみやすいといえます。
成功事例の中には、自社の取り組みに応用できるものや、開発のきっかけとなり得るものもあるでしょう。以下では、DXの取り組みに成功した企業の事例を紹介しますので、ぜひ自社の取り組みの参考としてお役立てください。
事例① デベロッパー
【商業施設における購買体験のDX】
都市部を中心に複数の商業施設を展開するデベロッパーでは、従来の店頭販売とECでの買い物を促すオムニチャネル機能を生かした商業施設における新しい購買体験を創出しました。利用者は各店舗や共用部のサイネージからEC在庫を選び、自身のスマホへ商品データを転送して買い物が可能となりました。また、一部店舗には、カメラで撮影した映像を表示することで、試着時に自分の後ろ姿を見ることができるシステムを導入するなど、購買体験をDXする取り組みを実施しています。
<取り組み成功のポイント>
- 基幹系システムを担う情報システム担当と、店舗のデジタル化を担うデジタル推進担当の統合
- ショッピングセンターが目指すべきDXの全体像を描いて社内で提示
事例② 食品メーカー
【最新鋭の次世代型スマートファクトリーの導入】
某食品メーカーでは、「Manufacturing Execution System (MES)」という製造実行システムを導入し、工場内のさまざまな作業を自動化。人が製造ラインに介在しないことでミスを起こさず、より安全な商品を提供できるとともに、製造ラインの人の数を減らすことで人材不足の問題についても解消しました。
<取り組み成功のポイント>
- 運用中心の「情報システム部」から、企画も担う「情報企画部」への体制の変革
- 中高年管理職へのIT啓発活動や、若手社員の外部からの採用などの人材推進活動
事例③ 物流企業
【ECエコシステムとデジタルプラットフォーム】
ある物流企業では、輸配送拠点を活用して法人や個人の配送パートナーがEC商品を配達する新たな配送サービスを一部地域で開始しました。業務システムを活用して、置き配やまとめ配達などにも対応しながらECラストマイルサービスの最適化を進めています。また、配達パートナーとの協業を進めるなど、組織体制も合わせて改革しており、DXの好例と言えるでしょう。
<取り組み成功のポイント>
- 社長直轄の社長室にデジタルイノベーション担当を設置
- 全社横断のシステムアーキテクチャーをフルクラウド化
まとめ
企業がDXへの取り組みを行っていく上で、はじめに直面するのが「どこから手をつければよいのだろう?」という問題です。これを間違えてしまうと、目標の達成ができないだけでなく、余分なコストや時間がかかってしまいます。
そのため、まずはDX推進ガイドラインを理解し、DX推進指標を活用して自社の位置づけを確認しましょう。これは、効率的なスタートを切るためだけでなく、確実に目標達成するためにも重要です。
具体的なDXへの取り組みは、企業それぞれで異なりますが、自社にあった方法を見つけるためにもこれらの資料をガイダンスとしてお役立てください。
この記事の目次
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK
サービスに関するご質問など
お気軽にお問い合わせください
資料ダウンロード
-
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK
サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください
サービス詳細情報は こちら



 JP
JP