ICT教育における6つの課題とその問題を解決する方法

公開日:2024/3/22
ICT教育は、簡単に説明すると教育のデジタル化であり、幅広いメリットを得られることから取り組む学校が増えています。
しかし、ICT教育を進めるには、PCやタブレット等のデジタルデバイスや、インターネット環境など、学習環境の整備が必須です。
実現に向けて準備を進める学校は増えていますが、幅広い課題があることから断念せざるを得ない学校もあるようです。
本記事では、ICT教育における6つの課題と、その問題を解決する方法まで詳しく解説するので、興味がある方はぜひチェックしてください。
ICT教育における6つの課題
ICT教育における課題は、大きく分けると6つあります。これから実現に向けて準備に取り掛かる学校は、ぜひ参考にしてください。
端末などにコストがかかる
1つ目の課題はコストです。
ICT教育を進めるにあたって最初の課題としてあげられるのが、デジタルデバイスの準備にかかるコストです。基本的には1人1台の端末を準備しないとICT教育を実現することは難しくなりますので、端末などにかかるコストの問題は課題と言えるでしょう。
実際に文部科学省が出す資料では、端末の整備状況について義務教育に関しては全自治体のうち既に99.9%が令和4年度内に整備が完了しているため問題ないと言えます。
しかし、公立高校においては、各都道府県の高校でほとんど整備されているものの、費用は学校等が負担するケースもあれば保護者が負担している学校もあります。
そのため、自費で準備することに対する不満や意見を持つ保護者が一定数は出てくる可能性があるので、先生の心理的負担が大きくならないよう、対策を考える必要があるでしょう。
通信機器を準備する必要がある
2つ目の課題は通信機器です。
ICT教育の実現には、端末だけではなく通信機器の準備も必要です。学校で全生徒が使用するとなると、家庭用の通信設備では物足りません。
全生徒が快適にデジタルデバイスを使用できるようにするには、高速かつ大容量の通信ネットワークが必須です。
しかし、学校内ではこれらのスキルを持つ技術者がいないケースもあるため、人材確保等も検討しなければなりません。人材確保は容易なことではありませんし、特に予算が限られている場合には大きな課題となるでしょう。
端末の管理が複雑になる
3つ目の課題は、端末の管理が複雑になる点です。
ICT教育を進めるにあたって、端末の管理は課題と言えそうです。大きく分けると学校側でデバイスを厳重に管理する方法と、生徒に管理を任せる2つの方法があります。
学校で管理をする場合、端末の損傷等を防ぐことが可能になりますが、生徒からすると使いづらく感じてしまうため、スキルを向上させる面では課題が残ります。
一方、生徒に管理を任せると、自由に使えるため日常的に学習スキルを向上させることが可能です。しかし、破損リスクやセキュリティの問題、忘れるリスク等の課題があるため、最適な管理方法を学校側で考える必要があります。
先生の負担が大きくなる
4つ目の課題は先生の負担が大きくなることです。
先生の仕事は授業だけではありません。授業の準備や生徒個別の悩み事への対応、保護者とのコミュニケーション、学校行事など他にも幅広い仕事があります。
それらの仕事に加えてICT教育のための準備にも時間を使わなければならないため、膨大な仕事量になることが予想されます。
ICT教育を成功させるためには、学校側が先生の負担を大きくしないよう対策をしなければなりません。
創造力や読み書き能力の低下が懸念される
5つ目の課題は、生徒の想像力や読み書き能力の低下が懸念されることです。
ICT教育においては画面を見る機会が増えます。本を読んだり、手で書いたりする学習は、自分で情報を整理したり、想像したりする機会が多くなりますが、画面を見るだけやクリック一つで回答を得られたりすると、考える過程がおろそかになる可能性があります。
その中でも書く機会が減ってしまうと、書く力自体が低下するリスクもあるため、すべてをデジタルデバイスで学習するのは課題が残ります。
ICT教育によって逆効果とならないように、バランスを考えるなど対策が必要です。
セキュリティに対して十分に配慮する必要がある
6つ目の課題は、個人情報の流出や有害サイトへのアクセスなどセキュリティ面の不安です。
インターネット環境を活用することで幅広い知識を調べることが可能ですが、間違った使い方をすると個人情報が流出する可能性もあるなど、さまざまなリスクが存在します。
特にルールを決めていない場合には重大なトラブルが発生するリスクがあるため、セキュリティに対しては十分に配慮して対策する必要があります。
ICT教育の課題を解決するための方法
ICT教育には幅広いメリットがある反面、いくつかの課題も残されています。ここからは、ICT教育における課題を解決する方法について紹介するので、参考にしてください。
一部の業務を委託する
1つ目は一部の業務を委託することです。
通信設備や端末管理等、ICT教育を進めるにあたって学校側が身につけなければならないスキルはたくさんあります。しかし、これらの専門知識を一から身に着けることは非効率的であり、学校側や先生の負担も増えてしまいます。
この課題の解決策としては、文部科学省がICT教育環境整備のために支援を行うGIGAスクールサポーターの活用がおすすめです。GIGAスクールサポーターは、ICT化を支援する人材確保のサポートや、端末管理や教員への事前研修、予算確保のための方策提案等を行っているので、積極的に活用することで課題を解決できます。
アナログとデジタルのバランスを保つ
2つ目はアナログとデジタルのバランスを保つことです。
ICT教育の懸念点としてあげられている生徒の想像力や読み書き能力の低下については、手書きの時間をあえて作ったり、デジタルツールを活用して図形を作成したりするなどアナログとデジタルのバランスを保つことで、想像力や読み書きの能力は低下しづらくなります。
また、ディスカッションを増やして話す時間も増やすことも、考えをまとめたり、新しいアイデアを出したりする際に役立つので、完全にデジタル任せではなく、バランスの取れた学習を取り入れることが大切です。
ICT教育は、取り組み方次第で想像力や読み書きの能力を低下させることなく、むしろそれらを伸ばす手助けとしても役立つので、実施する際にはどのような授業にするのか入念に準備を進めましょう。
生徒へネットリテラシー教育を行う
3つ目は、生徒へのネットリテラシー教育を行うことです。
具体的にはネットリテラシーを学ぶだけの授業を実施したり、授業以外での活用方法やルールを事前に決めたりすることが大切です。
学校側で最低限のルールや制限をかけるだけで、ネット環境にあるさまざまなリスクを回避できる可能性が高まります。
学校側や先生に専門知識がない場合は、外部の専門家を招いて講義をしてもらったり、ルールを決めるにあたってのサポートをお願いしたりするのもおすすめです。
まとめ
今回は、ICT教育における課題や、問題を解決するための方法について紹介しました。ICT教育には幅広いメリットがある反面、学校によって感じる課題も数多くあります。よくある課題は今回紹介したように解決策がありますので、参考にしながらICT教育を取り入れてみてください。
NTTコミュニケーションズでは、学生証をデジタル化するSmart Me®を提供しています。デジタルデバイスの導入が進む学校が増える中、学生証もデジタル化にしたいと考えている学校は、Smart Me®の導入をご検討ください。
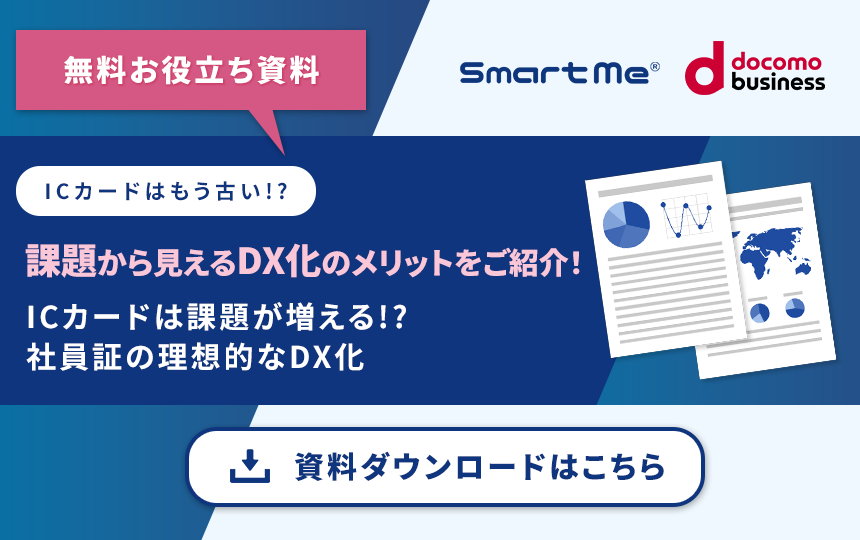




 JP
JP















