文部科学省が掲げるICT教育の概要や目的、現状について徹底解説

公開日:2024/3/22
ICT教育は、情報化社会の進展とともに注目されるようになりました。インターネットやデジタルデバイスを活用することで、これまでにない学習方法を実現できるようになりましたし、教室外のオンラインでも学べる機会を得られるようになったのです。
幅広いメリットがあることから多くの学校でICT教育が取り入れられるようになっていますが、中にはどのように始めたらいいかわからない学校もあります。
本記事では、ICT教育の実施を検討している学校向けに、文部科学省が掲げるICT教育の概要や目的、現状について解説します。これからICT教育を取り入れるにあたってのヒントにもなるので、ぜひ参考にしてください。
文部科学省が掲げるICT教育とは?
近年、インターネットの急速な普及により、新しい価値やサービスが生まれるようになりました。人々の生活はより豊かなものとなりましたが、 今後起こりうる問題としては、予測できない変化により、今の教育が通用しなくなることや、人工知能等の進化により、人々の職業が奪われるのではないかといった不安の声があがっていることです。
このような背景もあり、文部科学省では子どもたちが将来必要になるスキルを身に着けられるようICT教育を実施する流れとなりました。
文部科学省が掲げるICT教育とは、「情報活用能力の育成」であり、下記3つの項目があります。それぞれ解説するので参考にしてください。
情報活用の実践力
情報活用の実践力の内容は、下記3つの内容があげられます。
- 課題や目的に応じた情報手段の適切な活用
- 必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造
- 受け手の状況などを踏まえた発信・伝達
上記の内容は、具体例としてあげると、文字入力やインターネットなどの情報手段の適切な活用等、ICT教育に必要な基礎的な内容となっています。
情報の科学的な理解
次に情報の科学的な理解については、下記2つの内容があげられます。
- 情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解
- 情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善したりするための基礎的な理論や方法の理解
上記は簡単に説明するとプログラミングがあげられます。例えば、自分が意図する形を実現するためにコードで表現する力を、ICT教育を通して学びます。現在では小学校においてプログラミング学習がありますが、それも文部科学省の設定する「情報の科学的な理解」となります。
情報社会に参画する態度
最後に情報社会に参画する態度は、下記3つの項目があげられます。
- 社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解
- 情報モラルの必要性や情報に対する責任
- 望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度
上記は、情報発信による他人や社会への影響、危険回避等を学ぶICT教育です。具体例としては、SNS等での情報共有が他人に与える影響を考え、偽情報の拡散を避けるために情報の真偽を確認するスキルや、プライバシー保護のために自分の個人情報を安全に管理する方法などがあげられます。
文部科学省が推進するICT教育の目的とは?
文部科学省が推奨するICT教育には、さまざまな目的があります。具体的には下記項目の実現を目指しているので、参考にしてください。
学習の効率化
1つ目のICT教育の目的は、学習の効率化です。
ICT教育を実現することで、参考になる資料などを、インターネットを活用して簡単に収集できるようになります。生徒は調べるために本を探したり、毎回先生に聞かなくても自分で調べられたりするため、アナログに比べて効率的です。
また、オンライン授業にも対応することによって、生徒は好きなときに好きな場所で勉強ができます。わからないことがあってもその場で調べることが可能なので、効率的な学習が実現できるようになります。
わかりやすい授業
2つ目の目的は、わかりやすい授業の実現です。
ICT教育は、情報技術を活用して教育の質を高めることにあります。デジタルデバイスやインターネット環境を活用することで、生徒一人ひとりの能力に合わせた学習環境を用意できるため、わかりやすい授業の実現が可能になります。
情報活用能力の向上
3つ目の目的は、情報活用能力の向上です。
情報能力の向上とは、インターネットやコンピュータを活用して情報を探し、その情報が本当かどうか考えたり、自分の考えを人に伝えたりする能力のことです。
今の世の中は世界中でさまざまな情報が飛び交っているため、情報活用能力の向上がICT教育では必要不可欠となります。
学校における情報活用能力の向上は、例えば学校の宿題で何かを調べる際、どの情報が役に立つかを選ぶ力や、自分の言葉でまとめられるようにすることが目的です。これらの力を身に着けられれば、より情報を上手く活用し、学習や日常生活に役立てられます。
教員の業務効率化や負担軽減
4つ目の目的は、教員の業務効率化や負担軽減です。
教員は多忙な職種としても知られており、授業のみならず授業の準備から成績管理、生徒や保護者とのコミュニケーションなど幅広い仕事を任されています。
このような負担を少しでも軽減できるよう、ICT教育では生徒だけではなく教員の業務効率化や負担軽減も目的として含まれているのです。
ICT教育ではデジタル技術を活用するため、例えばオンラインのプラットフォームを利用することで授業資料を簡単に共有できたり、メールやオンライン掲示板を活用することで連絡事項を効率的に行えたりします。アナログに比べて業務を効率よく進められますし、負担軽減にもつながります。
ICT教育の現状について
ここまで文部科学省が推奨するICT教育の概要や目的について紹介しましたが、現状はどのような結果となっているのでしょうか。ここからは文部科学省の「学校におけるICT環境の整備状況等」の資料を参考に、ICT教育の現状を紹介します。
教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数
ICT環境の整備状況等については、令和2年3月までは1台当たり4.9人なのに対し、令和4年3月までには1台当たり0.9人まで上昇しています。平均値で0.9人といった数値が出ているため、ほとんどの学校ではICT環境の整備が進んでいると言えます。
実際に全国の児童生徒数が11,319,053人(令和4年度)に対し、教育用コンピュータ台数は12,359,187台(令和4年度)と児童生徒数を超えています。
インターネット接続率
インターネット接続率は、30Mbps以上で整備している学校が99.4%(令和4年度)、100Mbps以上で整備している学校が96.6%(令和4年度)と高い数値が出ています。
インターネット接続率は平均値となりますので、現状はほとんどの都道府県の学校でICT環境の整備が進んでいることがわかります。
教員のICT活用指導力の状況
教員のICT活用指導力の状況においては、現状でも高い数値が出ています。
特に「教材研究・指導の準備・評価・校務などにICTを活用する能力」では、全国の平均値が87.5%(令和4年度)とほとんどの都道府県の学校でICTを活用した教育を実施できています。
その他にも「授業にICTを活用して指導する能力」では、全国の平均値が令和3年度は70.2%だったのに対し、令和4年度では75.3%と約5%も上昇しています。
このようなデータをチェックしてもわかるように、ほとんどの学校でICT教育の環境が整備され、実施されていることがわかります。
まとめ
今回は、文部科学省が掲げるICT教育の概要や目的、現状についてまとめた内容を紹介しました。ICT教育は多くの学校で取り入れられ、なくてはならない教育にもなりつつあるので、まだ整備が進められていない学校は、積極的に準備を進めましょう。
NTTコミュニケーションズでは、学生証をデジタル化するSmart Me®を提供しています。紙やカードで発行されている学生証のデジタル化を希望されている学校は、ぜひSmart Me®の活用をご検討ください。
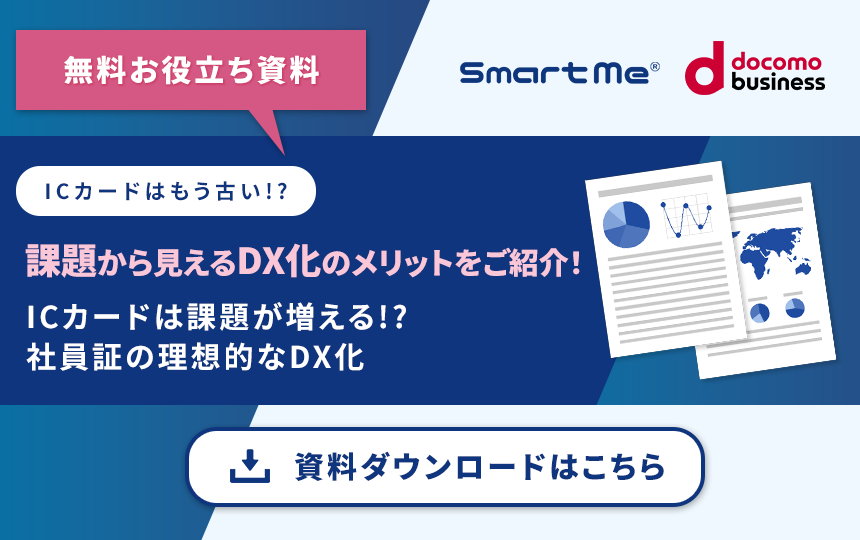




 JP
JP















