教育DXとは? DX化が推奨される理由や課題、効率的に進める方法についてご紹介

公開日:2024/3/22
幅広い業界でDX化が進められている中、教育現場においてもDX化が推奨されています。インターネットやデジタルデバイスを活用した教育が当たり前のようになっていますが、そもそも教育DXの目的とはどのようなことがあげられるのでしょうか。
また、教育DXをスムーズに取り入れるためには、目的や進めるうえでの課題も把握しておくことが大切です。
本記事では、教育DXの概要から推奨されている理由や課題、効率的に進めるための具体的な方法について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
教育DXとは
教育DXとは、教育現場において、データおよびデジタルツールを活用することで、教育方法や手段、教職員の業務などを変革することです。これは、ただ単にデジタル化へ置き換えるのではなく、変革させることが必要不可欠な要素となっています。
文部科学省では、教育DXの推奨において下記3つの取り組みを進めています。
- 教育データの意味や定義を揃える「標準化」
- 基盤的ツールの整備
- 教育データの分析・利活用の推進や、教育データ利活用にあたり自治体等が留意すべき点の整理
教育データの意味や定義を揃える「標準化」
文部科学省の教育DXの取り組みの一つにある「教育データの標準化」とは、教育に関連するデータが持つ意味や定義を統一するためのルールのことです。
これにより、異なる教育機関やプログラム間でデータを比較しやすくし、共有や利用がしやすくなります。例えば、学生の成績や出席情報などを標準的な形式で記録できれば、全国どこでも同じ基準でデータを解析し、適切な教育施策を立てることが可能になるのです。
基盤的ツールの整備
教育DXの取り組みに含まれる「基盤的ツールの整備」とは、教育DXの一環として、学校や教育機関で活用する基本的なデジタルツールやプラットフォームを整えることを指しています。
具体的に文部科学省では、全ての教育機関で活用できるツールの「文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)」と「文部科学省WEB調査システム(EduSurvey:エデュサーベイ)」の整備が進められています。
これらの基盤的なツールの整備を進めることで、教育の質の向上や効率化を図ることが期待されており、教員や生徒たちはより効果的かつ柔軟に学習活動を行えるようになります。
教育データの分析・利活用の推進や、教育データ利活用にあたり自治体等が留意すべき点の整理
最後に「教育データの分析・利活用の推進や、教育データ利活用にあたり自治体等が留意すべき点の整理」とは、教育に関するデータを収集し、そのデータを分析して教育の質を向上させる方法を模索することです。
また、データを利用する際には、プライバシーの保護やセキュリティ対策など、各自治体や教育機関が守るべきルールや注意点を明確にすることも含まれています。
教育DXが推奨されている理由
教育現場のDX化は、そもそもなぜ推奨されるようになったのでしょうか。ここでは推奨されている2つの理由を紹介します。
教育の質の向上が期待できるから
教育DXが進むことで、さまざまなデジタルツールを活用した学習が可能になります。例えばパソコンやタブレットを活用した学習では、各生徒が理解しやすいように教材を調整することができ、一人ひとりの進み具合を確認しながらその生徒に合った課題を出したり、難易度を変えたりすることが可能です。
これにより、従来の教育スタイルと比べて自分のペースで学習しやすくなるため、学習効果が高まります。個々のニーズに合わせて教えられることで、今まで以上に学習の質を向上させられることが期待できるため、教育DXは推奨されています。
あらゆるリスクにも対応しやすくなるから
新型コロナウイルスの感染拡大では、あらゆる学校が休校になり、学校にいけない状況が続きました。その他にもインフルエンザによって、学校が休校になるケースも少なくありません。
こうした感染症などあらゆる問題が発生しても生徒たちに学習環境を提供できるよう、教育DXが必要不可欠とされています。
全ての学校で整備が進めば、遠隔地でも授業を行うことが可能になり、学習の遅れなどを防ぐことができるのです。
教育DXの課題
ここまで教育DXの概要から推奨される理由まで紹介しました。教育DXが整備されることで幅広いメリットがありますが、一方で課題もいくつかあげられます。ここでは教育DXの課題についてまとめましたので参考にしてください。
インフラの構築と整備
1つ目の課題は、インフラの構築と整備です。教育のDX化を全ての学校で整備するためには、基盤となる技術や設備が必要不可欠となります。
具体的には高速インターネットの整備や、生徒へ必要になるデバイスの配布、これらを維持するためのコストも必要です。必ずしも資金に余裕がある学校ばかりではないため、インフラの構築と整備は、教育DXを進めるうえでの課題となります。
教員の知識不足や経験不足
2つ目の課題は、教員の知識不足や経験不足です。デジタルツールを導入したり、それらを効果的に活用したりするためには、教員がこれらの技術に精通している必要があります。
しかし、多くの教員はデジタルツールの使い方や、それを有効に活用する方法についての講習等を受けていないケースも多く、教育DXの推進を妨げる要因となっています。
教員の知識不足や経験不足のまま取り組んでも上手く活用できないケースが多くなるため、成功させるためには教員への研修やサポートは必要不可欠です。
セキュリティ
3つ目の課題は、セキュリティの問題です。教育機関で取り扱うデータ等は、多くが個人情報を含む機密性の高い情報です。もし情報漏洩などによって外部に流出してしまったら、大きな問題へと発展してしまうリスクがあるので注意が必要になります。
セキュリティに関する知識は、学校側で対応することが難しいケースもあるため、専門知識を持つ外部の機関に依頼 をするなどの対策が、教育DXを進めるためには必要になるでしょう。
教育DXを効率的に進める方法
教育DXを効率的に進めるためには、文部科学省の資料等を活用することで、何から実施すればいいのかなどが具体的に把握できます。どのように手を付けたらいいかわからない場合は、参考にしながら進めましょう。
また、教育DXに向けて便利なツールやアプリ等の導入を検討されている学校も多いかと思いますが、できる限り統合することをおすすめします。その理由としては、さまざまなプラットフォームを導入してしまうことで、教員は複数のツール間で切り替えなければならないなど、混乱が生じる恐れもあります。
情報やデータはできる限り一元管理できるものを選ぶことで、管理や操作がしやすくなります。全ての情報が一つに集約されることで使いやすくなるだけではなく、全体の生産性も向上するので、効率的に教育DXを進めるためにも混乱が起きないようなツールの選定を検討してください。
まとめ
今回は、教育DXの概要を中心に紹介しました。推奨されている理由は幅広くあり、特に教育の質の向上や、あらゆるリスクにも強くなるメリットがあげられます。一方で、インフラの構築と整備や教員の知識不足、セキュリティの問題が課題としてあげられているため、その対策は必要になります。しっかりと対策をすることで今までにない革新的な教育の実現ができるので、教育DXの導入に向けて準備を進めている学校は、今回紹介した内容も参考にしながら進めてみてください。
NTTコミュニケーションズでは、学生証をデジタル化するSmart Me®を提供しています。紙の学生証をデジタル化したいと考えている学校は、ぜひ導入をご検討ください。
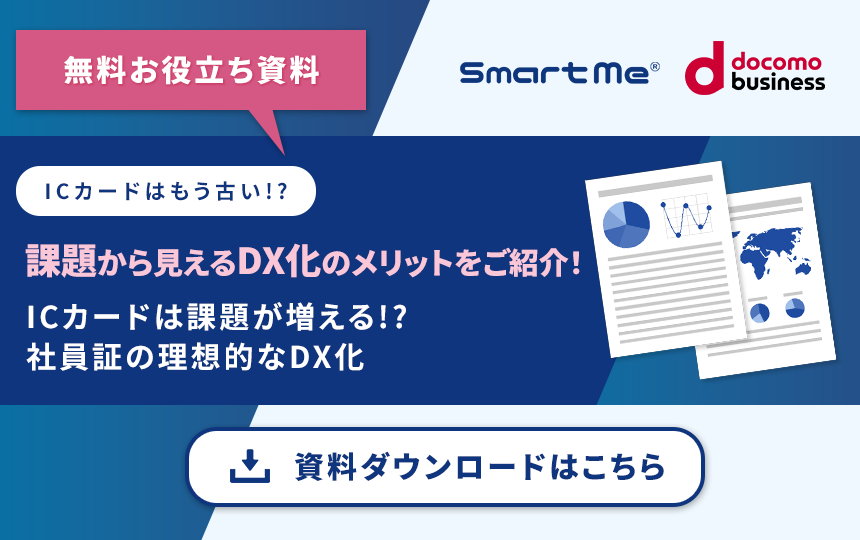




 JP
JP















