文部科学省が推進している教育DXとは?詳しく解説!

公開日:2024/5/30
教育の現場ではDXが求められるようになりましたが、その背景にはデジタル化社会への対応があげられます。また、その他にも文部科学省が教育DXを推進していることや、リモート授業の必要性が高まっているのもDXが求められるようになった背景と言えます。
実際に教育DXを進める学校は増えており、デジタルデバイスを活用した授業などが積極的に行われています。
本記事では、教育DXの実現に向けて取り組む学校向けに、教育DXの概要から文部科学省が推奨している教育DX推奨プランについて詳しく紹介しますので、特に本来の教育DXの進め方がわからない方は、ぜひ参考にしてください。
教育DXとは?
教育DXとは、教育分野でのデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めることを指しています。教育DXは、単に新しい技術を使うだけではなく、教育の方法や指導自体を改革することです。
例えば、紙の教科書の代わりにタブレット端末を活用することで、その日に必要な教科書を学校に持ち込む手間が省けますし、編集も簡単になるので内容の更新も随時行うことができるようになるのです。
さらに、動画や音声などを積極的に活用することで、より理解しやすい教材を作ることが可能になり、これまでのスタイルにはなかった授業を実施できるようになります。
その他にも、オンラインプラットフォームを活用することで、生徒一人ひとりの学習状況をリアルタイムで確認し、必要に応じて生徒のサポートができるようになります。教育DXは、生徒一人ひとりの学習状況の見える化も可能になるため、全ての生徒が平等に学べるようになるのです。
教育のデジタル化との違い
教育DX=教育のデジタル化と思われている方も多いかと思いますが、両者は似ているようで異なる意味を持っています。
教育のデジタル化は、ITツールやICT機器、システムなどの導入を指しています。具体的には学校にパソコンやタブレット端末を配布することや、電子黒板などがあげられます。しかし、これらのツールを導入するだけで、使い方や教育の方法が変わらなければ、それは単なるデジタル化のみとなります。
一方、教育DXはデジタル技術を活用して教育そのものを改革することです。単にパソコンやタブレット端末を導入して今までと同じ授業スタイルで行うのではなく、例えばオンラインで宿題を提出できるようになることや、テストの自動採点、先生が学習の進捗状況をリアルタイムで確認できるなど、今までなら実現できなかった授業や学習プランを提供することが教育DXです。
教育DXを実現できれば、今までよりも効果的で効率的な教育ができるようになるため、単にデジタル化だけでとどまっている場合は、教育モデルや指導方法などを見直していくことが必要です。
文部科学省が推進している教育DXとは?
教育機関が教育DXを進めるにあたっては、文部科学省において教育DX推進プランを出しています。そちらに沿って進めることで、基本的なガイドラインのような役割があり、より進めやすくなるので事前にチェックしておくことをおすすめします。
この見出しでは具体的に文部科学省が推進している教育DXの内容について紹介していますので、参考にしてください。
➀教育データの意味や定義を揃える「標準化」(ルール)
文部科学省が取り組む1つ目の内容としては、教育データの標準化です。
教育データの標準化は、文部科学省の資料では「教育データをデータの種類や単位がサービス提供者や使用者ごとに異なるのではなく、相互に交換、蓄積、分析が可能となるように収集するデータの意味を揃えること」と記載されています。
こちらについて簡単に説明すると、教育に関するデータを集める際、全ての学校が同じ意味やルールでデータを扱うことを意味しています。なぜ、教育データの標準化が必要になるのかというと、それぞれの学校で独自のデータ収集を行っても、統一がされていないと活用することができないからです。
データを集めても使えないとならないように、文部科学省は教育DXの取り組みの一つとして、教育データの標準化を重視しています。これから教育DXを進める学校は、文部科学省の教育データの標準化を参考にすることで教育DXを進めやすくなるので、取り組む前に必ずチェックしておきましょう。
➁基盤的ツール(MEXCBT、EduSurvey)の整備(ツール)
文部科学省が取り組む2つ目の内容は、基盤的ツールであるMEXCBTとEduSurveyの整備です。
そもそもMEXCBTとは、生徒が学校や家庭において、国や地方自治体等の公的機関が作成した問題を活用し、オンライン上で学習やアセスメントができる公的CBTプラットフォームです。
MEXCBTは、GIGAスクール構想により、児童生徒1人1台端末環境が整備されたことを踏まえ、開発が進められました。令和3年12月から希望する全国の小・中・高校で活用がスタートし、令和6年2月までで約2.7万校、約850万人に登録されています。
2つ目のツールであるEduSurveyは、文部科学省のWEB調査システムのことです。これまではエクセルを使ったアンケート調査を実施しており、複雑な集計作業を行っていた事実があります。しかし、EduSurveyがあれば、クラウド上に回答を保存することで、各自治体の集約の手間を省けます。学校の調査業務負担の軽減につながっており、教育DXにはなくてはならないツールとなっています。
教育DXに取り組むためには幅広いツールが必要になりますが、その中でもMEXCBTとEduSurveyは重要な役割がありますので、まだ導入していない学校は文部科学省の資料を事前にチェックしてみてください。
➂教育データの分析・利活用の推進や、教育データ利活用にあたり自治体等が留意すべき点の整理(利活用)
文部科学省では3つ目の内容として、教育データの分析・利活用の推進や、教育データ利活用にあたって注意すべき点についても記載されています。
教育DXを進めるにあたっては環境の整備などに集中しがちですが、デジタルデータを扱うことから、今まで以上に必要な対策から安全管理措置を行う必要があります。
具体的に文部科学省では、教育DXを進めるにあたって、教育データを安全・安心に取り合うためのセキュリティ対策や、個人情報の保有・取得に関するルール、個人情報の利用・提供に関するルールなどが記載されています。
これらの内容は、教育DXを進めるにあたって必ずチェックする必要があり、対策やルールは文部科学省が紹介している内容に沿って進めなければなりません。
対策をしていないと個人情報の流出などさまざまなリスクがありますので、注意点を守りながら進めましょう。
まとめ
今回は、教育DXの概要から、文部科学省が推奨する教育DXの内容について詳しく紹介しました。教育DXに関する取り組みは数多くの学校で進められていますが、中には教育のデジタル化にとどまり、デジタル技術を活用して教育そのものを改革できていない学校も多くあります。教育DXの正しい進め方についてわからない場合は、文部科学省が紹介している資料等もございますので、それらを参考にしながら進めることで取り組みやすくなるので、今回紹介した内容も参考にしながら具体的な準備から対策まで行ってみてください。
NTTコミュニケーションズでは、学生証をデジタル化するSmart Me®を提供しています。さまざまなもののデジタル化が進むにつれて、紙の学生証をデジタル化したいと考えている学校は、ぜひ導入をご検討ください。
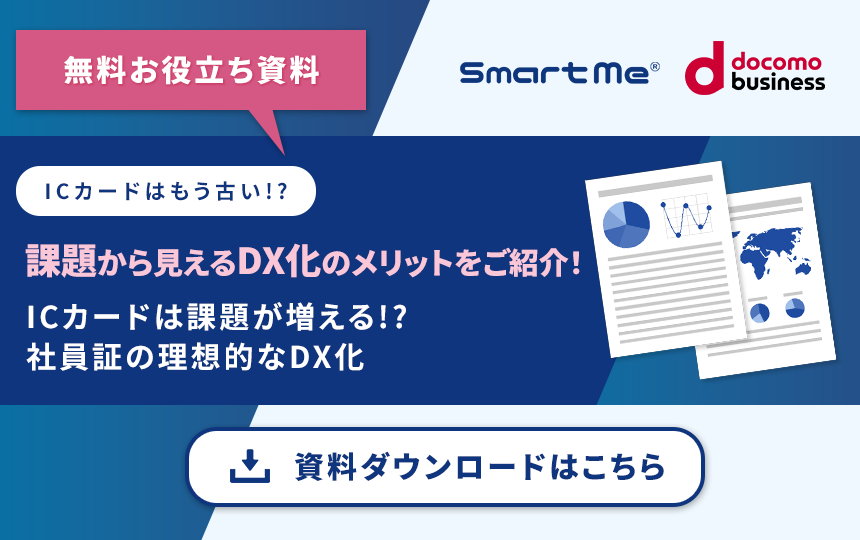




 JP
JP















