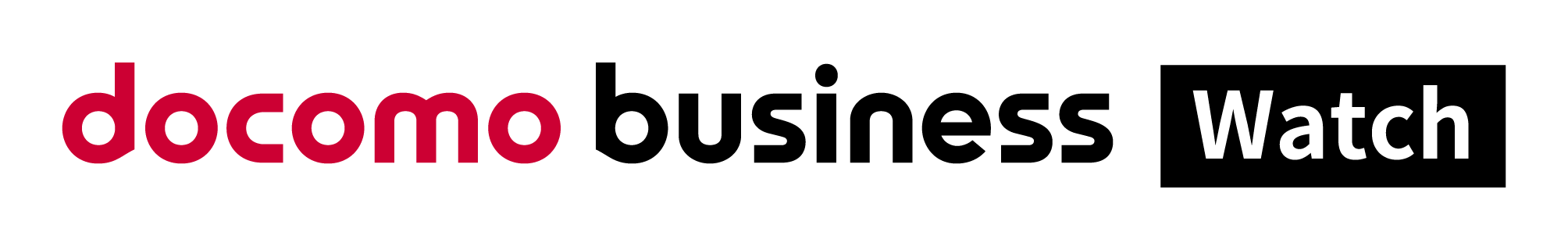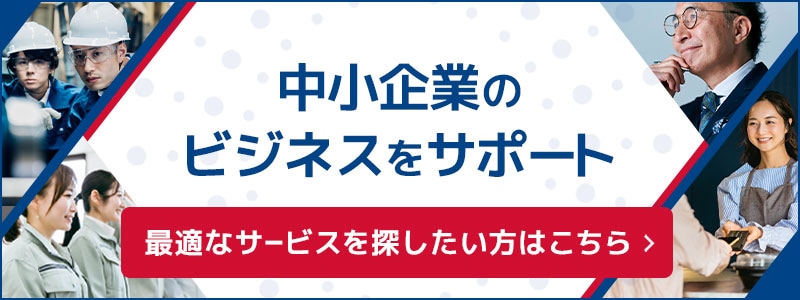元々は台帳や伝票も手書きの町工場だった

東京都足立区に本社を構える今野製作所は、板金加工、機械修理、油圧機器製造などをメイン業務とするものづくり企業です。
従業員数は39人(2021年11月現在)という中小企業ですが、2016年には経済産業省主催の「攻めのIT経営中小企業百選2016」に選定されています。これはITやデジタルの活用に積極的に取り組み成果を上げた中小企業を同省が認定するというもので、同省が現在公開している、製造業におけるDXの事例をまとめた資料「製造業DX取組事例集」にも掲載されています。
しかし代表取締役の今野浩好氏は、以前はいかにも"町工場"といえるような、デジタルとは程遠い職場環境だったと振り返ります。
「私が入社した1996年当時の今野製作所は、台帳や伝票は手書きで、月間の売り上げがいくらかを把握するのに、会計事務所から3カ月後に送られてくる試算表を待たねばなりませんでした。入社後は、販売管理パッケージや会計システムなどを導入し、本社から離れた工場で勤務する従業員との情報共有のためにグループウェアを導入するなど、その時々に必要なITを導入するようになりました」
2000年前後から地道なIT化を進めてきた今野製作所が、本格的なDXに取り組むきっかけとなったのが、2008年のリーマンショックでした。
リーマンショック後の今野製作所の売上は、対前年4割以上も落ち込んでしまい、経営の危機に陥っていました。同社はこの危機を打開するため、主力商品である油圧機器の特注品製作に注力する方針を打ち立てることにします。この結果、受注は増えたものの、別の問題も生まれてしまったといいます。
「特注品の製作は、仕事が複雑になりますし、営業から設計への情報伝達はこれまで以上に精度が求められるため、既製品と比べても手間暇がかかります。そのため、全体で見れば仕事は減っているにもかかわらず、現場は混乱し、営業と設計は毎晩遅くまで残業している状況に陥ってしまいました」(今野氏)
「人」に依存した業務プロセスは混乱を生む
混乱するばかりの職場環境を変えるために、今野製作所は2010年に、業務の1つ1つの流れを検証し、改善していくプロジェクト「業務見える化プロジェクト」をスタート。専門家の指導を受けて、丸1年がかりで取り組みました。
このプロジェクトの結果、今野製作所では多くの業務プロセスにおいて、「人」に依存した構造になっていたことが判明しました。
例えば、購買機能を担う部署がない同社では、外注手配や部品手配の業務も、設計担当者や営業担当者がケース・バイ・ケースで、"自分の当然の業務"と認識して行っていました。このように仕事が一連の業務機能の流れ(プロセス)として認識されていない状態では、何かトラブルが起きたときには、担当者の問題、人の問題になりがちです。リーマンショック後に生じた社内の混乱も、従来の業務プロセスを放置していたことが原因であることがわかりました。
「当時は業績が低迷しており、コンサル料を支払える状況ではありませんでした。コンサルタントの勉強会の題材に当社の業務事例としての使用してもらう条件で、実質的に無償で協力してもらえました」(今野氏)
なぜ今野製作所は業務に必要なシステムを内製できたのか
人に依存した業務プロセスを見直すために、今野製作所は社内の業務をすべてITで連携する取り組みを開始。具体的な施策としては、お問い合わせから受注までの情報共有と技術提案仕様書の作成における業務を管理することを目的に、サイボウズ社が開発した業務改善プラットフォーム「Kintone(キントーン)」を導入しました。
「Kintoneは、プログラム開発言語を使わない"ノンコーディング"でアプリケーションの開発ができるクラウドサービスです。Kintoneを使うことで、業務の流れと進捗を可視化して共有できるようになり、業務の手戻りも防げるようになり、受注までのリードタイムが短縮できました。従業員同士でデータがつながることで、まるでサッカーでパスを回すように、チーム力を発揮できるようになりました」(今野氏)
さらに、生産業務の基幹となるシステム開発にも着手しました。今野氏は以前より、受注→発注→生産に至るまでの状況が把握できる生産管理システムの必要性を感じていましたが、実現には至りませんでした。というのも、同社は製造工程の異なる事業を複数行っているため、見込生産(MTS)、受注組立生産(BTO)、繰返受注生産(MTO)、受注設計生産(ETO)など複数の生産方式が存在しており、それらに対応するシステムの構築が困難でした。
しかし同社は、なんと自社開発で生産管理システムを作り上げてしまいます。
「当時親交があったインダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ ※ の西岡先生(法政大学 デザイン工学部 西岡靖之教授)のアドバイスを受け、ノンコーディング開発ができる『Contexer』というツールを導入しました。データベースの設計については有償で専門家に作成を依頼しましたが、それ以外は自社で構築しました。
その結果、受注・出荷、調達、生産などの一連の業務をシステム化に成功しています。現在も使用しており、追加のシステム開発も社内の人材だけで行うことができています」(今野氏)
※一般社団法人 インダストリアルバリューチェーンイニシアティブ…ものづくりとICTを融合した業務改革について企業の枠を超えて取り組む企業のためのフォーラム。法政大学 デザイン工学部 西岡靖之教授が理事長を務める。
DXに高スキル人材はいらない?
このように従業員自らの手でシステム化を推進してきた今野製作所ですが、IT人材については、特に社外から採用することはなかったといいます。
「当社では幸運なことに、現場から適性のある人材を発掘して専任者にできました。しかし、人手不足やコストの面から、なかなか中小企業ではIT人材を採用するのは難しいでしょう」(今野氏)
一方で今野氏は、高スキル人材を採用しなくても、DX化は可能であると指摘します。
「高スキル人材が採用できなくても、従業員全体のITスキルを底上げするだけで、できることの範囲は少しずつ広がってくると感じています。当社でも全社員の2割くらいがシステムの基本的なことを理解し始めた頃から、できることが目に見えて増えていきました」(今野氏)
今野氏はさらに、新たなITシステムを作る際には、他社に依頼するのではなく自社で作り上げた方がメリットは大きいとも話します。
「外注は依頼側の手間が少ない点はメリットではありますが、一方で導入後にフィットしない場合は、大きな損失になってしまいます。その点、自社でノーコーディングのツールを使って開発すれば、トライ&エラーを繰り返すことで組織にフィットするシステムが作れます。現場にとって使いやすくて便利なアプリケーションであれば、外注したものであれ、内製したものであれ、絶対に使われます。
ただしアプリケーションの設計については、専門家の力を借りて慎重に作っておくべきです。当社の場合も、事前に業務プロセスを専門家と綿密に話し合っていたことが功を奏したと感じています」(今野氏)
「中小企業こそDXは進みやすい」
今野製作所では現在も従業員自身によるノンコーディングのアプリケーション開発を行っており、2020年からはコロナ禍対策として工場のライブ配信による営業活動、IoTでのデータ収集による溶接技能の伝承など、デジタルを活用した新たな取り組みを進めているといいます。今野氏はこれまでの取り組みを従業員と振り返り、「昔はできなかったよね」という話をしているそうです。
今野製作所のように、中小企業がDX化を推進するためには、何が必要なのでしょうか。今野氏はそのための重要なポイントとして、経営者がITへの理解を深めておくことを強調します。
「今でこそシステム開発は担当者に任せていますが、実は私も給与管理の簡単なアプリケーションを自作しました。ものすごく時間がかかりましたが、おかげで開発ツールの仕組みやどんなことができるのか、仕組みを理解することができました。こうした経験を積んだことで、現在は新しいアプリケーションを開発する際に、開発者とイメージを共有したり、見合った成果が得られるか否かの検討ができるようになっています。
経営者がこのような感覚を持っていなければ、"DXは誤った投資になるのではないか"と心配になり、結局やらないという判断になってしまうと思います」(今野氏)
今野氏はさらに、DXに"期待しすぎないこと"も、DXを成功するための大きな要因だったと振り返ります。
「当社が順調にITを取り入れられた理由の1つに、私自身が『すぐできると思っていなかった』というのがあったかと思います。DXには『スピード』や『抜本的な改革』というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、当社のような製造業の場合であれば、従来のやり方をガラリと変えないことも1つの策だと感じています。"DXは時間かかるもの"と構えて、少しずつ変えていき、いつのまにか従来のやり方から変わっていた、というのが理想的なのかなと考えています。
DX化とは、仕事のやり方、つまり"習慣"を変えるという話ですから、徐々に従来のビジネスにデジタルを馴染ませていくことが大切だと思います。習慣が変わり組織能力が高まった先に、デジタルを活用したからこその新しいサービスが何かしら見えてくるはずです」(今野氏)
今野氏はインタビューの最後に、「中小企業こそDX化は進めやすい」と考察しました。
「今振り返ると、当社はDX化しやすい状況にあったようにも思えます。もともと少人数だったこともあり、一人の人間が複数の業務を行ったり、複数の人間が同じ業務を行ったりすることは普通で、組織の壁がありませんでした。さらに、既存のシステムがない"更地"からのスタートだったため、レガシーシステムの制約を気にする必要がありませんでした。
これらの特徴と共通する中小企業は、きっと多いはずです。中小企業だからといってデジタル化を諦めるのではなくて、むしろ優位性だと捉え、新たなチャレンジをスタートしてみてはいかがでしょうか」(今野氏)
●今野浩好(こんの・ひろよし)氏プロフィール
今野浩好(こんの・ひろよし)
1996年、今野製作所に入社。2003年、代表取締役に就任。2016年からは一般社団法人 インダストリアルバリューチェーンイニシアティブ(IVI)の理事も務める。



 JP
JP