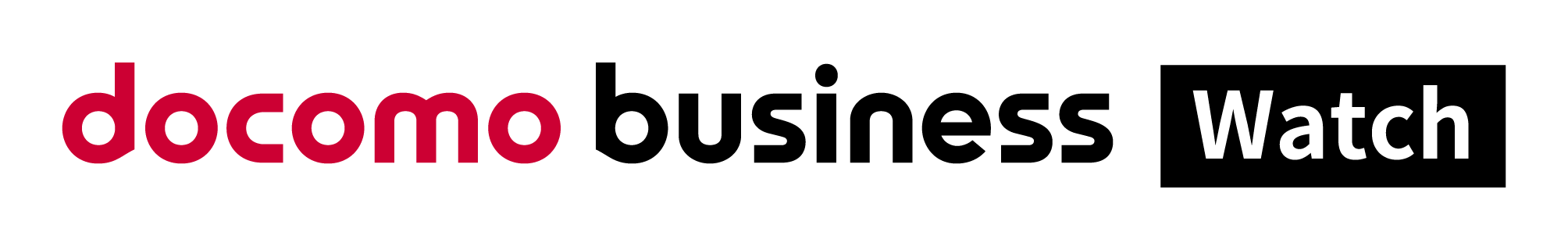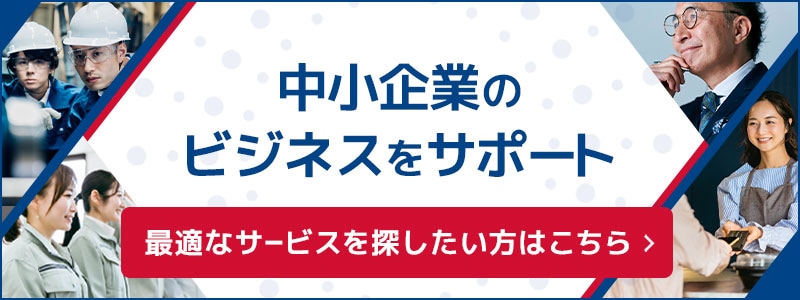「本当に好きなことを事業にしてもいい」
新潟の「はんこの大谷」では、新規事業の社会福祉法人も訪問看護リハビリステーションも人に任せても問題ないフェーズに入り、堂田社長はさらなる事業を考えます。
きっかけは、野村総合研究所と野村證券新潟支店が共同開催した「新潟イノベーション・プログラム(NIP)」への参加でした。
このプログラムは、将来の新潟経済を担う次世代経営者を対象にしたプロジェクトで、スノーピーク代表取締役会長兼社長の山井太さんがアドバイザーとして参画していました。そこで山井さんから「自分が本当に好きなことを事業にしてください」と言われました。
スノーピークは、もともとは新潟・燕三条で「金物問屋」として創業しています。初代社長の山井幸雄さんは「野遊び」が大好きで、既存の登山道具で満足できませんでした。
そこで「本当に欲しい登山道具を自分で作る」という強いwillでオリジナルの登山用品を開発しました。スノーピークのブランド基盤を固め、成功できた理由は「自分の好きなことを突き詰めたから」だという山井さんの話に、堂田社長は感銘を受けたといいます。

堂田社長「山井さんに出会うまで『自分の好きなことや趣味を仕事にしてはいけない。それは社会的にも倫理的にも会社を私物化する行為なのではないか』という、古い固定観念から抜け出せませんでした」
固定観念は、同じ地元で「好きなこと」を事業化した山井さんの一言で変わります。
「新潟イノベーション・プログラム」に参加する前から、堂田夫妻には「ある夢」がありました。それがウイスキー事業でした。「自分の好きなことを事業にしてもいい」。価値観の大転換が、堂田社長を突き動かします。
学生時代のウイスキー造りの夢。諦め会社員に

北海道で生まれ育った堂田社長は、大学生の頃に教授とともに「ニッカウイスキー」の余市蒸溜所を初めて訪れました。それからというものニッカウイスキーのとりこになりました。
余市は「日本のスコットランド」と称されるほど、気候と豊かな自然に恵まれた土地です。ニッカウイスキーの創業者・竹鶴政孝がこの土地にほれ込み、蒸留所を建設したといわれています。
蒸留所を見学した際、堂田社長は「ここで働きたい」と本気で思ったといいます。歴史的な建築もありウイスキーの理想郷のような雰囲気の場所でウイスキーを作る仕事ができたらどれだけ楽しいだろうと想像が広がり、「採用情報」を必死に探しました。
ただ、時代はバブル崩壊後の景気後退の影響を受けた「就職氷河期」。採用の募集枠はゼロでした。さらに、1990年代から2000年代、日本では焼酎がブームだったのに対し、ウイスキー離れが進み、どん底の時代。世界的にもウイスキー需要が落ち込んでいる時期でした。やむなくウイスキー業界への就職を諦め、会社員の道を選びます。

製薬会社の営業であるMR(医薬情報担当者)として忙しく働き、社内でトップの売り上げ成績を獲得することもあり、やりがいを感じていたといいます。現在の妻・尚子さんとは、転勤先の新潟で出会いました。新潟の「大衆割烹」で知り合い、2人とも「お酒が大好き」という共通点もあり、引かれ合ったといいます。

尚子さんと結婚後、東京に転勤して、大学病院の麻酔科担当を行っていました。そこで医療機器を扱う会社からの引き抜きの話があり、転職について尚子さんに相談しました。
そのときちょうど、尚子さんの父、勝彦さん(現会長)が脳出血を患っていたため、尚子さんが社長業を引き継いだタイミングでした。尚子さんが、会社経営のため孤軍奮闘していたこともあり、「転職するぐらいであれば、大谷を手伝ってほしい」と説得され、堂田社長は「はんこの大谷」へ就職しました。
堂田社長「MRの仕事は、楽しくやりがいもあり天職だと感じていました。けれども、会社員としてのキャリアを捨てることに戸惑いはありませんでしたね。自分のキャリアよりも、家族との将来を最優先に考えていました」
夫婦間の何げない会話が、新規事業の背中を押す
2人で会社を切り盛りするなか、ウイスキー事業に乗り出したきっかけは晩酌でした。
10年ほど前、ニッカ「竹鶴17年」は3500円程度で販売されていました。当時は、定価5000円程度の商品が、ダンピングで値下げされていたのです。
堂田社長は「こんなにもおいしいウイスキーがなぜ安く売られているんだろう」と不思議に思っていたといいます。しかし、2016年頃からウイスキーブームが再び訪れて、「竹鶴17年」は5000円に一気に値上がりしました。
夫婦でウイスキーを飲みながら、「近い将来、日本のウイスキーって、僕らが手の届かないほどの高い値段になっちゃうんだろうな」と堂田社長がぼやいたところ、「じゃあ、自分たちで作ってみればいいじゃない」と尚子さんに言われました。
「そうは言ったって、大変なんだよ」と二の足を踏む堂田社長に、「でも、調べてみないと分からないでしょう」と尚子さんは諦めません。

堂田社長「最初は、私よりも妻のほうが本気だったかもしれません。そこで取引のある銀行に紹介してもらい、日本のクラフトウイスキーメーカーを何軒か訪問させていただいたんです。訪問を重ねるうちに、素人ながら『もしかしたら、できるかもしれない』と思うようになりました」



堂田社長はそれまで、ニッカウイスキーの余市蒸溜所、サントリーの山崎蒸溜所など歴史のある古い工場しか見ていなかったので「あんな大層なものができるわけない」と心の中で決めつけていました。
けれども、クラフトウイスキーメーカーを見学してみると、「造り酒屋」のようなたたずまいで、意外とこぢんまりと作られています。こんな「小規模蒸溜所」であれば、自分たちでもできるかもしれないと乗り気になります。
当初は、会長の勝彦さんに反対されるのを恐れていましたが、「やっぱり好きなことを始めたい」と、堂田社長はウイスキー事業に着手する決心をするのです。
作れる人がいないから、社長がいちから学ぶ
心は決まったものの、「そもそも、ウイスキーを作れる人がいない」という課題がありました。そこで、堂田社長は自らウイスキー製造の勉強を始めます。
まずは、ウイスキー専門雑誌を出版している「ウイスキー文化研究所」の土屋守さんを頼りました。その伝手で鹿児島の老舗酒造メーカーで1カ月間、研修させてもらい、造り方の基本を学びました。そこでは、グローバルな視点に立ったマルチな酒類事業が行われていて、強く刺激を受けたといいます。
さらにウイスキー文化研究所が主催する研修「プロのためのウイスキー製造概論」にも参加し、一からウイスキーの造り方を学びました。


堂田社長は、研修を受けた後もさまざまな文献を読みあさり、ウイスキー製造の体系を頭に叩き込みました。
そして、2019年に創業。翌20年に生産開始を目指しましたが、新型コロナウイルスの影響で設備が整わず、予定より1年ほど遅れた21年にスタートしました。
初期投資は3億円。さらに追加の投資で合計6億円ほど。さらに土屋さんにコンサルに入ってもらい、きめ細やかなアドバイスを受けました。
堂田社長「研修や講座など、学べることは全て意欲的に学びました。大金をつぎ込んでいるので、『事業の失敗』という選択肢はなかったですから(笑)」
立ち上げ当時は、堂田社長と元バーテンダーの社員の2人でウイスキー造りを開始。最初の1年間は「トライ&エラー」の毎日で、ウイスキー造りに向き合い、休みなく働きました。

堂田社長「おいしいウイスキーが造りたくて何度失敗したか分かりません。けれども、自分が好きなことなので挫折にはならないんです。地道な作業ですが、つらいと感じたことはありません」
クラフトウイスキー造りには、標準的なマニュアルを押さえつつ、発酵の時間、温度、配合などを常に試行錯誤し「自分たちの好みの味」「独自のレシピ」「自分たちのスタイル」を追求していく面白さがあります。
ウイスキーは蒸留した後に樽に寝かせてから3年以上経過しないと「ウイスキー」にはなりません。今は、蒸留したばかりの未熟成の「ニューボーン」や「ニューポット」を販売しています。これらは、まだ荒々しい味わいを残しつつ、複雑な香りが交じり合っているのが特徴です。
2年連続で世界的評価、量産難しく予約待ちに
新潟亀田蒸溜所の商品「ニューポット」は、2022年と翌23年の2年連続、イギリスのウイスキーマガジン社の主催するウイスキーの世界的品評会「ワールドウイスキーアワード」で入賞を果たしました。

ニューポットは、未熟成原酒で量産が難しいため、自社のホームページでささやかに販売をしていましたが、受賞後に注文が殺到。1万本販売され、今も予約待ちの状態が続いています。

現在、国内ではクラフトウイスキー工場が約100社にまで増え、「レッドオーシャン」状態です。だからこそ味や品質において「差別化」が必要です。そんな中で、イギリスの品評会で最高賞を獲得できたことは、好調なスタートが切れたと言えるのではないでしょうか。
堂田社長「スノーピークの山井さんを含めた新潟県内の企業や、会長、妻にも出資してもらっているので、皆さんの期待に少しでも応えられて良かったと少しほっとしています。でも、まだまだひよっこです。2年後にリリースする予定の『ウイスキー』でどう勝負するかを考える日々ですね。初めは反対をしていた会長も、今では応援してくれています」

堂田社長「好きなことは、どれだけ突き詰めても飽きることはない。失敗したとしても挫折だと感じることもない。だから、おのずと成功することができるんです。新潟は米どころ、酒どころ。将来的には、新潟清酒のように口当たりが淡麗なウイスキーを造りたいですね」

はんこを祖業に多岐にわたるビジネスを展開、並走させている堂田社長ですが、現在はウイスキー事業4割、はんこ事業3割、福祉事業や訪問看護ステーション3割の割合で、時間とエネルギーを割いています。それぞれバラバラの事業を展開できているのは、「いい人たちに巡り合えていて、仕事を任せられているから」だといいます。
ウイスキーの真の評価が出るのには、5~10年かかると言われます。そのときにいかにおいしいウイスキーを提供できるか。「異業種からの参入ならではの常識にとらわれないアイデアで、ユニークな挑戦をし続けたい」と、堂田社長は生き生きと語ります。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。
取材・文:松浦美帆
写真:高橋信幸
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:野上英文



 JP
JP