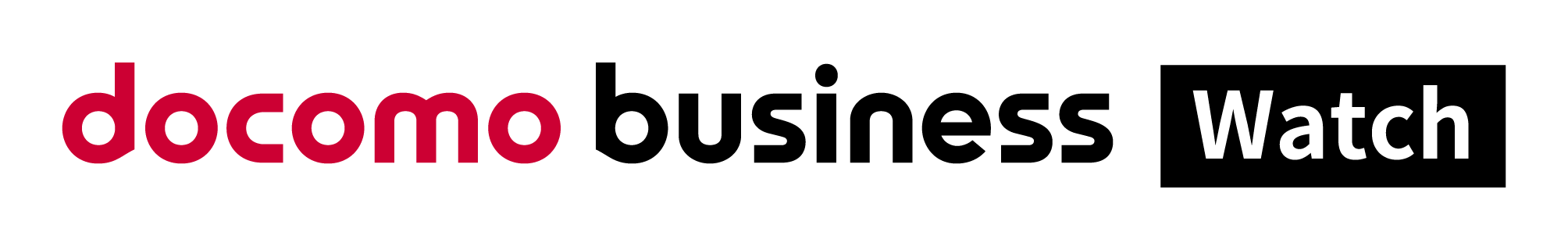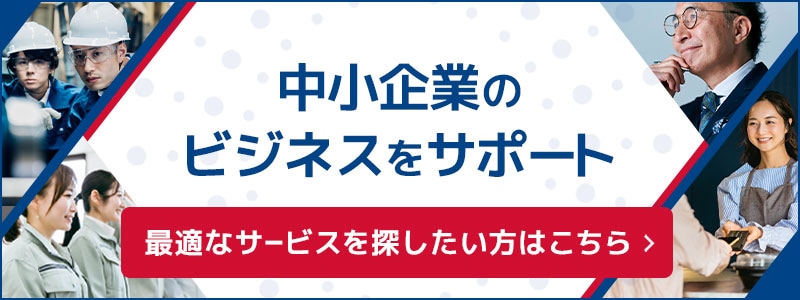そもそも裁量労働制とは
裁量労働制は「働いた時間の長さ」ではなく「働いたことへの成果」に対して報酬が支払われる制度です。労働者が自分の裁量で、仕事の進め方や労働時間を決められるため、うまく運用できれば働き方改革や生産性向上が期待できます。
とはいえ、裁量労働制はすべての職種に適用できるわけではありません。厚生労働省では、裁量労働制が適用できる業務を「専門業務型」と「企画業務型」の2つに分類しています。
専門業務型
専門業務型の裁量労働制は「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務」(※)とされており、19業務が指定されています。研究者やシステムエンジニア、デザイナー、プロデューサー、弁護士、建築士などが該当します。
※厚生労働省「専門業務型裁量労働制」
企画業務型
企画業務型の裁量労働制はその対象を「事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者」(※)としており、以下の4つの要件をすべて満たす業務が対象となります。
- 事業の運営に関する事項についての業務であること
- 企画、立案、調査及び分析の業務であること
- 当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること
- 当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること
※厚生労働省「企画業務型裁量労働制」
このように、適用職種は限られるものの、裁量労働制は労働者側としては自由な働き方ができるなどメリットも多くありました。しかし前述の通り、2024年4月に制度の見直しが行われました。どのような背景があるのでしょうか。
裁量労働制見直しの背景
一見、労働者のメリットが多そうな裁量労働制ですが、これまでの運用のなかでいくつかの問題点が発生していました。そのうちの一つが、長時間労働が常態化しやすいことです。
2021年に厚生労働省が行った「裁量労働制実態調査」(※)によれば、裁量労働制が適用された労働者がいる事業所では、1か月の労働時間の状況の平均(1人当たり)は171時間36分、1日の労働時間の状況の平均は8時間44分という結果に対し、非適用事業場における1か月の労働時間の平均(1人当たり)は169時間21分、1日の労働時間の平均は8時間25分と裁量労働制が適用された労働者のほうが、長時間働いているという実態が明らかになりました。
※厚生労働省「裁量労働制実態調査」
先に述べたように裁量労働制では、あらかじめ定められたみなし労働時間を超えても、給与が追加されるわけではありません。そのため、企業によっては残業代を減らしたいという理由から裁量労働制を導入するケースもあります。みなし労働時間では到底完了の見込みが立たない量の業務を与えられた従業員が、長時間労働に陥ってしまうケースが問題となっているのです。
もう一つの問題が不適切な制度利用が行われている点です。裁量労働制を適用できる職種は厳密に定められていますが、一部の企業では営業職や事務職など、適用職種とは異なる従業員にも裁量労働制を適用し、残業代を削減しているケースが報告されています。
こうした裁量労働制の問題点を改善するために、今回の制度の見直しが進められています。
裁量労働制はどう変わる?

2024年4月以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入するすべての事業所で以下の対応が必要です。
対応が必要な事項
①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める(専門型・企画型)
②労使委員会に賃金・評価制度を説明する(企画型)
③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う(企画型)
④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する(企画型)
⑤定期報告の頻度の変更(企画型)
具体的には、専門業務型裁量労働制の労使協定に①を追加、また企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に②③④を追加後、決議に①②を追加し、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行わなければなりません(※)。
※厚生労働省「事業主の皆さまへ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」
裁量労働の適切な運用は、適切な勤怠管理から
これまで述べてきたように、裁量労働制は決して残業代を削減するための制度ではありません。休日出勤はもちろん、裁量労働制でも残業時間には上限もあります。今後も裁量労働制を採用していく場合は、制度変更への対応はもちろん、これまで以上に適切な勤怠管理を行う必要があるでしょう。
たとえばドコモビジネスでは勤怠管理ツールとして「dX勤怠・労務管理」というサービスを提供しています。こうしたクラウド型勤怠管理サービスを利用すれば、従業員は場所や時間を問わず、勤怠の記録ができるため、より適切な労働時間の管理ができるでしょう。
日本企業を取り巻く環境は日々変化しており、労務関連に関する不適切な対応は、場合によっては企業に大きな影響を与えかねません。こうした制度の改正を機に、あらためて自社の働き方について見直してみてはいかがでしょうか。
※本記事は2023年10月現在の情報を元に作成されています。最新・正確な情報は各省庁や自治体のホームページをご確認ください。



 JP
JP