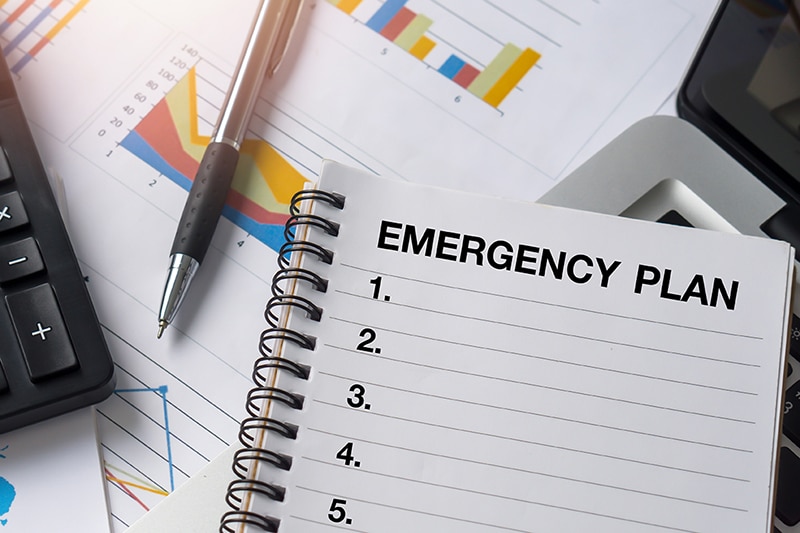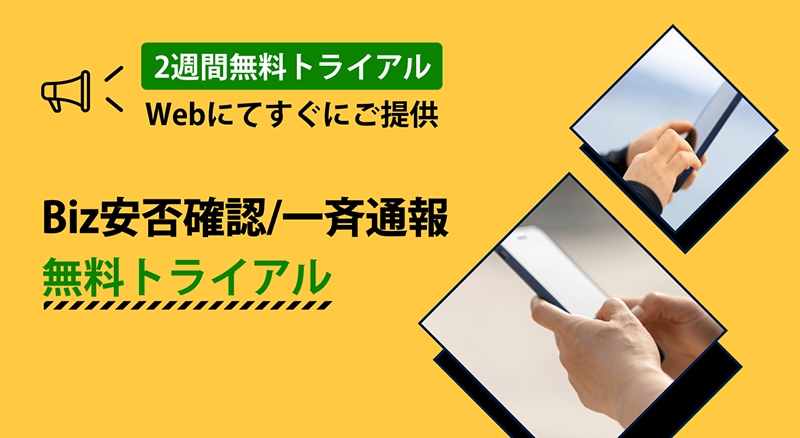世界のM6級大地震のうち、
18.5%が日本で発生している
日本は自然が豊かな国ですが、それは一方で「災害」に遭いやすいということも意味します。
一般社団法人 国土技術研究センターのサイトによると、日本の面積は全世界のわずか0.29%だけ。にもかかわらず全世界の活火山の7.1%が日本に集中し、マグニチュード6以上の地震の18.5%が日本で発生しているといいます。さらに、全世界で発生した災害の死亡者のうち1.5%、全世界の災害による被害金額の17.5%が日本というデータも存在します。
(※)一般社団法人 国土技術研究センター「国土を知る / 意外と知らない日本の国土」
さらに地震をはじめ、台風や洪水、地滑り、火山など、災害の種類が多いことも日本の特徴といえるでしょう。
このような自然災害が発生した場合、被害の状況によっては、ビジネスの継続が困難になることは十分に起こり得ます。たとえば地震でオフィスが崩れたり、洪水で工場が浸水したりした場合、普段のようにオフィスや現場で業務を開始することはできません。これに加えて、鉄道や道路、電気や水道といったインフラが絶たれた場合も、業務の継続は困難です。
いつ災害が起こっても不思議じゃない。
だから準備が重要
こうした災害などの緊急事態が発生した際、その被害を抑えつつ事業を継続する取り組みのことを「BCP」(もしくは「BCP対策」)と呼びます。
BCPは自然災害だけでなく、パンデミックや事故、セキュリティ被害といったさまざまなリスクを想定して策定されるものですが、災害大国である日本では、とりわけ自然災害に備えた対策が優先される傾向にあります。
しかし、BCPを策定するにも人手やノウハウの不足から、特に中小企業などでは十分な取り組みができていないケースも少なくありません。その一方で、2024年4月からは、介護サービス事業者にBCPの策定および研修・訓練の実施が義務づけられるようになるなど、BCPの重要性は増しています。
気候変動により災害は増加傾向にあり、パンデミックもいつまた発生するかわかりません。事業内容にかかわらず、有事に備えるための早めのBCP対策が賢明といえるでしょう。
「BCPの策定」というとハードルが高いようにも聞こえますが、定期的な訓練の実施や防災備蓄品の準備管理などもBCP対策です。最初から完璧を求めず、自社が優先すべき対策からまずは着手し、段階的に策定していくという方法で進めてみることをおすすめします。
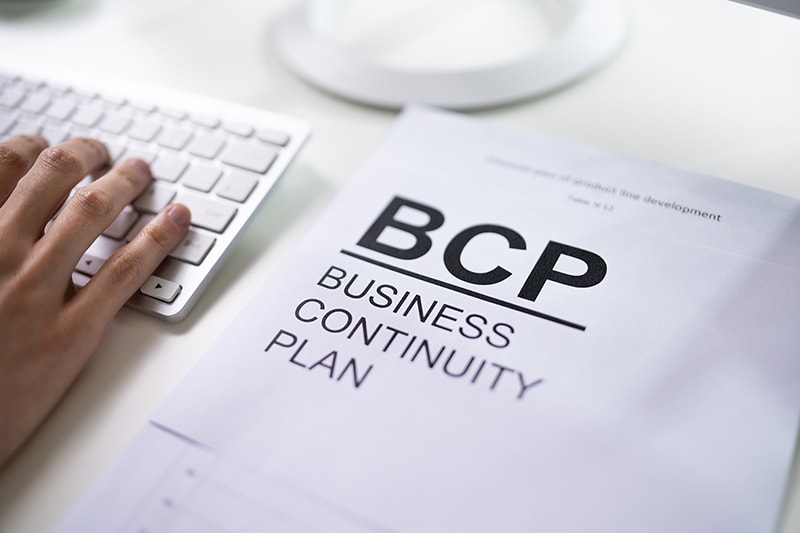
「安否確認は電話やメール、SNSで良い」では危険
このBCPの中でも重要な準備の一つが「安否確認」です。安否確認とは、災害が発生した際、従業員や従業員の家族などの安全や被害の状況を確認することで、災害などが発生した際に、まず企業が行うべきことの一つといえるでしょう。
安否確認の結果を今後の事業継続の指針として役立てることはもちろんですが、そもそも企業には従業員に対して安全で働きやすい環境を確保する「安全配慮義務」が存在します(※)。災害時に従業員の安否確認を行うことは、企業の責任でもあるのです。
※労働契約法 第五条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
安否確認は、電話やメール、SNSといった、通常の業務で使う連絡手段をそのまま利用することも可能です。しかし、どのツールも、緊急時には心許ない面があります。
たとえば電話は、リアルタイムに直接従業員と話ができるため、従業員が置かれた状況を把握しやすいというメリットがあります。一方で、災害時は多くの人が安否確認を行うため、電話がつながりにくいケースも多く発生しがちです。もしつながったとしても、一対一の対話になるため、被害の状況の聞き取りを従業員の人数分繰り返さなければなりません。その情報を一人ずつ集計するのも非常に大きな負担となるでしょう。
メールを使った安否確認の場合は、電話とは異なり、一斉送信が可能です。非常に効率的ではありますが、一方で他のメールに埋もれて気づかない恐れもあります。場合によっては、会社のメールを業務時間外に受信(確認)できない従業員もいるでしょう。これを回避するために、プライベートのメールアドレスを使用すると個人情報の管理という問題が発生します。また、メールリストの管理を怠っていた場合、新入社員にメールが届かなかったり、すでに退職済の従業員に送付したりする恐れもあります。
コミュニケーション手段として多く利用されているSNSはどうでしょう。既読表示機能があるため、急ぎの安否確認がスムーズなのはメリットです。しかし、プライベートのアカウントを会社と共有しなければならないのは、従業員からは歓迎されないでしょう。また他の安否確認方法同様、集計にかかる手間も小さくありません。
| 安否確認の方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 電話 |
|
|
| メール |
|
|
| SNS |
|
|
大震災に耐えたデータセンターで
運用中の安否確認サービスがある
それでは、どうすれば安否確認がスムーズに行えるのでしょうか? 最も簡単な方法は、安否確認専用のサービスを利用することです。NTTコミュニケーションズの「Biz安否確認/一斉通報」(以下、Biz安否確認)も、そうした安否確認サービスの一つです。
Biz安否確認は、設定した震度以上の地震が発生した際や、大雨・洪水・土砂災害といった気象特別警報が発出された際に、安否確認を自動で従業員に配信(自動発報機能)し、その回答を自動で集計するサービスです。回答方法は、事前に用意された質問の中から選ぶシンプルなスタイルのため、従業員も回答登録しやすく、管理者側も集計しやすい特徴があります。従業員の安否確認の漏れを防ぐため、未回答の従業員に対して自動で再送信することも可能です。再通知は最大5回まで自動で行うため、管理者側の負担の軽減が期待できます。
「一斉通報機能」は、自然災害などの緊急時のみならず、「平常時の社内連絡」などにも幅広く利用できます。
ある交通機関A社では、Biz安否確認を運行トラブルが起きた際の情報共有に役立てたり、社外活動といった社員同士のコミュニケーションにも活用していると言います。迅速かつ正確な情報共有がビジネスに役立つメリットはもちろん、普段から安否確認システムの操作に慣れておくことは、いざという時、社員がスムーズに安否確認システムを利用することにもつながります。
冒頭でも触れたとおり、日本ではいつ大災害が発生してもおかしくありません。平時からの準備が必要ではありますが、一方で日常の業務が忙しく、いざという時の備えが用意できていない企業も少なくないことでしょう。
現在NTTコミュニケーションズでは、Biz安否確認を2週間試行できるトライアルを実施しています(利用ID数は最大40。トライアル終了後は、有料プランに自動で移行しません)。もし準備が進んでいないのであれば、まずは災害対策の第一歩としてBiz安否確認を試してみてはいかがでしょうか。
「Biz安否確認/一斉通報」の2週間トライアルは、下記のバナーよりお申し込みください。



 JP
JP