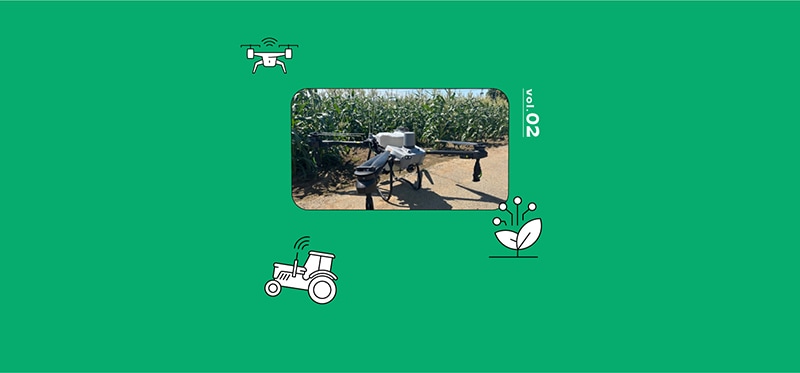アグリテック企業が集まる深谷市
2019年3月に、農業とそれに関連する領域の発展に寄与する企業をターゲットとした誘致策として、「アグリテック集積戦略」を策定した深谷市。
アグリテック企業の誘致を目的に、毎年、本市主催のアグリテックのコンテスト「DEEP VALLEY Agritech Award」を開催しています。
最優秀賞を受賞した企業には、株式取得のための出資交渉権を、1000万円を上限として授与しています。参加企業に対しては、受賞の有無や企業規模の大小などに関わらない支援を行っており、アワードを機に拠点を深谷に移す企業も出てきています。
2020年の「DEEP VALLEY Agritech Award」で、現場導入部門最優秀賞を受賞し深谷に拠点を移して活動する株式会社レグミンは、2018年の起業時には、静岡に拠点を持っていました。代表取締役の成勢卓裕さんに伺いました。

成勢「スタートアップ時は、ロボット開発も初めてで、農業も初心者。まず、小松菜を自分たちで育てながらオール自動化を目指して開発を進めることにしました。でも、小松菜を育てること自体が非常に難しく、行き詰まっていました」
そんなときに深谷市から声がかかり、「DEEP VALLEY Agritech Award」への参加を決めたという成勢さん。現場導入部門最優秀賞を受賞したレグミンは深谷に拠点を移します。

成勢「ちょうど、コロナ禍で、スタートアップの資金調達環境の見通しが立たない時期でしたから渡りに船でした。
それまでは、種まきから収穫までをロボットで自動化することを目指していたのですが、深谷のねぎにすぐ使えそうな農薬散布ロボットに切り替えて、開発を進めました」
農業を知るところから始まるアグリテック
一方、レグミンと同じく2020年に「DEEP VALLEY Agritech Award」で未来創造部門最優秀賞を受賞したAGRIST株式会社は宮崎に拠点を持ったまま、深谷市との連携を進めている企業です。代表取締役の秦裕貴さんに伺いました。

秦「アワードに参加した当時、我々はまだ、拠点としている宮崎で、ロボット開発を盛んに行っているタイミングでした。遠隔地にロボットを持って行って活動できる状況ではありませんでした」
深谷市のコンテストは、受賞企業に対し、株式取得のための出資交渉権として1000万円を上限として授与し、その後も企業との継続的な関係性は構築されていくのが特徴です。
秦「深谷市さんからは、我々が開発しているキュウリの収穫ロボットの導入について色々なご提案をいただき、キュウリの生産者の方をご紹介いただいたり、『将来的に一緒にやりましょう』という言葉をいただいていました」

今年に入り、ロボットを実際に現場で使える状態になってきたこともあり、今年から深谷市との動きが活発になっているといいます。
アグリテックの生産現場導入の壁
一足先に、拠点を深谷に移したレグミンは、2022年に自律走行ができる農薬の自動散布ロボットを開発。深谷ねぎ農家さんの協力のもとに実証実験が重ねられ、改良が進み、AIによる自動運転により、1回の給水で300Lの農薬散布が可能になったといいます。
今回取材に伺ったのは7月初旬でしたが、深谷ねぎ畑で農家から請け負ったレグミンのスタッフが、自律走行型ロボットによる農薬散布を行っていました。
手動の動力噴霧機に比べて、約半分の時間まで短縮可能とのことで、高齢化が進む生産者の負担を格段に減らすことができるといいます。

成勢「深谷市で最優秀賞を取らせていただき、その後、農林水産省の実証プロジェクトに採択していただいて、農作業受託サービスをスタートしています。今取り組んでいるのは、事業化の壁をどうやって乗り越えるかというところです」
成勢さんは、農家から、「自分たちで撒くのと変わらないね」「均等に撒けていて驚いた」と言われ、その声が喜びにもつながっているといいます。
次の課題は農業の未来を見据えた開発と事業化
深谷市では、生産者が新しい機器の導入や整備をするための経費の2分の1、最大で50万円を補助をする「深谷市アグリテック導入支援事業補助金」制度も整備されていますが、実際に農家が、ロボットを購入し、農作業を効率化していくには、まだまだ時間がかかるであろうと考えています。
そこには、農業ならではのスピード感があるようです。
成勢「農業は、拡大するにしても物理的なもの。なかなか、ソフトウェアのスタートアップのように半年で売り上げが5倍になるようなことにはなりません。
ロボット導入にも、まずロボットをその現場に持って行って、一人ずつトレーニングをするなどの手間がかかります」
秦「工場向けの自動化するシステムの場合は、何を目標にしてこのシステムを設計し、どうなれば完成、成功なのかが比較的はっきりしています。
一方農業は、実際の生産現場の自動化のプロットを考えるとき、本当にそこに農業の未来があるのかという視点が必要になってきます」

現在の農業の生産と出荷の仕組みは30年前に作られたもの。そこにただ自動化ロボットを導入するだけでは、便利にはならないという認識もあるようです。
秦「現在の農業の生産と出荷の仕組みは、多くの生産者がいた時代に作られたものです。それは、品質を底上げして産地として生き残っていく当時の戦略でもありました。
現在では、売買方式なども含めて、産業構造としても、必然的に転換していくタイミングでもあると考えています」
次回は、アグリテックが農家に浸透していくために必要なものや、アグリテック企業の取り組み、深谷市の更なる挑戦についてレポートします。
この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。
編集:岩辺みどり
デザイン:山口言悟(Gengo Design office)
取材・文:Yoshimura Maru(編集オフィスPLUGGED)
写真:小野さやか



 JP
JP