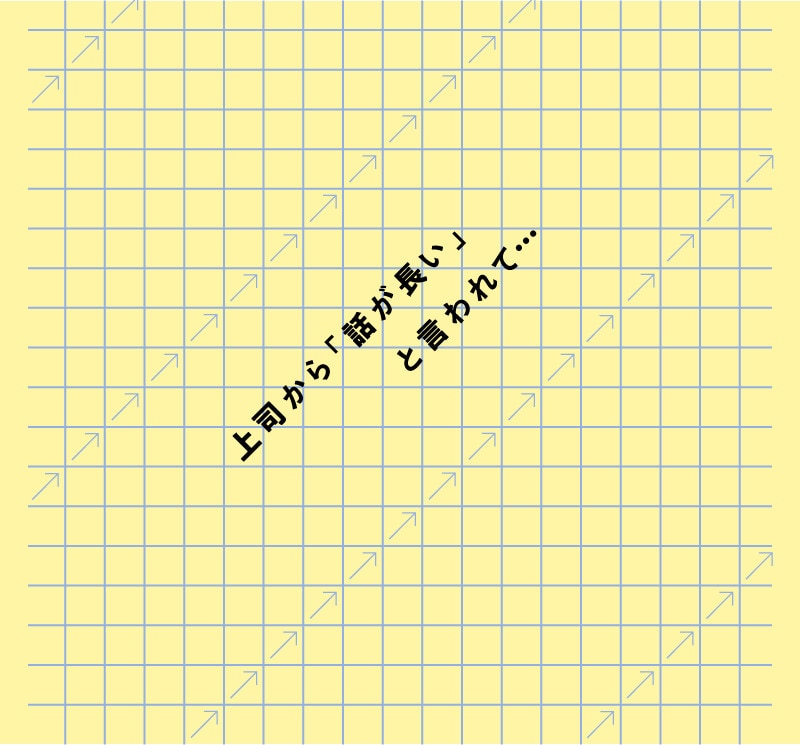「話が長い」と言われたナオミさん
会社員のナオミさん(仮名、20代女性)は以前、上司から「話が長すぎて、なにを言いたいのかわからない」と指摘されてからというもの、話すのが苦手になってしまいました。ナオミさんはそれからというもの、上司にちょっとした報告をするときにも、プレゼンのときにも、こう思って不安になります。
「ああ、また話長い、話ヘタくそだって思われてるんだろうな」 「また、なに言いたいか伝わらないのかな」
こんな状況が続いているので、ナオミさんはもうその上司が苦手になってしまいました。その上司の前でプレゼンがある日は、前日からずっと不安でおなかが痛いのです。
ナオミ「私だって、うまく話したい。でも、なんでちゃんと伝わらないのかわからない」
実は、ナオミさんはプライベートではものすごくよくしゃべる人で、友だちとお茶をしながら4時間でも話しています。そういうときに「話が長い、わかりにくい」とは言われたことがありません。母親ともよく話しますが、母はいつも「ナオミと話すと楽しい」と言ってくれます。
なのに、なぜかその上司のような人には伝わらないのです。

そういえば、ナオミさんには似た経験が学生時代にもありました。大学では工学部にいたナオミさんですが、指導教官からも「なにが言いたいかわからない」と繰り返し言われていたのです。
どうしてときどき、このようなことがあるのでしょうか?
2つの「情報処理」タイプ
ふだん私たちがしていることを「情報処理」の視点から分類すると、①情報を取り入れて(インプット)、それを②脳で処理して、③アウトプットするという3つの過程に分けられます。
このうち②を情報処理と呼び、「これは赤くて丸くてこのぐらいの大きさだから、リンゴだな」と判断したり、「もしかしたら毒入りかもしれない」と推理したり、「このリンゴが3個で600円だから、1個あたり200円だな」と計算したり、「おなかすいてるから、これ食べたいな。ほしいと伝えてみようかな」と意思決定したりする過程を指します。

こうした情報処理には、大きく分けて2つのタイプがあるといわれています。外から入ってきた情報を、はじめにざっと見渡して全体像をつかもうとする「同時処理タイプ」と、順にひとつずつこなしていこうとする「継次処理タイプ」です。この情報処理のタイプは、コミュニケーションの取り方に大きく影響します。
まずはみなさん、この2つのタイプで、より多く当てはまるのはどちらですか?
同時処理タイプ
- 本を読むときは最初にパラパラとめくってみて全体をつかむ
- 本を読むときは気になるところから読むこともある
- 選択肢をたくさん出して、詳細はあとから考える
- 状況をざっと把握できる
継次処理タイプ
- 本を読むときは目次から読む
- 本を読むときは最初から順に読む
- 筋道立てて、順にこなしていきたい
- 仕事を教えてもらうときには、ひとつずつ順に習いたい
電気回路でたとえるならば、同時処理タイプは並列つなぎ。継次処理タイプは直列つなぎです。それぞれのタイプの人に仕事をお願いしようとしたら、次の点に注意するとうまくいきます。
同時処理タイプには「見ておいて」と見学してもらったり、おおまかな説明をしておけば、なんとなくわかってくれて、「これ頼むけど、もしいけそうならこれもできる?」といったように、いくつかのタスクを振ることも可能です。
継次処理タイプには「この仕事の背景はこうで、全体の項目はこの10個」のように、目次のような前置きが必要です。そして「まずはこれをして。終わったら次の仕事を頼むから教えて」といったように、ひとつずつ投げていく感じがいいでしょう。

両方の情報処理タイプに、同じぐらいチェックがついた方も多くいらっしゃるかもしれません。この場合、どちらの情報処理もできるという意味で柔軟で、適応しやすいでしょう。
しかし、どちらか一方のみが多い方は、自分の情報処理タイプをよく認識しておいたほうが、勉強でも仕事でもコミュニケーションでもうまくいくでしょう。反対に認識なしでは、ナオミさんのようにツラい思いをしてしまうかもしれません。
相手の「情報処理」タイプに合わせる
ここで話をナオミさんの「話が長い、わからない」問題に戻しましょう。この問題と情報処理タイプは深いつながりがあります。基本的に同じ情報処理タイプの人同士は、話が通じやすいといえるでしょう。自分と同じ捉え方をしていますし、同じ手順で物事を処理していこうとするからです。
ナオミさんは、同時処理タイプでした。むかしから「あの映画はだいたいこんな感じだった」とおおざっぱなあらすじや感想を伝えるのは得意でした。しかし、あくまでおおざっぱなので、「その映画のどういうところを見てそう思ったの?」と根拠を尋ねられると、うまく答えられないところがありました。
そういえば、ナオミさんは、むかしリカちゃん人形の洋服を見よう見まねで作ったことがありましたが、洋服作りの基礎など知らないけれど、布を当てながら感覚だけでササッと作ることができました。細部はまったく気にしていなかったので、ザツな出来栄えではありましたが、短時間でセンスのいい服になりました。

教育実習でも、先生方の授業を見ただけで要領がつかめたため、詳細はともかく、授業の計画を思いつくのは早く、苦労しませんでした。反対に卒業論文では苦労していました。あらかじめ理論背景を固め、仮説を立てて、検証するための実験を行い、考察するといった一連の緻密な流れを作るのが苦手でした。ナオミさんはいつも「うん、やりながら考えよう」というタイプだったからです。
そして、その苦手な上司はおそらく継次処理タイプだったようです。上司はナオミさんの話があやふやな根拠しかなく漠然としている点や、あちこちに脱線する点に疲弊するようでした。上司なりに話の順番が見えていて、それが順に並んでいないと、理解しにくいようです。
もちろんこのタイプは、計画を決めたらそのとおりに実行して、脱線せずにやり遂げることができるタイプです。しかし、同時に複数のタスクをこなすように言われたり、仕事も家庭も介護も……と気にかけなければならないことが多方面にわたったりすると、こなせなくなりがちです。

私たちが誰かに話したり、仕事を教えたり、相手を説得したりするときには、この両者のタイプの違いを念頭に置いて、相手の情報処理タイプに合わせる形で情報を提示していくとうまくいきます。
「今日みたいな報告だと助かるよ」
ナオミさんは、その上司の継次処理に応じた話し方を準備しました。
ナオミ「じゃあ、仕事の進捗の報告は、最初に結論を伝えるとか、2点ありますとか、目次みたいなのを前置きするといいのか。そして、なぜそうなったかなどの理由や背景の説明とか、“ちなみに〜です”といった追加情報は極力少なくすると理解しやすいのね」
ナオミさんは要点を箇条書きにしたメモを手に取り、それを見ながら脱線しないよう注意して、どんなに不安で情報を付け足したくなってもガマンして簡潔に話しました。そして、上司が「もっとこれについて教えて」などと質問してきたら、そこで初めて情報を追加したのです。
この方法は非常にうまくいきました。上司が初めてこう言いました。
上司「わかった。今日みたいな報告だと助かるよ。そのメモ、ちょっと見せてもらっていい?」
上司は、ナオミさんがわざわざメモまで作って努力している姿にも感動したようでした。

いかがでしたか? まずは自分の情報処理タイプを知って、仕事や勉強や家事をこなす計画を立ててみましょう。そして相手の情報処理タイプを推測し、それに合わせて話すことでぐんと伝わりやすくなりますよ。
中島美鈴(なかしま・みすず)
公認心理師・臨床心理士。博士(心理学)。九州大学大学院人間環境学研究院学術協力研究員。X発信中。このコラムの更新や筆者のADHDや心理学系のお役立ち情報が受け取れます。
この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。
文:中島美鈴
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:鈴木毅(POWER NEWS)



 JP
JP