■前回の記事からご覧になりたい方はこちら
フォロワー170万人超え「ショートドラマ」で日本のエンタメを世界へ
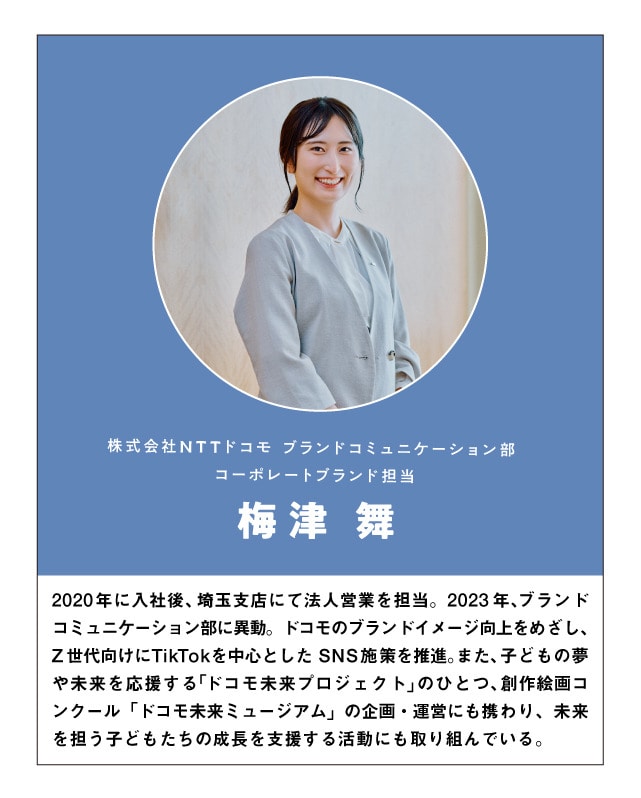
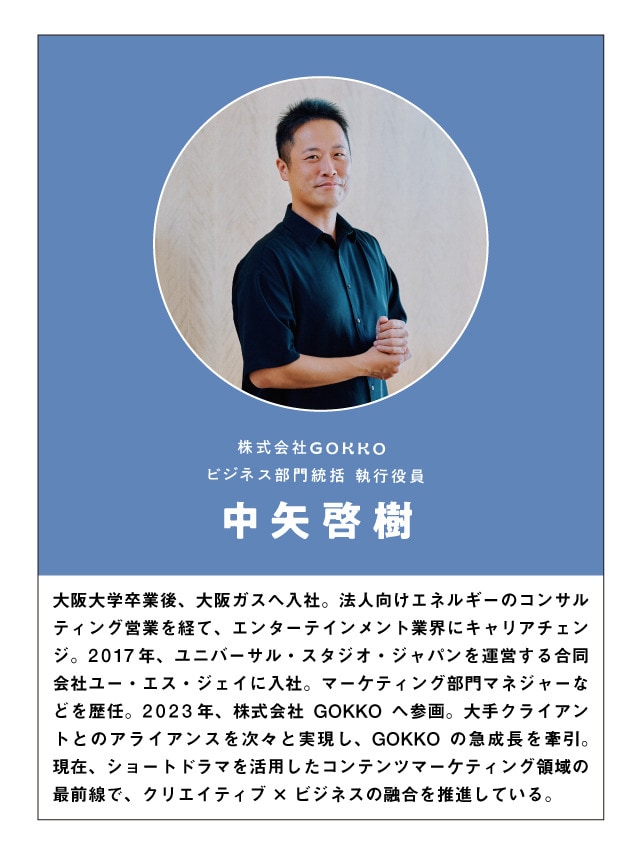
ターゲットは高校生、制作を手がけるのはZ世代
──NTTドコモ(以下、ドコモ)とごっこ倶楽部の取り組みが始まった経緯を教えていただけますか。
梅津「若者にとって携帯キャリアの存在が日常に溶け込みすぎていて、ドコモに対するブランドイメージをもたれていないことに課題を感じていました。そこで若者の共感を生むコンテンツの配信などを通じて、ブランドの価値を高めようと考えたんです。
年間を通して若者とコミュニケーションをとるために、彼ら・彼女らが日常的に触れているTikTok、なかでもショートドラマに着目しました。
ショートドラマは、そのストーリーの展開から長時間の視聴やコメントの書き込みといった高いエンゲージメントが期待できます。それによりバズが生まれ、多くの視聴者に動画を見てもらうことができるのです。

青春の身近なところに存在するスマホやネットワーク、それを陰で支えているドコモ
といった、ストーリーのなかに企業が伝えたいメッセージを込めることができる相性のよさも、ショートドラマを選んだ理由です。
そうした考えから、すでに企業との制作の実績があったごっこ倶楽部さんに私たちからお声がけして、取り組みが始まりました」
──今回の取り組みでは、青春の一ページ、高校生活の日常風景を切り取るようなショートドラマが配信されています。題材を決めるのに、どのようなプロセスを経たのでしょうか。
中矢「動画を届けたいターゲット、そして何を伝えたいのかを聞いたうえで、それをクリエイティブとしてどうかたちにするのか、ごっこ倶楽部とドコモさんの双方で議論してテーマを決めていきました」

梅津「動画を見てもらうターゲットは、15歳から24歳のZ世代、なかでも高校生をメインに設定しました。
学生にとって、受験や卒業といった大きなイベント以外の、席替えや放課後といった日常的なシーンをドラマにすると面白そうだという話がお互いのコミュニケーションのなかで生まれ、いまの動画のかたちにたどり着きました」
中矢「実際の作品づくりは、ショートドラマ一本一本の企画から撮影、編集に至るまで、一気通貫してごっこ倶楽部のメンバーが担当しています。監督や脚本など、チーム自体が主にZ世代のメンバーで構成されているんです。
そしてひとりよがりな企画にならないように、すでにTikTokで数多く見られている動画への反応、どういったコメントが書き込まれているか、どのコメントに『いいね』がたくさんついているかなど、リサーチして参考にしています。
視聴者が確実にいるボリュームゾーンを目がけて動画を制作しているので、最終的に100万回、1000万回近くといった再生数に達する動画を生み出せるのです」

ショートドラマ制作はスピードが命、
社内調整に奔走
──制作が進むなかで、両者はどのようにコミュニケーションをとっているのでしょうか。
中矢「実は私たちから、たくさんお願いしたことがありまして。
例えばドコモさんがこれまで手がけてきたテレビCMは、準備を経て3カ月から半年といった長い期間をかけて制作されてきたのではないかと思います。
一方でショートドラマは、TikTok上のトレンドをタイムリーに企画へ落とし込むことが、バズを生むために重要です。
そこで企画から撮影、編集、投稿までを、非常に短いスパンで実行したいという要望をお伝えしました。
それに対して社内で調整していただいた結果、通常では考えられないスピードでのチェックバックが実現しています。これがこの取り組みの成功の秘訣といっても、過言ではないですね」

梅津「調整はとても大変で、社内の説得に半年ほどかかったかと思います。
そもそもTikTokがどういうものか、なぜショートドラマがバズるのかを実際の動画を見てもらって納得してもらうところから始めました。
そして動画のチェックを社内の上層部まで通すととてもスピードが追いつかないので、制作の流れを理解してもらって、現場のチームに任せてくださいと伝えて説得しました。
これまでにないスピード感で制作が進むことに対する懸念、リスクをとても気にされたので、リスクをすべて洗い出して、一つひとつに対してどのように対策を講じるか、あらかじめ提示しましたね。いかに社内の抵抗感をなくすかを心がけました」
中矢「ショートドラマは、企画を考えてから撮影、編集を経て投稿するまでに、10日〜2週間ほどの期間しかかけていません。CM制作が放映までに最低でも3カ月かかるとすると、その6分の1ほどの時間で1本の動画をつくっていることになりますね」
梅津「現在は私を中心に、動画を確認してすぐにごっこ倶楽部サイドへお戻しする体制を整えています。施策の効果も見えてきているので、社内でも評判がよく上司からも応援されています。やってよかったなと思いますね」

情報があふれるなか、大切なのはバズり続けること
──ドコモのような大きな会社でありながら、意思決定のスピードを担保できるような体制を構築できたからこそ、この取り組みは実現しているのですね。
中矢「いまの時代は情報があふれていて、一度バズるだけではすぐに忘れ去られてしまうんです。
重要なのはバズるコンテンツを出し続けることで、ごっこ倶楽部はそこを強く意識しながらこれまで取り組んできました。
そのメカニズムをドコモのブランディング施策に活用しようと、ごっこ倶楽部のなかに10人ほどのメンバーからなる専用のチームを用意しています。
現在は週に4本、2作品分の動画をつくり続けられるよう、サイクルをまわしています」
梅津「ドコモ側では私を含めて4人のチームで、毎日届く脚本を確認して、即日お戻ししています。このスピードでの制作はやはり上を通していたら実現できませんし、あらかじめ社内で合意を得て体制を構築したことが週2本の動画投稿を続けられる要因ですね。
また、制作に取りかかる前にはドコモとしてコンテンツに盛り込んでほしい要素や、気をつけてもらいたい表現についてごっこ倶楽部さんとすり合わせを行っています。
それをふまえた確認がくるので、脚本に対して大きな修正をかけることもなく助かっています」

中矢「1本目の動画からほぼいまと同じようなスピード感で制作してきて、だんだんとリズムができて、現在では当たり前のような状態になっていると感じています。
それはすり合わせを受けて、事前に注意点を押さえながらこちらも制作を進められているためです。ドコモさんとごっこ倶楽部、両者がワンチームで取り組んでいるような感覚をもっていますね」
ワンチームだからこそ、結果を一緒に喜べる
──一緒に取り組んでの手応え、そしてこれから先の展開をどのように考えていますか。
梅津「ドコモはもともとTikTokアカウントを広告配信に活用しており、継続的な発信には取り組んできませんでした。
そうした状態からアカウントを立ち上げ直すようなかたちでごっこ倶楽部さんとご一緒し始めたのですが、最初はどのぐらい再生回数が伸びるかが読めず、『まずは1本、10万回再生される動画を投稿する』といった目標を設定していました。
それが10本ほど動画を投稿したところからどんどん再生回数が伸び始め、4月頭に本格的な運用を開始してから約5カ月で、フォロワーは1.8万人から24.3万人まで増えました。
また、投稿した動画の9割以上が100万回再生を超えて、なかには900万回超に達しているものもあります。
またターゲットの施策認知率は、開始後約1カ月で40%を超え(2024年4月、NTTドコモ調べ)、純粋にコンテンツとして楽しんでいただいているだけでなく、『ドコモ』として多くの若者に届けられていることを定量的なデータからも実感できています。
こうした結果が生まれたのは本当にうれしいですし、より高い目標値を設定しながら多くの若者にコンテンツを届けて、ドコモに対する共感を生んでいければと思っています」
中矢「ワンチームという話をしましたが、動画を1つ投稿して終わりではなく年間何十本と継続して投稿してアカウントを育てていくので、やはりチームにならざるを得ません。
脚本を送って急いで確認してもらってという日々を続けているのも、まさにチーム活動ですよね。
だからこそ、何十万フォロワー達成というタイミングで一緒に喜べます。企業同士の取り組みの、新しいかたちだと感じますね」

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。
執筆・編集:加藤智朗
撮影:大橋友樹
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)



 JP
JP























