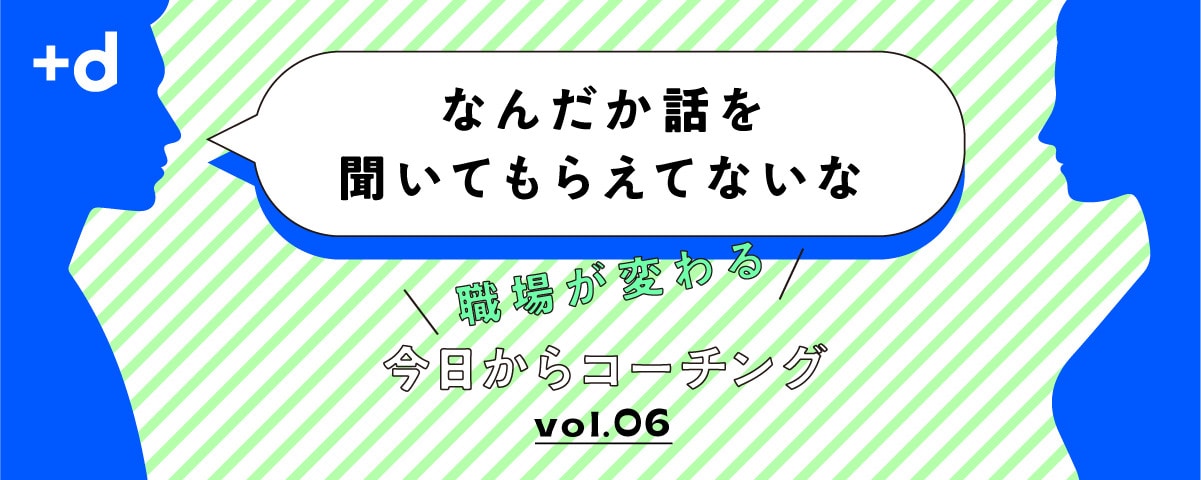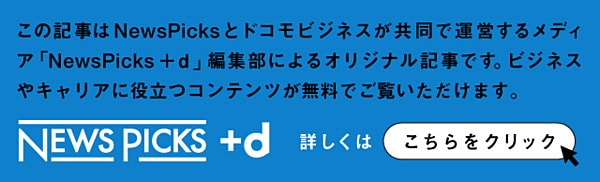「聞く」スキルの前に意識すべきこと
相手の話を聞くことが大切だということは広く認識されていますが、実際には「聞く」という行為について本当に理解している人はまれです。
リーダーの多くは「聞く」ことがマネジメントにおいて重要なことだと理解していながら、実際に「聞く」トレーニングを受けたことがある人はほとんどいません。ですから、本当に他者の話を聞ける人は、実は少ないのです。
巷には「聞く」をテーマにしたスキル本がたくさん出版されていますが、スキルに注目する前に、私たちが意識しなければならないことがあります。それを飛ばしてしまっては、人の話を「聞く」ことはできないでしょう。
そこで今回は、聞く行為の障害になっていることと、良い聞き手になるために私たちが意識すべきポイントを具体的にご紹介します。
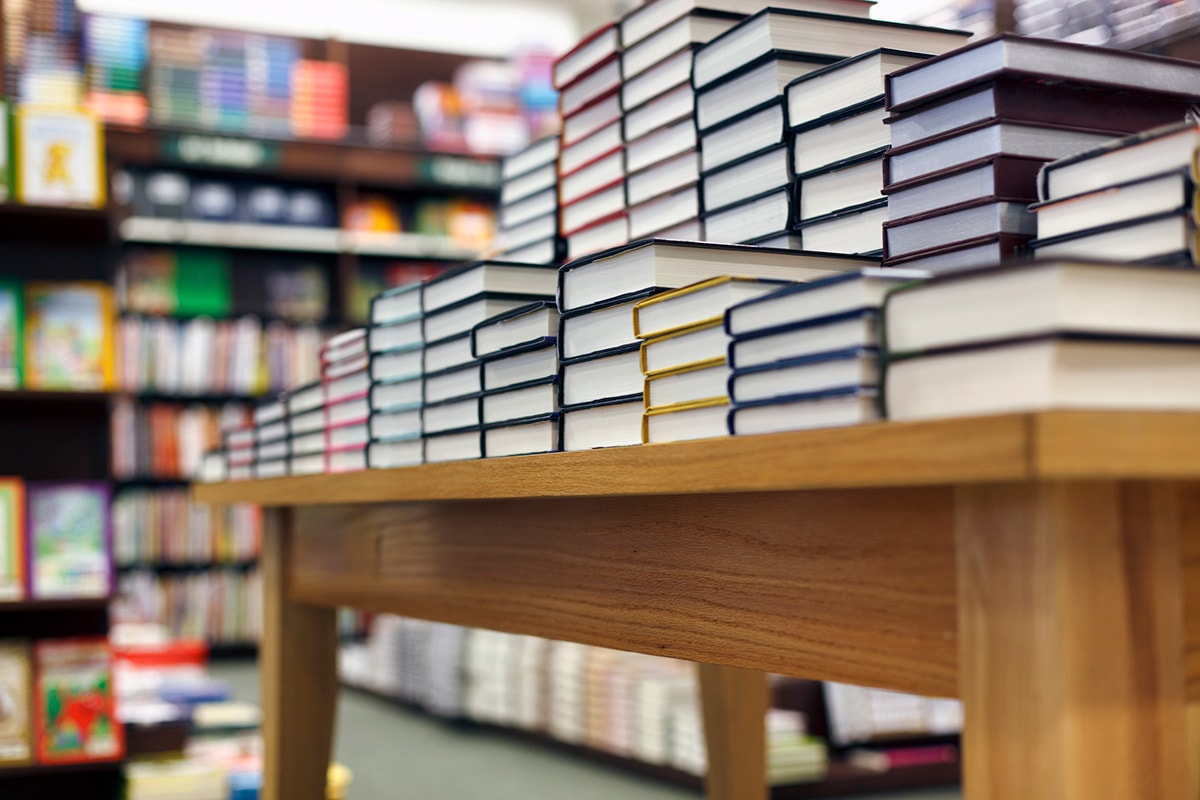
「聞いているように振る舞い」「聞きたいように聞いている」私たち
誰かと会話をしているシーンを振り返ってみてください。
たとえば、ふんふんと相手の話を聞いているふりをしながらも、「この人の意見は、なんだかイマイチなんだよなぁ」と心の中で相手の話を評価していたり、はたまた「そういえば、このあとに大切な会議があったから準備しなくちゃ」などと全然違うことを考えていたり、ということはないでしょうか。
あるいは、相手がまだしゃべっているにもかかわらず、それを遮って自分の考えや質問を挟み込んだことはありませんか? 何か作業をしながら、相手の話を聞いたことは?
これでは「話を聞いているように振る舞っている」だけであって、「相手の話を興味をもって聞いている」ということにはなりません。
もちろん、「いやいや、自分はそんな振る舞いはしない、きちんと相手の話にしっかり向き合っている」とおっしゃる方もいると思いますが、そんな方でも忘れがちな視点があります。
それは、「私たちは、見たいように見て、聞きたいように聞きがちである」ということです。
生物学用語に「レセプター(受容体)」という言葉があります。これは、細胞が情報を受信する器官です。
レセプターはやってきた情報をすべて受け取っているのではなく、受け取ると決めた情報だけを受け入れていると言われています。
これはコミュニケーションで得た情報も同じで、自身では意識できないものの、実は私たちは日々見たいものや聞きたいことしか受け取っていません。

話を聞いているふりは言わずもがな、自分が聞きたいように聞くような振る舞いは、相手に「自分は話を聞いてもらえていないんだな」という思いを抱かせます。場合によっては、自分の存在そのものが否定されたかのような感覚をも引き起こします。
皆さんも、自分が話しているとき、「なんだか話を聞いてもらえてないな」と感じることはありませんか? こういう感覚が繰り返し引き起こされると、人は最終的に孤立感や無力感を感じることになります。
一方で関心をもって話を聞いてもらうことによって、人は「自分の存在が受け入れられている」という感覚を持ちます。この感覚によって、新しいことにチャレンジする気持ちも高まり、結果として、人は行動的になるのです。
自分自身の「前提」と「レッテル」を意識する
では、私たちが良い聞き手になるためには、まず何ができるのでしょうか。
もちろん「良い聞き手になるポイント」はいくつかあるのですが、その前に意識しておきたいことがあります。それが「話を聞く妨げ」となる「前提」と「レッテル」です。
【自分がもつ「前提」に気づく】
生まれてからいままでの経験や育った環境によって、私たちの世界の捉え方、思考のクセは人それぞれ違いますが、私たちはこのことを忘れがちです。無意識のうちに私たちは、他者も自分も同じように世界を捉えていると思い込んでしまい、「ふつうは〇〇するよね」「〇〇するのが当たり前じゃない」というフレーズを使いがちです。
相手の話を「真の意味で聞く」ためには、「相手が見ている世界は自分の見ている世界と違うかもしれない」という点に心を留めることが大切です。まずは相手の発する言葉を評価もせず、否定もせず、また、次々と浮かんでくる「私はこう考えるのに」「この人の言っていることは間違っている」などの思考も、いったん脇に置くように努めます。
次に相手がそのような考えに至った背景を、興味をもって聞いてみて、同時に、自分の主張と前提を相手にも話します。そして、自分の主張や前提を相手がどのように受け取ったのか、どのような印象を受けたのかを聞いてみます。
このようなプロセスを踏まないと、相手とあなたの間に流れる時間が「意見を戦わせ、最終的にどちらが正しいかの勝敗を決めるディベート」になってしまう可能性もあります。

【「レッテル」は脇に置く】
「レッテル」というとネガティブな印象を持つ方もいるかもしれませんが、人間社会の中で生き延びるためには、ある程度必要なものともいえます。長い時間をかけて「この人はどういう人だろう」と考えていては、瞬発的な行動は起こせません。だから、「この人は私に危害を加えない」「この人には気をつけたほうがいい」など、それまで築き上げてきた膨大なデータベースと照合して判断するのです。
一方で、あまりにも レッテルへの依存が強すぎると、そのレッテルを通してしか人を見ることができなくなってしまいます。日常生活の中には、たくさんのレッテルがあります。「あの人は仕事が雑」「あの人はいつもミスをする」「あの人は時間にルーズ」など 、皆さんも一度は他者にそのようなレッテルを貼ったことがあるでしょう。
レッテルを貼ったまま相手の話を聞いていては、その人の新しい一面に出合う機会を逃してしまいます。話を聞くときは、ときに貼っているレッテルを少し脇に置き、「本当はこの人はどういうことを考えているんだろう」「その考えは、どういう経験からきたのだろう」と、興味と関心をもって聞く必要があります。

「良い聞き手」になるための10のポイント
次に、相手の話を聞く環境を整えるためのポイントを見ていきます。
皆さんのまわりには、話しやすい環境をつくるのが上手な人がいる一方、話しやすい環境とはほど遠い雰囲気をまとっている人もいると思います。「相手の話を聞くことが大事」と頭では理解していたとしても、忙しかったり、自分の感情が整っていなかったりする場合、ときに以下のような態度を取ってしまっているかもしれません。
【相手が話しづらくなる 5つの態度】
- 攻撃的な態度 「途中で口を挟む」「険しい顔をする」など
- 優位に立とうとする態度 「相手が話したことを論破しようとする」「勝ち負けなどで自分の立場を示そうとする」など
- 心ここにあらずの態度 「視点を合わせようとしない」「相手の話に対して興味がなさそう」など
- 傲慢な態度 「足や腕を組む」「椅子にふんぞり返る」など
- 神経質な態度 「ペンをいじる」「足を小刻みに揺らす」など
では、良い聞き手になるためには、どのようなポイントを意識すればいいのでしょうか? 10のポイントをご紹介します。
【良い聞き手になるための10のポイント】
- 時間をつくる 5 分でも 10 分でも、相手のために日常的または定期的に時間をつくる。
- 相手を尊重する 「そう思っているんだね」「話してもらってよかったよ」など、相手を承認する言葉を入れると、尊重していることがより伝わりやすくなります。
- 話しやすい環境を用意する「個室をとる」「静かなところに行く」など、話しやすい環境を用意します。
- 最後まで話を聞く相手の話を最後まで聞くことはもちろん、相手が話し終えたあとに数秒待つことも、ときに効果を発揮します。相手が心の奥底に秘めていた思いを口にすることもあるからです。
- 判断しない話を聞いたあとに「それは違うんじゃない ?」などと聞き手が判断を加えることは、「あなたの言うことは受け入れられない」というメッセージにつながってしまうので、注意が必要です。
- 自分が理解しているかどうかを確認する「いま、あなたが言ったことは、つまりこういうことですか?」など、聞いたことをそのまま相手に返して、自分がきちんと理解しているかどうかを確認するのは有効な手段のひとつです。
- 客観的になる感情や先入観が、聞くことの妨げになることがあります。良い聞き手は、自分の考えや感情を脇に置き、客観的な立場に立って、聞くことに専念します。
- 肯定的なノンバーバル ・ メッセージを出すコミュニケーションには、バーバル(言葉によるもの)とノンバーバル(言葉以外のもの)の 2 種類があります。相手の話を聞く際は、「目を見る」「相手のほうに体を向ける」「パソコンから手を離す」など、「聞いているよ」というメッセージをノンバーバルでも示すことがポイントです。
- 沈黙を大切にする沈黙が訪れると、その間に耐え切れず、自分から話を始めてしまう人がいますが、そのときはぐっとこらえてみてください。せかすことなく相手が話し始めるのを待ってみることで、相手が自身の内側からアイデアや思いを言語化する可能性が高まります。
- 聞くことに最大限コミットするポイントの最後は、「話を聞くことが、最終的に相手の目標達成につながる」ということを信じ、聞くことに最大限のコミットをすることです。
今回は、「聞く」をテーマに、「相手の話を聞く妨げ」と「良い聞き手になるための10のポイント」をご紹介してきました。相手に話してもらうには、まず私たち自身が相手の話を聞けているかを振り返りたいところです。
次回は、「聞く」にもつながる「質問」にフォーカスします。相手の置かれた状況を的確に判断し、目的を持って効果的に質問を使い分けるヒントになれば嬉しいです。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。
文:片桐多佳子
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:鈴木毅(POWER NEWS)



 JP
JP