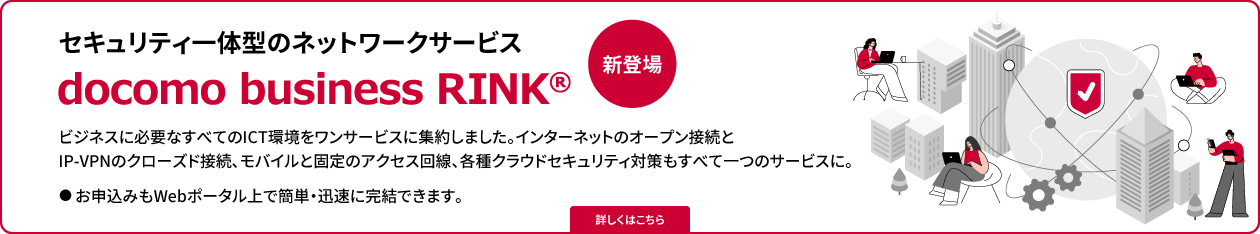選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK
オフィスに縛られないハイブリッドワークを快適にしたい。働く場所に合わせてスピーディかつリーズナブルに最適なネットワークやゼロトラストのセキュリティ対策を導入したい。 いつでも、どこからでも、安心・安全・簡単にセキュリティと一体化した統合ネットワークサービスです。
関連コラム
企業が市場における競争優位性を確立するためには、経営データの効率的な運用が欠かせません。そこで重要となるのが、企業の基幹業務を統合的に管理する「ERP」です。本記事はERPの概要や基幹システムとの違いについて解説するとともに、導入時のポイントや具体的なメリットなどを紹介します。
ERPとは
ERPとは
ERPとは「Enterprise Resources Planning」の頭文字を取った略称で、日本語では「企業資源計画」と訳されるビジネス用語です。ERPを簡潔に定義するのなら、企業の経営資源を統合的に管理するマネジメント手法といえます。
企業の根幹を支えるヒト・モノ・カネ・情報などの経営資源を一元的に管理し、リソース配分を最適化することで、効率的な経営体制を構築することがERPの本質です。本来はこのようなマネジメント手法を意味する概念的な用語ですが、近年では企業の基幹業務を一元管理する統合基幹業務システムを指してERPと呼称する傾向にあります。

ERPが広まった背景
日本でERPが普及し始めたのは2000年代に入ってからであり、市場のグローバル化への対応を目的として、海外市場に向けて事業を展開する企業の間で導入が進みました。グローバル企業にとって海外拠点との情報共有は非常に重要な経営課題であり、現地法人の経営データを的確に把握できなければ意思決定の遅れを招き、致命的な損失につながる可能性があります。
従来は国内企業でも各部門が独立してデータを管理しており、業務連携に支障が生じていました。このような状態では海外拠点との円滑な情報共有は困難であるとして、海外の現地法人を含め、企業の基幹業務を統合管理するERPのニーズが高まったのです。
また、近年多くの企業において重要な経営課題となっている「DX」の実現も、ERPの普及に拍車をかけている理由の1つです。DXとは「Digital Transformation」の略称で、最先端のデジタル技術を活用して経営体制に変革をもたらし、市場の競争優位性を確立するという概念を指します。DXが目指すのは単なる業務のデジタル化やIT活用ではなく、テクノロジーの活用によるイノベーションの創出や優れた顧客体験の提供です。組織の基幹業務を統合的に管理するERPは、現代の企業経営において不可欠なシステムであり、DXの実現の要となるソリューションとして導入が進んでいます。
ERPとは経営資源を効率的に管理・活用する考え方
記事冒頭で述べたように、ERPとは企業の経営資源を統合的に管理するマネジメント手法です。財務・会計・人事・生産・販売・購買などの基幹業務を一元的に管理し、効率的かつ効果的な運用を目指すのがERPの基本的な考え方です。従来、財務会計や生産管理といった基幹業務データは部門単位で管理され、個別最適されていました。しかし、それでは部門単位での効率化は進んでも、組織全体における円滑な部門間連携や生産性の向上は見込めません。
部門間連携の滞りは意思決定の遅延を招き、市場の変化や顧客ニーズへの対応の遅れにつながります。変化の加速する現代市場で市場価値を創出していくためには、迅速かつ的確な意思決定が不可欠です。
だからこそ、企業の基幹業務を統合管理することで経営状況を可視化し、組織全体の情報共有と業務連携を強化するERPの重要性が高まっています。そして、このような基幹業務を一元的に管理するITソリューションを「ERPパッケージ」や「ERPシステム」、または「統合基幹業務システム」と呼びます。
ERPパッケージと基幹システムとの違い
ERPパッケージと基幹システムとの違い

ERPパッケージと基幹システムは混同されがちなソリューションですが、その役割や業務範囲は明確に異なります。基幹システムとは、財務会計や生産管理、あるいは販売管理や購買管理といった基幹部門の業務データを管理するシステムであり、基本的には各部門に設置された個々のシステムを指す用語です。一方でERPパッケージとは、こうした基幹部門の業務データを統合的に管理するシステムを指します。
ERPパッケージは部門ごとに独立している基幹システムを一元化したものであり、それらに加えて顧客情報を管理する「CRM」や定型作業を自動化する「RPA」といった情報系システムとの連携も可能です。つまり、ERPパッケージは組織全体の基幹業務を管理対象とし、基幹システムはあくまでも独立した各部門の基幹業務を管理するシステムといえます。このように、組織全体におけるあらゆる業務データを一元的に管理する機能を備えていることが「統合基幹業務システム」と呼ばれる所以です。
ERPパッケージにおいてデータを統合的に管理する際、各部署がそれぞれ管理しているデータを一元管理することが重要です。
そこで役立つのが、NTTコミュニケーションズが提供する「データ統合インフォマティカ ソリューション」です。インフォマティカ ソリューションは、現在使用している複数のツールを、オンプレミス・クラウド問わず、ネットワーク上で接続し、統合管理できるプラットフォームを実現します。データはもちろん、アプリの統合管理も可能です。そのため、各部門が必要なときに必要な情報を確認、取得、活用できる環境を構築できます。
ERPのメリット
ここからはERPシステムの導入によって得られる具体的なメリットについて解説します。
生産性が向上する
ERPシステムの導入メリットとして挙げられるのが労働生産性の向上です。労働生産性とは、従業員一人あたりが生み出す生産量や付加価値額を定量化したもので、「産出量÷労働投入量(従業員数×労働時間)」という数式で表すことができます。労働生産性を高めるためには、いかにして最小の労働投入量で最大の産出量を創出するかが重要な課題です。ERPシステムは部門ごとに分断されていた基幹業務を一元的に管理し、部門を跨いだ情報共有や業務連携を可能にします。結果として業務の効率化と標準化に寄与し、より少ない労働投入量で成果を生み出せるようになり、労働生産性の向上につながります。
スピーディーで的確な経営判断ができるようになる
企業を取り巻く環境は常に変化しており、事業活動において迅速な経営判断や意思決定は非常に重要な要素です。変化の加速する現代市場において、経営判断の遅れは市場の参入機会や商品の販促機会の損失につながりかねません。ERPシステムの導入によって基幹業務が統合管理されることで、経営状況をリアルタイムに可視化できるようになり、スピーディーな経営判断や意思決定が可能になります。結果として、市場の需要や顧客ニーズの変化に対して、的確かつ柔軟に対応できる経営体制の構築につながります。
内部統制が強化できる
企業には経営理念やビジョンといった目的があり、ゴールへ到達するためには効率的かつ効果的な運営が求められます。そこで重要となるのが、組織内のルールや仕組みを整備する内部統制です。
企業が発展し続けるためには、組織に関わるすべての従業員が理念やビジョンを共有し、同じ方向に向かって進まなくてはなりません。そのためには、全従業員が社内ルールや法令を遵守する体制を整備しなくてはならないのです。ERPシステムはあらゆる情報を統合的に管理することで社内の仕組みを整備し、ガバナンスとコンプライアンスの強化に寄与します。
ERPのデメリット
ERPのデメリット
物事とは表裏一体であり、メリットの裏には必ずそれ相応のデメリットが存在します。たとえば、ERPシステムのデメリットとして挙げられるのが、セキュリティインシデントの危険性です。ERPシステムには、顧客情報や従業員の個人情報、または製品開発情報や人事考課情報といった機密情報が保管されています。そのため、これまで以上に強固なセキュリティポリシーを整備し、データガバナンスの重要性を周知徹底しなくてはなりません。
また、ERP製品は種類が多く、ソリューションの選択が難しいという問題もあります。さまざまな企業から多種多様なERP製品がリリースされており、自社の企業規模や事業形態に適したシステムを選択するためには、ERPと経営に対する深い知見が必要です。さらにERPシステムの導入はパッケージのライセンス費用だけでなく、サーバーやネットワーク機器などの導入・管理費用など、莫大なコストがかかります。

主なERPの種類
ERPシステムは大きく分けると2種類に分類されます。それが「統合型」と「コンポーネント型」の2つです。ここからは統合型とコンポーネント型のERPシステムについて解説していきます。
統合型
統合型のERPシステムは、財務・会計・人事・生産・販売・購買など、基幹部門の業務データを管理するために必要な機能が網羅されたソリューションです。会計や人事といった間接部門や、仕入れから販売に至るサプライチェーン管理はもちろん、オフィスソフトやグループウェアといった情報系システムとの連携も可能なオールインワンタイプのERPシステムを指します。非常に多彩な機能を搭載しており、組織全体の経営資源を一元的に管理できるものの、価格については高額な傾向にあります。
柔軟なコンポーネント型
コンポーネント型とは、必要な部門の基幹システムだけを組み合わせるタイプのERPシステムです。必要最小限の基幹システムのみを導入できるため、企業規模や事業形態に合わせて柔軟なシステム環境を構築できます。また、事業の拡大に伴って新たな機能が必要になれば、自由に追加できる拡張性の高さもメリットの1つです。しかし、柔軟性と拡張性に優れる分、必要な機能の取捨選択が必要なため、システム設計時に高度な知見が求められます。
クラウドERPとは
近年、クラウドファーストの流れが加速しており、ERPシステムの主流もオンプレミス型からクラウド型へと移行しつつあります。ここからは、クラウド型とオンプレミス型の違いを解説するととも、クラウドERPのメリットやデメリットについて見ていきましょう。
クラウドERPと従来のオンプレミスERPとの違い
オンプレミス型のERPは、システム構築に必要なサーバーやネットワーク機器などを自社で導入して管理します。一方でクラウド型のERPは、クラウドコンピューティングサービスを活用し、クラウド環境に構築されたプラットフォーム上でERPシステムを運用します。つまり、クラウド型とオンプレミス型の最も大きな違いは、ERPシステムの運用基盤が自社サーバーかクラウドプラットフォームかという点です。
その他の違いを挙げるとすれば、オンプレミス型のERP製品は基本的に買い切り型であるのに対し、クラウド型は月額課金制や従量課金制のサービスが多い傾向にあります。また、オンプレミス型はバージョンアップやセキュリティパッチの適用もユーザー自身で設定しなくてはなりません。それに対してクラウド型は基本的に無償アップデートが可能であり、常に最新バージョンを使用できる点がオンプレミス型との違いです。
クラウドERPのメリット
オンプレミス型はカスタマイズの自由度が高く、独自のセキュリティポリシーを設定したり、必要に応じて他システムとの連携を図ったりと、自社の運用形態に適したシステム環境を構築できます。しかし、サーバーやネットワーク機器などの導入に莫大な費用を必要とし、さらにそれらを管理する施設やエンジニアも必須です。クラウド型のERPシステムはオンプレミス型のように、サーバーやネットワーク機器などのITインフラを必要としません。そのため、システム導入費用の大幅な削減が可能です。
ERPシステムをクラウド環境に移行することで、情報システム部門の保守・管理などの業務負担が軽減されるため、ITインフラの管理コストや人件費の削減につながります。それと同時に余った人的資源を企業価値の向上に直結するコア業務に投入できる点も大きなメリットです。また、企業の基幹業務データがクラウド上に集約されているため、インターネット環境さえあれば時間や場所を問わず情報にアクセス可能になり、多様かつ柔軟なワークスタイルの実現に貢献します。
クラウドERPのデメリット
クラウド型のERPシステムは基本的に初期費用が不要で、月額課金制か従量課金制のサービス形態が多い傾向にあります。初期費用の大幅な削減が可能ですが、毎月のランニングコストが必要となり、従量課金制は使用量によって支払額が変動するため、費用の流れを一定に保つのは困難です。また、クラウドサービスは、その利便性の高さと引き換えにベンダーへの依存度が高く、ロックインのリスクが高まります。インターネット環境に依存する点や、カスタマイズ性に乏しく必要な機能要件を満たせない可能性があるというのも、クラウドサービスの大きなデメリットです。
ERP導入のステップ
ERP導入のステップ

ERPシステムを導入、もしくは刷新する場合、既存の基幹システムからのデータ移行や情報系システムとの連携が必要です。移行プロセスそのものは非常にシンプルで、「旧システムから必要なファイルを抽出して新システムに組み込む」と要約できます。しかし、旧システムから新システムへの移行にはファイルの破損やデータ移行の遅延など、さまざまなリスクや不具合が考えられます。そのため、あらゆるリスク要因を把握した上で、適切な導入プロセスを整備しなくてはなりません。ここからはERPシステムの具体的な導入ステップについて解説します。
プロジェクトチームを作る
ERPシステムを導入・移行する際の第一歩はプロジェクトチームの組成です。そして、ERPシステムを導入する目的やメリット、機能要件と非機能要件などを明確化してメンバー全員で共有します。その際に重要となるのがシステムアセスメントです。アセスメントとは、IT分野ではシステム導入やデータ移行時の運用体制や動作環境を分析・評価する施策を指します。部署の枠を超えて発言できる役職者と関係部署から知見を備えた担当者を選び、要件定義とともに現状を調査し、あらゆるリスクに備えた万全の導入計画を立案する必要があります。
業務を把握する
システムアセスメントと同時に、業務の棚卸しも非常に重要なプロセスです。ERPは企業の基幹業務を統合管理するシステムですが、万能のツールではありません。たとえば、原材料の調達から製品の販売に至るサプライチェーンの流れを可視化できても、ビッグデータ分析や多次元分析などの高度な解析には不向きです。そのため、基幹部門の業務を棚卸しし、ERPシステムで管理可能な分野と不可能な領域を明確化しなくてはなりません。また、業務の棚卸しをすることで各部門の業務プロセスが可視化され、明確な要件定義が可能になるというメリットもあります。
業務フローを構築する
新たに導入したシステムを効率的に運用していくためには、多くの場合において従来の業務フローを変更する必要性が生じます。したがって、ERPの導入ベンダーや関係部署と相談しながら、新しい業務フローを構築しなくてはなりません。ここで活きるのが、先述したシステムアセスメントや業務の棚卸しです。システムアセスメントや業務の棚卸しによって現状のシステム環境や業務プロセスを的確に把握できれば、明確な要件定義や改善点の抽出が可能になります。ERPシステムの導入によって業務プロセスに生じる変化を可視化できるため、必然的に新しい業務フローの策定につながります。
ERPは導入して終わりではありません。企業全体からERPに集約されたデータを有効活用するためにも、「データ統合インフォマティカ ソリューション」の導入をおすすめします。
インフォマティカ ソリューションはERPだけでなく、SaaSやAWSなど、さまざまなデータを統合管理できます。
インフォマティカ ソリューションによってデータを統合することで、ERPで集約したデータについても、ERP導入のプロジェクトチームだけでなく、各部署で必要なデータを取得できるようになるため、非常に利便性に優れています。
ERPを選ぶポイント
ここからは、ERPシステムを選ぶポイントについて見ていきましょう。重要となるのは自社の事業形態や経営戦略に沿ったシステムを選択することです。具体的には「機能改変や追加ができるか」「自社が求める機能・特徴があるか」「セキュリティ機能が十分か」の3点に着目する必要があります。
機能改変や追加ができるか
ERPシステムを選択する上で、機能の改変や追加といった拡張性と柔軟性は非常に重要なテーマです。ITシステムに求められる機能要件は、自社の環境や市場の変化によって変化します。たとえば、Webサービスを運営していてユーザー数が増加した場合、大量のトラフィックに耐えられるサーバーを構築しなくてはなりません。このようなケースの場合は拡張性に優れるクラウド型のERPシステムが適しています。オンプレミス型のスベックを拡張するためにはサーバーの増設が必要なため、導入費用や管理コストといった負担が増大します。
しかし、クラウド型のERPはシステム環境がベンダーに依存するため、自由なカスタマイズはできません。そのため、システム環境の柔軟性という観点では、オンプレミス型のERPシステムに軍配が上がります。また、クラウド型とオンプレミス型を組み合わせた、ハイブリッド環境を構築できるERP製品もリリースされています。ERPシステムを導入する際は導入後の拡張性や柔軟性を踏まえた上で、自社に適したソリューションを選択することが重要です。
自社が求める機能・特徴があるか
ERPシステムを選択する際は、自社の事業活動に不可欠な機能要件と非機能要件を明確に定義し、それらと照らし合わせながら検討しなくてはなりません。たとえば、規模の大きな製造業や流通業を営む企業であれば、会計管理や人事管理、生産管理や販売管理、在庫管理や購買管理など、あらゆる基幹部門の業務データを統合管理する必要があります。このような企業であれば、オールインワンタイプの統合型ERPシステムが不可欠です。
しかし、インターネットメディア運営やWebサイト制作などを展開しているベンチャー企業などは、製造業や流通業と比較した場合、必要な基幹システムが少ない傾向にあります。情報通信業やソフトウェア業は基本的に在庫を保有する必要がないため、中小規模の企業であればコンポーネント型のERPシステムが適しているかもしれません。このように、ERPシステムを選択する際は、自社の企業規模や事業形態を考慮し、必要な機能や製品の特長を理解した上で選択する必要があります。
セキュリティ機能が十分か
企業にとって情報セキュリティの強化は最も大切な経営課題の1つです。先述したように、ERPシステムには、顧客情報や従業員の個人情報、製品開発情報や人事考課情報といった機密情報が保管されています。そのため、ERPシステムを選択する際は、堅牢なセキュリティ機能が備わっているかどうかが非常に重要なポイントです。たとえば、アクセス権限設定や職務分掌の規定、ユーザー認証やID認証といったセキュリティ機能が搭載されている製品を選択する必要があります。
また、ERPシステムの導入を考慮する上で重要なポイントが「GRC」です。GRCとは、企業倫理を統制する「ガバナンス(Governance)」、事業活動における「リスク(Risk)」の管理、法令やルールを遵守する「コンプライアンス(Compliance)」の頭文字をとった略称で、経営体制の統合的なリスクマネジメント手法を指します。ERPシステムの運用効率を最大化し、事業活動におけるリスクを最小化するためには、GRCを強化してセキュリティ体制を整備しなくてはなりません。そのため、ERPシステムを選択する際はGRCの観点にもとづき、セキュリティ要件を満たす製品を選択する必要があります。
20世紀半ばにコンピューターが発明され、わずか半世紀足らずで世の中に情報革命をもたらし、さまざまな産業が発展を遂げました。しかし、経済の発展は苛烈な競争原理の上に成り立っており、市場の競争性は激化の一途を辿っています。このような社会的背景のなかで企業が競争優位性を確立するためには、経営資源の効率的な運用が不可欠です。ERPシステムは企業の経営資源を統合管理し、経営状況の可視化や意思決定の迅速化に寄与します。DXを実現するためにもERPシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事の目次
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK
サービスに関するご質問など
お気軽にお問い合わせください
資料ダウンロード
-
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK
サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください
サービス詳細情報はこちら



 JP
JP