 Business/Technology
Business/Technology
NTTコミュニケーションズ
ソリューションサービス部
村木 奏介

新規ビジネスの創出や社会実装を
目指す事業共創の場です
産業・地域DXプラットフォーマーとして
企業と地域が持続成長する社会を目指します
地域社会を支える皆さまと地域課題の解決や
地域経済のさらなる活性化に取り組みます
旬な話題やお役立ち資料などDXの課題を解決するヒントをお届けする記事サイト
課題やニーズに合ったサービスをご紹介し、
中堅中小企業のビジネスをサポート!
モバイル・ICTサービスをオンラインで
相談・申し込みができるバーチャルショップ
2023年7月14日、愛媛県四国中央市のHITO病院にて「医療現場におけるスマートグラスを活用した未来型看護実現の実証実験」がスタートした。
この取り組みを手がけているのは、ICTを駆使した課題解決を積極的に推進する社会医療法人石川記念会HITO病院と、株式会社スマートゲート、NTTコミュニケーションズ株式会社(以下、NTT Com)だ。この3者の強固なパートナーシップはいかにして生まれ、実証実験で、何をめざしたのか。
HITO病院 DX推進室で技術を担当するHIA(Hospital Infrastructure Architect)の村山公一さん(以下、村山さん)、スマートゲートのシステム開発主任である花谷直徹さん(以下、花谷さん)、そして、5G&IoTサービス部 メディカルビジネス推進チームの内村健一さん(以下、内村さん)に、実証実験にかける思いを聞いた。
医療業界の共通課題とされている「ICT導入の遅れ」。センシティブな患者の情報を取り扱うことや、間違いが許されない業務の特性も、ICT導入をためらわせている大きな要因といえる。
そうした医療業界にあって、HITO病院が、NTT Comのサポートを受けながら2018年に院内コミュニケーションツールとしてiPhoneを採用したのは、エポックメイキングな事象だった。
HITO病院は、以後、先進的なICTの活用を積極的に行ってきた。将来的に医療機関での普及が見込まれる「スマートグラスを活用した未来型看護」プロジェクトは、その集大成的な取り組みとなる。その目的について、村山さんは「すべては現場のため」と説明する。

病室のネットワークカメラで捉えた患者の映像が、スマートグラスのモニターに投影される
HITO病院が地域医療を担う宇摩医療圏は、人口の減少とともに、高齢化が進展している。国立社会保障・人口問題研究所が2023年12月に算出した将来人口推計によると、2020年に82,754人だった人口(国勢調査)は、2050年には51,455人となり、高齢化率は46.0%にも達するとされる。高齢化率の高まりは、医療ケアや介護などのニーズの増加に直結する。HITO病院のような医療機関は、働き手が減少する中、限られた人員で地域の医療ニーズに対応していくことが求められているのだ。
ICT活用によって効率的な働き方を可能にすることは、人口減少時代の医療従事者の人手不足への対応と共に、働く人から選ばれる病院、持続可能な病院の実現につながる。効率的に働くことで創出できた時間は、新たなケアにあてることができる。「ICTの活用は最終的に、提供する医療の質の向上に結びつく」。村山さんは、そう力を込める。
すべては現場のためーー。医療現場の課題解決をめざした協働プロジェクトは、確たる信念の下、進んでいくことになる。
HITO病院の働き方改革において、課題となっていたのは「夜勤帯の看護」だった。
例えば、夜間のナースコール対応。高齢の入院患者の中には加齢性難聴などの影響で会話がスムーズにできず、看護師が病室に駆けつけて応対しなければならないケースも少なくない。一晩に何度も病室とナースステーションの往復を余儀なくされる状況は、看護師にとって大きな負担となるばかりではなく、同部屋の他の患者の安眠を妨げることにもなってしまう。コロナ禍のような状況になれば、病室間の移動も極力避けなければならない。病室への出入りを少なくすることは、必達の改善課題だった。
そこで生まれたアイデアが、スマートグラスとネットワークカメラを連携し、入院患者を遠隔で見守る「未来型看護システム」だ。

未来型看護の実現に向けて活躍するスマートグラス
病室に設置したネットワークカメラの映像をスマ-トグラスに投影し、離れた場所から病室の患者を見守ることが可能に。他の患者を介助している最中にナースコールが鳴っても、映像で患者の様子を確認し、病室に駆けつける必要があるかどうかをいち早く判断し適切に対処することができる。スマートグラスを介せば、看護師間での情報共有もスムーズで、映像・音声による双方向コミュニケーションもハンズフリーで実現する。
「未来型看護システム」は、看護師たちの負担を軽減するためには、不可欠なものだった。
「未来型看護システム」の活用によって、夜勤帯の看護の心理的・身体的負担の軽減を図ることができるはずだった。ところが、実際にスマートグラスにネットワークカメラの映像を投影すると、期待したほどのパフォーマンスが得られない。
「フレームレートが低く、映像が滑らかでなかったり途中で切れたりすることがあって、患者様の様子を正確に把握しきれないことが分かった」と村山さん。実用には不安が残った。
対策を模索した内村さんは、新たにスマートゲートの花谷さんの参画を求めることにした。「花谷さんは、オンライン診療システムを手がけてきた実績を豊富に持ち、医療業界にもICTにも明るい。心強いパートナーだと考えた」

左から花谷さん、内村さん、村山さん。花谷さんの参画で、プロジェクトは一気に加速した
花谷さんは、カメラの映像をスマートグラスにスムーズに投影するために、アプリケーションを新たに開発。加えて、複数機種のスマートグラスを活用できるようシステムの見直しも図った。改善したシステムを試した看護師からは「早く使いたい」という声が上がるほど、現場の期待を膨らませる仕上がりとなった。
壁を突破し、実用に向けた実証実験の準備は整った。花谷さんは、チームになくてはならない存在となった。
こうした経緯を経て、実証実験が始まった。すぐに花谷さんが、新たな動きを見せる。
「オンライン医療システムを提供していても、病院の業務フローに詳しいわけではない。看護師など関係者とのより直接的なコミュニケーションをとりたい」と、2023年末に活動の拠点を、それまでの宮城県塩竈市からHITO病院に移したのだ。
花谷さんは、実証実験を「医療現場の事情や要望、診療の課題などを知る機会になり、将来の技術やプロダクツ開発のヒントをもらえる場」と考え、現場の実際の反応を見ながら、カメラの機能のブラッシュアップやシステムのアップデートを行い、その精度を一段二段と高めていった。
村山さんのもとに集まる現場からのフィードバックや、現場で生まれる思いがけないアイデアを、花谷さんがシステムに組み込んでいく。そして内村さんが、その両者をつなぐとともに、通信分野のインフラを手がける中で培われた幅広い視点で、システムを外部にも展開できるものに仕立てていく。
「このような対応が可能なのは、村山さんや花谷さんと、お互いの役割を大切にしながらしっかりとタッグを組めているから。2人はかけがえのないパートナー」だと内村さんは言う。
夜勤帯の看護師の働き方の改善に役立つことが検証できれば、システムの利用を「全国各地の医療機関で働く方たちに広げたい」と意気込む村山さん。少子高齢化による医療の担い手不足は、決してHITO病院のある四国中央市に限った問題ではないのだ。

さらなる使いやすさ向上のため、看護現場でトライアルを重ねる
村山さんは、実証実験から見えてきたこととして、「他の医療機関や業界への水平展開には、コストもさることながら、平準化と導入の簡便性を磨くことが大切」と、その重要性を挙げる。「iPhoneを導入した際に、マニュアルがなくても使えることに改めて気づいた。スマートフォンと同様に、誰もが直感的に使えるシステムであることが必要」と語る。
近年、医療現場では働く人の年齢がより幅広くなり、外国人医療従事者が増えて国籍も多様化している。となれば、「誰もが」の範囲がこれまで以上に広くなっていることは疑いようのない事実だ。内村さんは、そうした幅広い利用者にとっての「使いやすさ」を実現するには、「今回の実証実験のようにトライアルの場を設けて確認するなど、きめ細かな対応や工夫が不可欠」になると語る。
一方、直感的なインターフェースにするために、花谷さんが求めるのは「ユーザー体験と、今以上の医療現場とのコミュニケーション」。システムを使った際の印象や感覚といったものを、丁寧なコミュニケーションを通じてすくいとり、「インターフェースのデザインに生かすことが必要」と語る。
今回の実証実験について、内村さんは「全国共通の地域医療の解決に、通信やDXといった切り口で手助けできることを示せた」と話す。
村山さんは、「新しいシステムに対して、ただ提供されて使うだけではなく、3者の連携体制のおかげで当事者として向き合うことができた。この経験は大きい」。花谷さんは「現場とのコミュニケーションの中からしか、新しいものは生まれないことを確認できた」と語っており、それぞれに大きな手応えを感じている。
「未来型看護システム」は、サービス化に向けた検討を引き続き3者で進め、2024年度のリリースをめざしている。内村さんは、「NTT Comの販売網を生かして、全国の病院に向けた提案体制を構築し水平展開するとともに、現場の声をさらに拾い上げて、IoTを活用した患者からの呼び出し機能やAI活用など、段階的な機能拡充や先進技術の活用検討を進めていきたい」と意気込む。

ビジョンを共有して3人は未来へ向かう
少子高齢化や働き方改革といった課題の解決は、「10年、20年先の未来をつくること」と言い換えることができる。
「私たち3人は、未来にいちばん近い位置にいて、未来を共につくるパートナー」
「取引先ではなく、ビジョンを共有するチームとして未来に向かいたい」
DXによる医療現場の働き方改革という大きなミッションに挑む3人は、今日も同じビジョンを描き、地域医療の明るい未来を見据えている。

HITO病院
理事長
石川賀代さん
医療現場ではこれまで、セキュリティの名のもとに、クラウドサービスやクラウド前提で動くスマートデバイスの導入に消極的でした。しかし、コロナ禍を経た今、ようやく転換点に差し掛かっています。スマートフォンやスマートグラスの導入により、時間と場所に縛られることなく、医師・メディカルスタッフと患者・家族がつながることで、より質の高い患者ケアを提供することが可能となります。また、働き手の確保が難しくなる中で、スタッフの業務効率化と負担軽減にも寄与します。

HITO病院
脳神経外科部長
CXO(Chief Transformation Officer)
CHRO(Chief Human Resource Officer/最高人事責任者)
篠原直樹さん
今後、少子高齢化が加速する中で地域医療を持続していくためには、限られた人材で地域医療を支えるネットワーク環境の整備が必須となります。病院や施設といった事業所単位ではなく地域単位で、さまざまな事業所の専門職が手を取り合って、互いに助け合いながら地域の高齢者を見守っていく必要があるのです。これを実現するためには〈カルテの共通化〉〈コミュニケーションのオンライン化〉〈遠隔医療のインフラ〉が必須となり、いずれもICT活用が必須です。
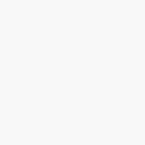
NTTコミュニケーションズプラットフォームサービス本部 5G&IoTサービス部
内村 健一
5Gサービス部門第七グループ第一チームでは、医療業界領域特化のチームとして病院DXの提案支援業務を行っています。高齢化社会化を背景に地域における医療の担い手不足や医療サービスの均てん化など、医療業界は数多くの課題を抱えています。課題に対し、病院DXを基軸に病院と伴走支援しながら解決策を模索し、持続的な地域の医療の発展に貢献します。
 Business/Technology
Business/Technology
NTTコミュニケーションズ
ソリューションサービス部
村木 奏介


 JP
JP
