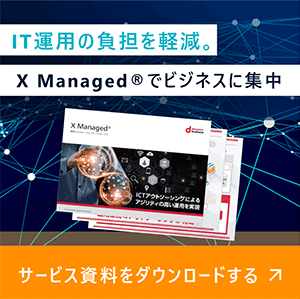マルチクラウドとは?
メリットや進め方について解説

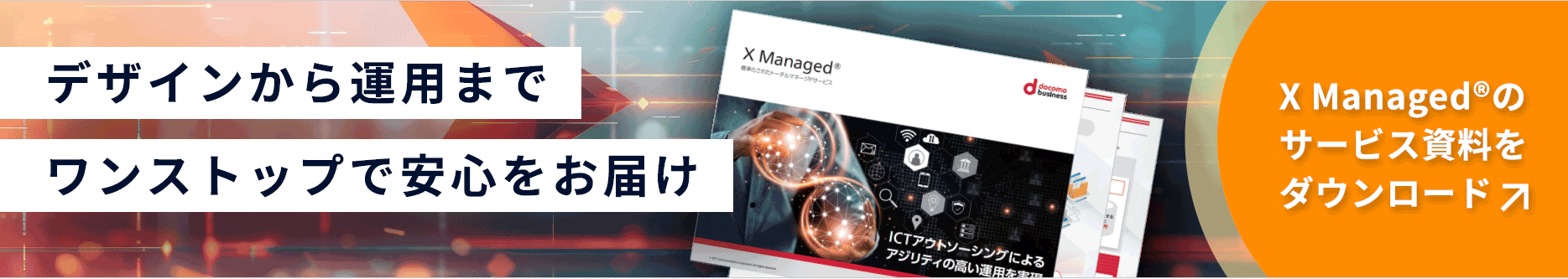
マルチクラウド戦略とは、複数ベンダーのクラウドサービスを組み合わせて活用するITインフラ戦略のことです。近年、クラウド活用が進む中で、単一ベンダーへの依存リスクを回避し、柔軟性や安定性を高めるために注目されています。
日本でも生成AIやメタバースなどのデジタル革新が進む一方、企業のDX推進においては、データの利活用やクラウドインフラの最適化が重要課題となっています。
そこでこの記事では、「マルチクラウドとは何か?」という基本からメリット・デメリット、戦略策定のポイント、実践ステップまでをわかりやすくご紹介いたします。
マルチクラウドとは
マルチクラウドとは、複数ベンダー(例:AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなど)のパブリッククラウドサービスを併用する戦略的なITインフラ運用のことを指します。
単一ベンダーに依存せず、それぞれのクラウドサービスが持つ特長を活かして、企業のニーズと選択に合わせた柔軟な構成を実現できる点が大きな特徴です。
特に、クラウド活用が高度化する現在においては、業務システムやアプリケーションごとに最適なクラウドを使い分けることが、コストの最適化やシステム全体のパフォーマンス向上、そして事業継続性の確保にもつながります。
ハイブリッドクラウドとの違い
マルチクラウドは「ハイブリッドクラウド」と混同されることがありますが、両者は明確に異なります。ハイブリッドクラウドが「オンプレミス環境とクラウド(パブリッククラウド、プライベートクラウド)の組み合わせ」であるのに対して、マルチクラウドは「複数のクラウドベンダーを横断的に活用」する点がポイントです。
マルチクラウドのメリット
マルチクラウド戦略を採用することで、企業のIT基盤にさまざまなメリットがもたらされます。
可用性の向上
複数のクラウドサービスを併用することで、万が一、特定のクラウドベンダーでトラブルが発生した場合でも、ほかのクラウドサービスで業務を継続できます。
これにより、サービス停止によるビジネスへの影響を最小限に抑えることができ、可用性の高いITインフラを構築することが可能です。
たとえば、データベースはA社のクラウドで運用し、アプリケーションはB社のクラウドで稼働させるといった分散配置により、サービスの冗長性を確保できます。
柔軟性の向上
ベンダーごとに提供されている機能や価格体系は異なるため、システムやサービスごとに最適なクラウドを選定することで、柔軟な運用を実現できす。
ワークロードの特性や要件に応じて、最適な環境を選べる点は大きな強みです。
たとえば、AIの開発環境はGPUに強みを持つクラウドを選定し、ERPシステムは安定性を重視したクラウドを活用するなど、目的に応じた最適化が図れます。
リスクの分散・回避
単一のクラウドベンダーに依存する構成(シングルクラウド)は、故障発生時やベンダーのサービス改定、コスト変更などの影響を直接的に受けるリスクがあります。
一方、マルチクラウドを活用することで、そのようなベンダーロックインから脱却し、リスクを分散できます。
また、地域や業界特有のコンプライアンス要件にも柔軟に対応可能なため、複数ベンダーの選択肢を持つことで、将来的な事業拡張や海外展開時も有利に働きます。
マルチクラウドのデメリット
マルチクラウド戦略には多くのメリットがある一方で、導入や運用においては注意すべき課題も存在します。
ここでは、マルチクラウドを採用する際に直面しやすいデメリットについて解説します。
運用管理の複雑化
クラウドサービスごとに管理コンソールや仕様、設定方法が異なるため、複数ベンダーを同時に扱うことで運用負荷が高まる点はデメリットです。このため、アカウント管理やネットワーク構成、リソースの監視・メンテナンスなど、情報システム部門に求められるスキルと工数が増える傾向があります。
特に、システムごとのログ収集や故障対応を統合的に行うには、横断的なモニタリングや自動化ツールの導入が欠かせません。
運用体制の整備を怠ると、クラウドの利便性が逆にリスクとなってしまう可能性があるでしょう。
コスト管理の増加
マルチクラウドでは、利用するクラウドサービスごとに料金体系が異なるため、コストの全体把握や最適化が難しくなる点もデメリットです。
従量課金による料金の変動、割引プランやリザーブドインスタンスの管理など、多様な料金モデルを理解した上での調整が必要です。
クラウドの利用状況を継続的に可視化し、コストの無駄を排除する仕組みを導入しなければ、想定以上の支出につながる恐れがあります。
セキュリティリスクの増加
複数のクラウド環境をまたぐことで、セキュリティ対策の一貫性を保ちにくくなるというデメリットもあります。アクセス制御や暗号化ポリシー、認証プロトコルなどの管理が複雑化し、セキュリティギャップが発生しやすくなるのです。
また、クラウドごとのコンプライアンス要件に対応する必要があるため、運用ルールの明確化や統一的なセキュリティガバナンスの整備が欠かせません。
マルチクラウド戦略の進め方
マルチクラウドの導入は、単に複数のクラウドサービスを契約することではありません。企業全体のIT戦略と整合させた上で、段階的に進める必要があります。
ここでは、マルチクラウド戦略を成功に導くための基本的な流れをご紹介します。
導入目的を明確にする
まずは、「なぜマルチクラウドを導入するのか」という目的を明確にしましょう。
たとえば、災害時の可用性確保、特定サービスへの最適化、ベンダーロックインの回避など、導入目的が戦略全体の軸となります。
目的や目標が曖昧なままだと、無駄な構成や運用コストの増大につながるため、注意が必要です。
サービスを選定する
次に、導入目的や業務要件に応じて、最適なクラウドサービスを選定し組み合わせましょう。
ビッグデータ解析に強いGoogle Cloud、企業内システムとの親和性が高いMicrosoft Azure、高い柔軟性とグローバル展開に向けてはAWSなど、それぞれの強みを把握した上で選びましょう。
さらに、サービス同士の連携性や、セキュリティ・運用性も含めて評価することが重要です。
移行計画を立てる
オンプレミスやデータセンターからのマルチクラウド環境への移行は、一度にすべてを切り替えるのではなく、段階的に進めることが基本となります。
移行の対象となるアプリケーションやデータを洗い出し、既存システムの依存関係やデータの可搬性を確認しながら、優先順位をつけて移行計画を立てましょう。
また、移行時のトラブルに備えてバックアップ体制やロールバック手順を整備しておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。
運用状況を確認し継続的に改善する
マルチクラウド導入後は、運用状況を定期的にモニタリングし、課題を明確にして継続的に改善を行いましょう。
ITインフラは変化し続けるため、たとえば、コストの最適化やパフォーマンスの向上、セキュリティ体制の見直しなど、定期的な棚卸しと調整が欠かせません。
このような改善サイクルを仕組みとして持つことで、マルチクラウドの利点を最大限に活かすことができます。
まとめ
マルチクラウド戦略は、企業のITインフラに柔軟性と安定性をもたらし、単一クラウドの限界を補完する有効な手段です。
可用性の向上やリスクの分散、クラウドサービスごとの最適利用といった多くのメリットがある一方で、運用やコスト、セキュリティ管理の複雑さといった課題も存在します。
そのため、マルチクラウドを成功させるには、「導入目的の明確化」から「サービス選定」「移行計画」「運用体制の整備」まで、計画的かつ段階的に取り組む必要があります。
また、複数クラウドの運用を効率化し、継続的に最適化していくには、専門的なノウハウを持つ支援サービスやソリューションの活用もおすすめです。
たとえば、ドコモビジネスが提供する「X Managed(クロスマネージド)」は、設計・構築から運用・改善までをトータルにサポートするマネージドサービスです。サービス利用によって、運用負荷の軽減と、継続的な最適化の支援を受けられます。
マルチクラウドを導入される際は、ぜひご利用をご検討ください。